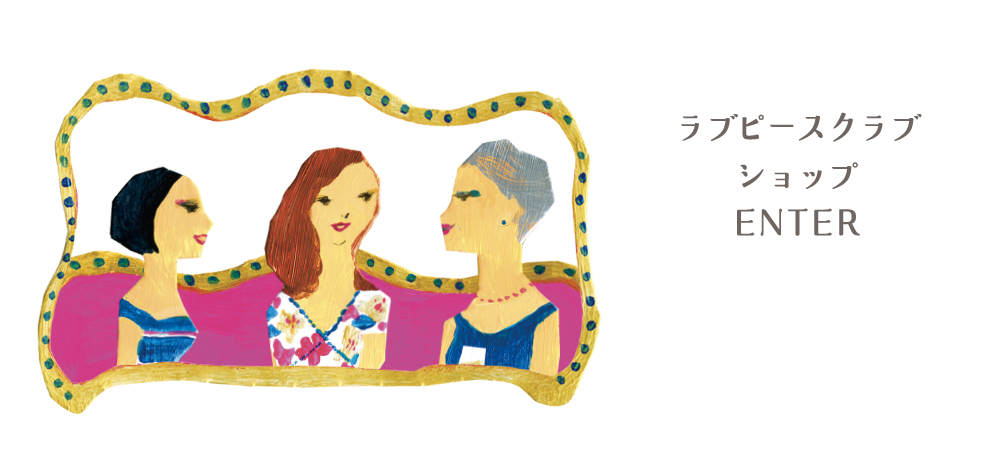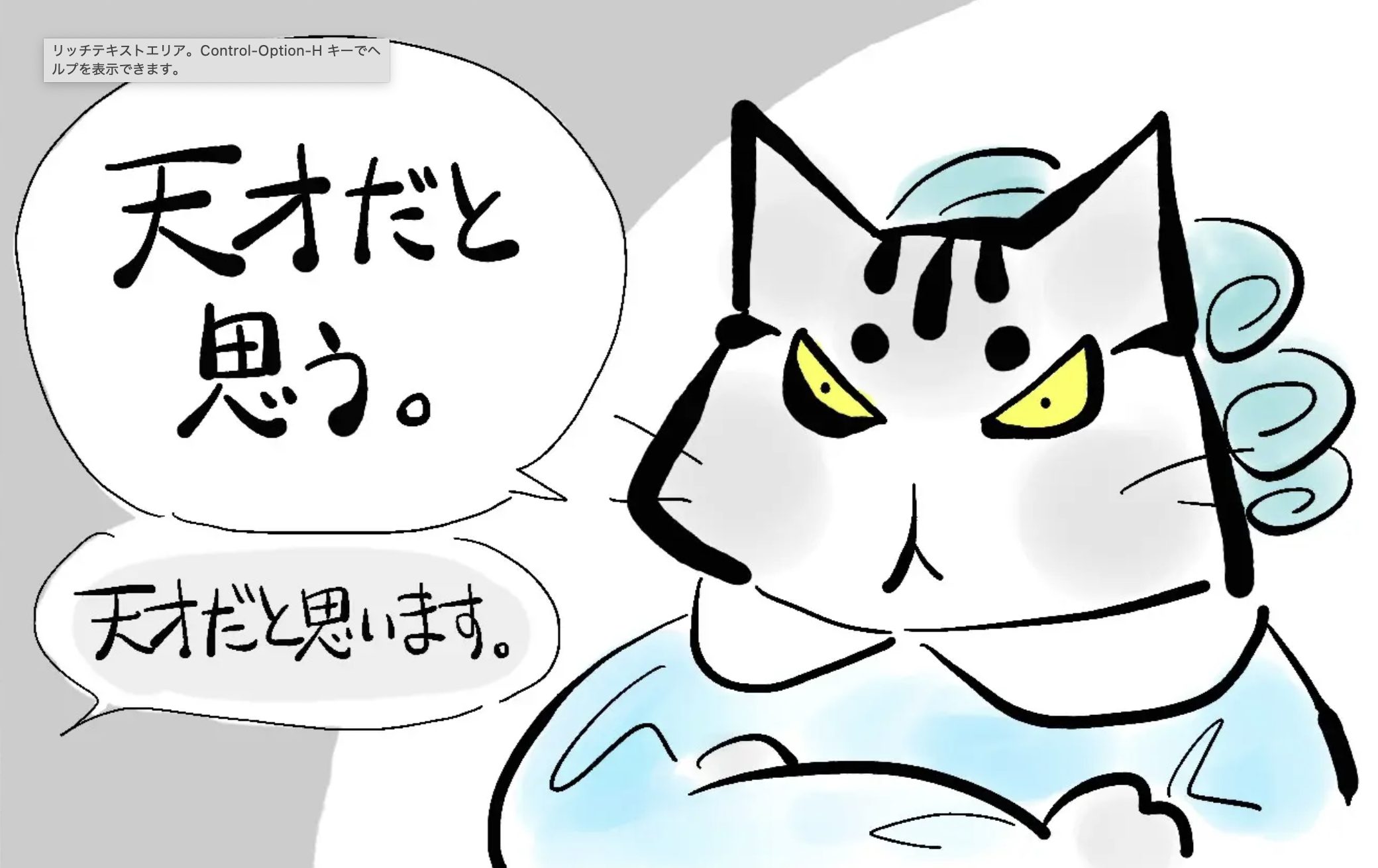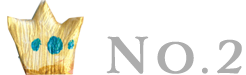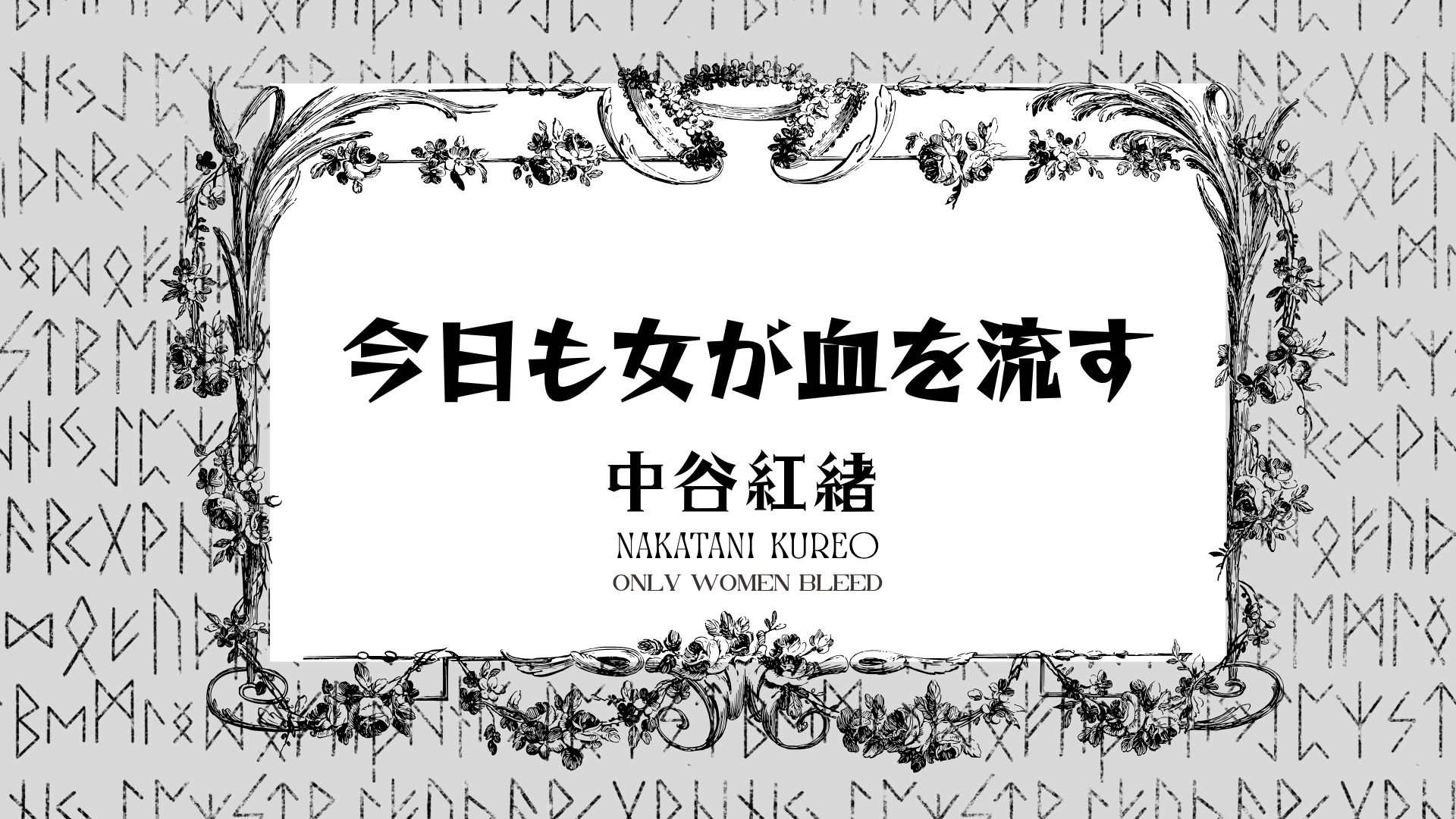
半年ほど「歩くだけでポイントが貯まる」アプリでポイ活をやっていた。始めてみて分かったのは、実際には歩くだけではポイントはほとんど貯まらず、けっこうな数の広告動画を見せられるということだ。広告動画の再生はランダムなのか、「若見え」を目指す美容アイテムのような明らかに女性をターゲットにした広告もあれば、ED治療薬のようなむしろ男性向けのものも流れる。男性向けのものにはアイキャッチとして女性が使われることも多い印象だ。
そんなことを観察しながら見ていて、広告にはっきりと性差が現れるアプリの1つに「筋トレ系」があることに気づいた。実際にダウンロードしていないので、中身の差については正確にはわからないが、どちらも広告で見る限りやっている運動はほぼ同じで、椅子に座ったまま脚を持ち上げるなどの運動器具のいらない筋トレがメインのようだ。しかし、女性向けアプリには「ズボラ」という単語が入っているのに対して、男性向けアプリには「ズボラ」の代わりに「マッスル」が入っているのだ。深読みし過ぎと笑われるかもしれないが、こういうところにこそ、社会的性差の刷込みは顔を出す。
まず、「ズボラ」という単語はどちらかといえば女性と結びつけられがちだ。それは、「女性は細かい作業が得意なものである」とか「女性は物事への対処が丁寧であるべき」という規範があるからだろう。女性がこの規範に反して大雑把に作業をしたり手間ひまをかけなかったりするとズボラ認定を受けることになる。女性自身もこの規範に縛られているため、丁寧に時間をかけてやっていると自信を持って言えない時に、自分自身やその行動をズボラと表現することが多い。また、そのように謙遜・自虐しておくことで「女性なのに〜」という非難を事前に封じる手段にもなっていそうだ。
女性に求められる規範は、時に生身の人間には到達不可能なものなので、女性は減点方式で自分自身を評価させられる機会が多い。だからこそ、「ズボラな私でも続いているコレ!」のような女性向け広告には訴求力があるのだろう。実際にはズボラな男性の方が圧倒的に多いと思うのだが、男性のズボラは豪胆とかワイルドとか「男性専用のポジティブな言葉」に置き換えられることもある。
そして、女性向けアプリに「マッスル」が入らないのは、女性に求められる外見に筋肉が入っていないからだろう。実際のところ、女性は男性と比較してムキムキにはなりにくいし、お腹周りに脂肪がつきやすい。私は、ランニングをしたり通勤で一駅分余分に歩いたりしているし、自宅でできる程度の筋トレもやっていた。しかし、そのような運動をしていないパートナー(男性)に全く勝てない。身体の大きさも違うので、彼は片手で私を制圧できる。それでも、「意外と力が強いよね」と言われたことがあり、それで考えた。もしかすると女性は自分の筋力や体力を把握しにくいのではないだろうか。
高校などの体育の授業内でやらされた体力測定(今は「新体力テスト」というものになっているらしい)を思い出してみよう。あの体力測定は女子の体力および筋力の測定に適していただろうか。分かりやすい具体例として、握力計の大きさを挙げたい。しっかり握った上で測定してもらえる人からしたら、私の「握力15」という数字は笑ってしまう筋力の無さだろう。しかし、辛うじて指先が引っかかる程度のものをどうやって「握る」ことができるのか?あの大きな握力計では、私の握力は測れていなかったとしか思えない。
当時は、このような身体のサイズの違いについてあまり考えていなかったのだが、女子の手のサイズ(平均)に合わせた握力計があれば、私ももう少しは自分の握力を正確に把握できたのではないかと思う。握力だけがすべてではないにしても、握力が15しかないのだから他の筋力もたかが知れていると思っていたし、どうせ自分には筋力がないのだという諦めのような気持ちは、私の体育の授業へのモチベーションを下げた。
握力が正しく測れていないというのは、それ単体で見れば、日常生活にこれといった影響はない。しかし、「自分には筋力がない」という認識は様々なレベルで日常生活だけでなく将来の進路の選択にも影響を与えかねない。こうした小さな積み重ねが女性の自信ややる気を削いでいること、それはその女性個人にとってのみならず、社会的にも損失になっているかもしれない。
体力測定の項目が男子生徒を基準に作られていて女子生徒にはサイズ等が合わないのではないか?という問題は、きっと今もあまり真剣に取り合ってはもらえていない。この国では、不利益を被るのが女性のみである場合、それは些細な問題として脇に置かれてしまうことが多い。女性の側も、それが当たり前になっていることから、あまり気にしないですませてしまいがちだ。
ところで、「筋肉は裏切らない」と言う人がいるが、筋肉はちょっと運動をサボるとあっという間に消えていくので、割と忠誠心を要求してくるものだと思っている。脂肪の方が「いつも傍にいるよ」と、頼んでもいないのに気づけばそこにいる。でも、それにだって身体的性差による違いはあるということは指摘し続けたい。

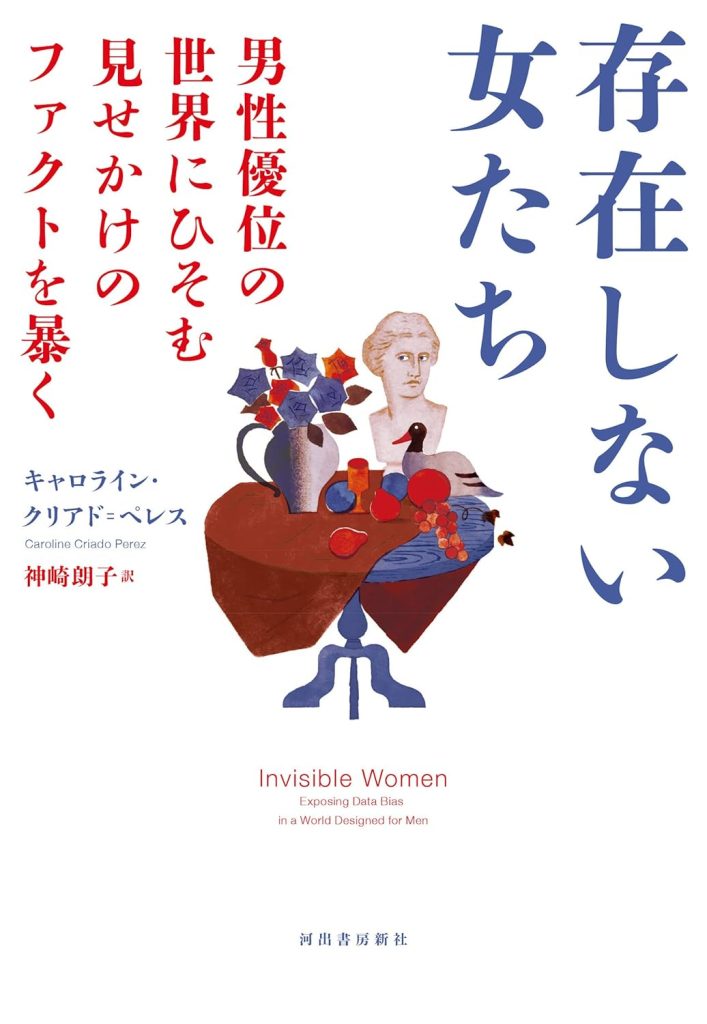
キャロライン・クリアド=ペレス著、神崎朗子訳
『存在しない女たち』
河出書房新社 2020年
「無いことにされている女性身体」に関する本として、真っ先に思い浮かぶのがこちら。久しぶりにパラパラとページを捲っているのだが、この本を読んで、何ひとつ新たな知見を得ることがない人はおそらく一人もいないだろう。女性でも「そんなところにまで性差が?!」と驚くと思う。ましてや男性が知っているはずがない、女性が「女性身体を持っているがゆえに不利益を被っている」ことがこれほどあることを。
もちろん、同性間の身体差も個別に見ていけばたくさんあるけれど、おおまかに平均値をとっても、男性と女性で大きな違いがあることは誰もが経験としてある程度は知っているはずだ。そして、現状、社会は「男性の平均値」に合わせて設計されている。それが、時には女性の安全を脅かし、命の危険にさえ繋がっているということがデータに基づいて書かれている良書だ。
エビデンスとかソースとかを求めることが大好きな男性たちこそが率先して読むべきだと思うのだが、彼らは自分たち男性用に設計された社会で女性だけが困っている問題にはなかなか向き合おうとしない。女性の方がケア労働などの無償労働にも時間や労力をとられているのに、女性自身が学んで発信しなければいけないという不均衡には腹が立つが、少なくともこういう本が翻訳・出版されるようになったのだから、社会は少しずつ前進していると思いたい。
そして、まずは知るところから始めようと呼びかけたい。世界のあらゆる場所で、女性たちがその身体ゆえにさらされる不利益は、認識されなければ解消されない。しかし、逆に言えば、問題を認識したならば、解決策を考えることはできるのだ。