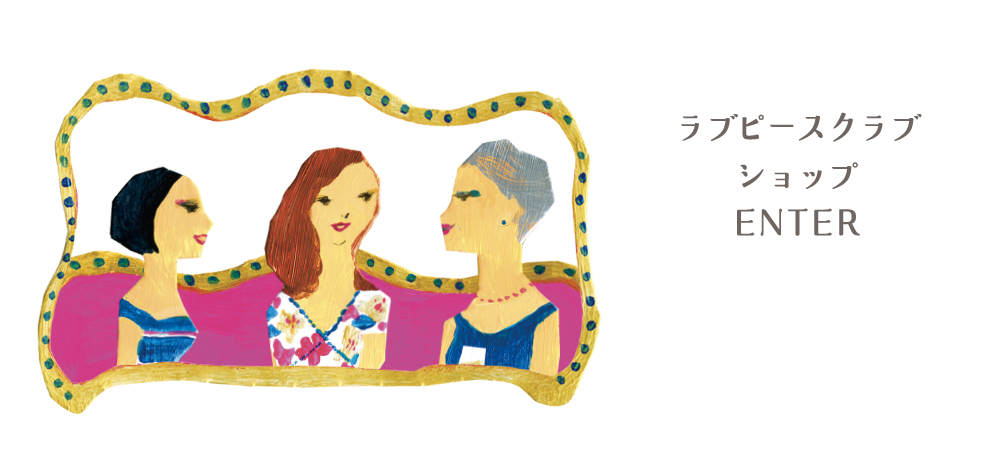今回から数回は、なぜ私がこのテーマでコラムを書いているかを、私のライフヒストリーを詳述することで見ていきたい。この大きなタイトル、「医療の暴力とジェンダー」は、私の幼児期から10代までの日々を象徴しているとさえ言える。
障がいを持って生まれると、生きるということに医療が無茶苦茶に関わってくる。多分これは戦後の、それも高度経済成長が進み、物質的な豊かさを求める中で始まったこと。先天的な、あるいは幼い時からの障害を持った子供達への眼差しには、「そのままの体ではダメ」と言う優生思想が貼り付いていた。
私が生まれたのは1956年、『厚生白書』には「もう戦後は終わった」という記述がかかれた年でもある。人々が幸福になるためには、経済活動こそが至上命題なのだと言わんばかりに医療もそれを踏襲した。私の骨の弱い体に、男性ホルモンが有効という“エビデンス”は全くなかったのにもかかわらず1日おきの注射が始められた。
つまり当時の医療は私の体を生体実験の実験材としてみなしたのである。3キロにも満たない体重だった私に、生後40日目くらいから、男性ホルモンの投与が始まり、その効果を見るためのゴム板無しでの、夥しいレントゲンの数々。その上、ギブスの身体拘束と、それを外す時の電動ノコギリの爆音は拷問にも等しかった。どう考えても私の命を助けたいというわけではなく、彼らの向学心の満足のために使われたのだ。
医療は命を助けてくれるものであるはずだという母の願いと期待を大きく裏切ってのそれは、圧倒的な暴力でしかなかった。毎回医者に連れて行くたび泣き叫ぶ私を見て、彼女の混乱と悲しみはどんなに深いものであったろう。ただ家が貧しかったために、高等尋常小学校卒だった彼女にとっては、その暴力に抗うすべは全くなかった。だから1年以上の通院の終わりにとった彼女の戦略は、妹を妊娠するということだった。少しづつ彼女のお腹は大きくなり、私をおぶりながら3歳の兄の手をひいてやってくる母の姿。さすがに医者達の良心も目覚めたのだろう。約2年続いたその注射は、「効果がないようだからやめましょう」という一言で終わったという。
私の兄は3歳年上だが、戦後4年半のシベリア抑留から帰ってきたばかりの父は、「長男の誕生」ということで、彼を溺愛していた。母も兄を可愛がっていたから、そんな中、生まれた私に対する兄の気持ちは実に複雑なものであったろう。骨の弱い私をケアするというよりは、まだまだ彼らの愛を必要としていた兄にとっては私は邪魔者でしかなかったのだ。
最初の骨折は、2歳の時。母は私が寝ているのを見て、兄に少しだけ私を見ているよう頼んで外に出た。ところが私はすぐ起きてしまい、1人遊びを夢中でしていた兄に、さらしのおぶい紐で縛られた。5歳の兄の縛り方ではハイハイを始めていた私を留めることは出来ず、私はそこを脱出し、風呂のたたきに落ちたのだ。突然大声で火がついたように泣き始めた私に、さすがの兄も気づき、近所の綺麗な小川で洗濯していた母を呼びにいった。その一連の光景は、母と兄から何度も聞かされたので、想像なのか記憶なのかが定かではないほどに、私の中に痛ましく、同時に洗濯機もない時代のどかな光景としてある。結果としてその後、兄に母が私のケアを期待するということは全くなくなった。
それに対して、私の手足かのように私のニーズを叶え続けてくれた妹。妹は生まれた時から私のそばで、私の骨折や手術、医療に介入され続ける苦しみを見続け、助けてくれた。
私は、骨折するたびに骨が曲がっていくというので、6歳の時に初めて手術をされた。曲がった骨は真っ直ぐにすべきであるという医療の強力な押し付けに誰も逆らえなかった。母が1ヶ月近く付き添い入院しての、大腿骨を2箇所切って真っ直ぐな棒を骨に通すという大手術だった。父は、あまりに仕事が忙しく私の付き添いは1週間に1、2回がやっとだった。
すでに学校に行き始めていた兄と、まだ幼稚園にも行っていない妹を見るために母の実家から祖母と叔母たちが交代で動員されたという。祖父は戦後の農地解放まで小作農と寺男をしながら、7人の子供達を育てた。母の双子の妹が24歳で亡くなった時から、突発性難聴となった。母の妹の死の原因は結核だけでなく抗生物質を手に入れられなかった貧乏故だろうと、私が生まれてからは一族総出で私を大事にしてくれていた。シベリア帰りということで教職の仕事をレッドバージで追いやられた父。祖父はその父を少しでも応援しようと、米や芋を背負って、しょっ中、訪ねてくれた。貧しいけれど、平和な家庭に育った母を「絶対に叩かない」という証文も父から取って、祖父母は母へのプロポーズを認めたという。だから父は母と私に対しては全く手をあげていない。
私は幼児期からこんなふうに家族の中での天国と、病院での地獄のような日々を味わい続けた。特に小学校5年で4、5回目の手術を学校に行きながら受けられるということで、病院付きの学校、療育園という施設に移った。そこでは医療との関係は更に酷くなり、障害を持つ人、特に子供の社会での位置に、これでもか、これでもかという程に気付かされていった。
家に居れば勉強しろと怒鳴る父に向かって「偉そうに大声を出すな!」と反撃したり、母に対しても体の痛みから言いたい放題を言い続けた私。それがここではホームシックで泣くだけでもレントゲン室に連れて行かれ、説教をされた。あまりの辛さにその施設からの脱出をすぐ考えたのだが、それが実現したのは13歳の時。2年半は隔離と排除に置かれ、その過酷さを身にしみるほど学んだ。それはその後の優生思想との戦いの強力な核となっている。