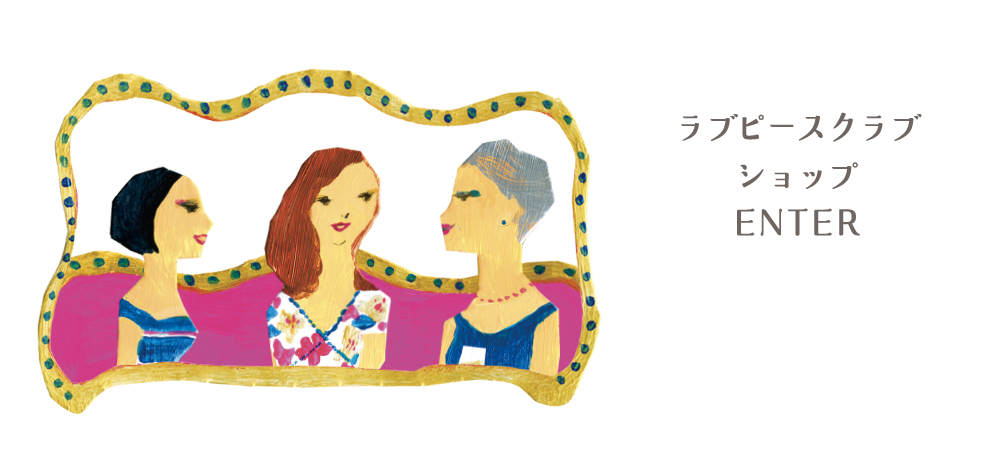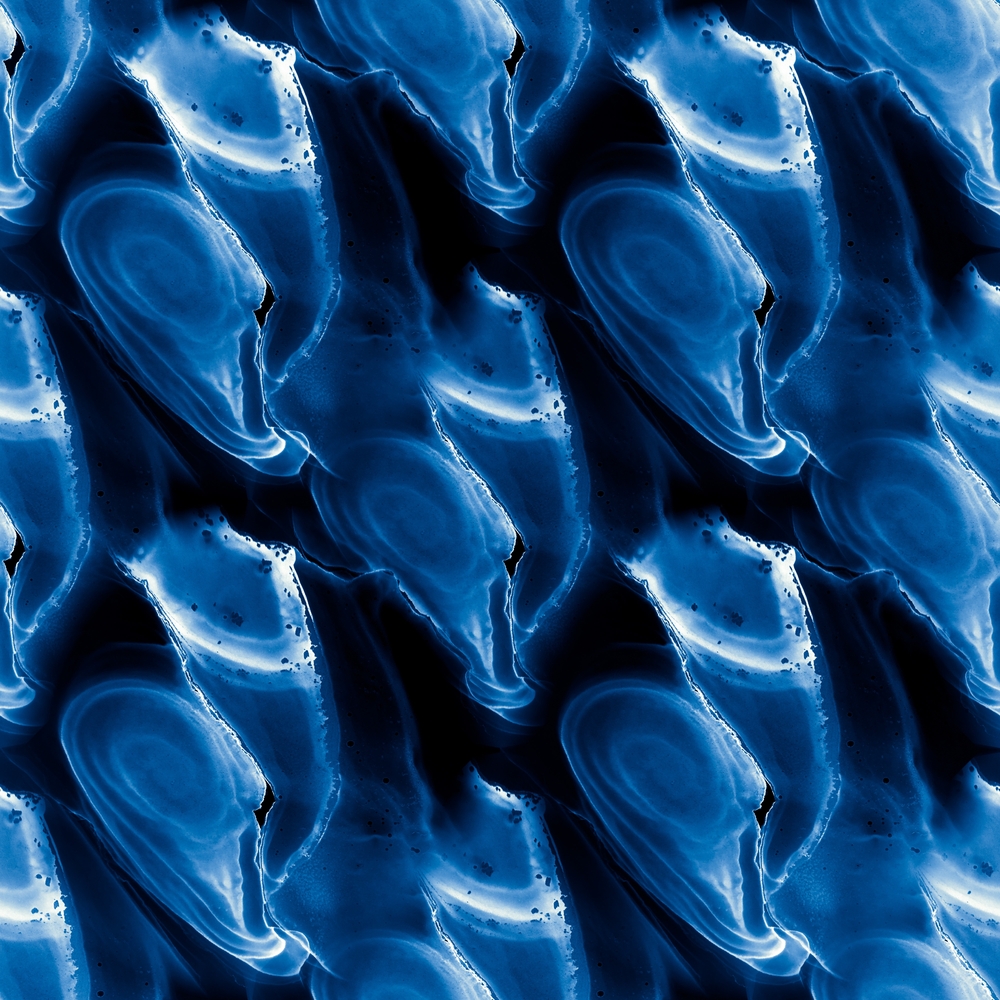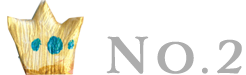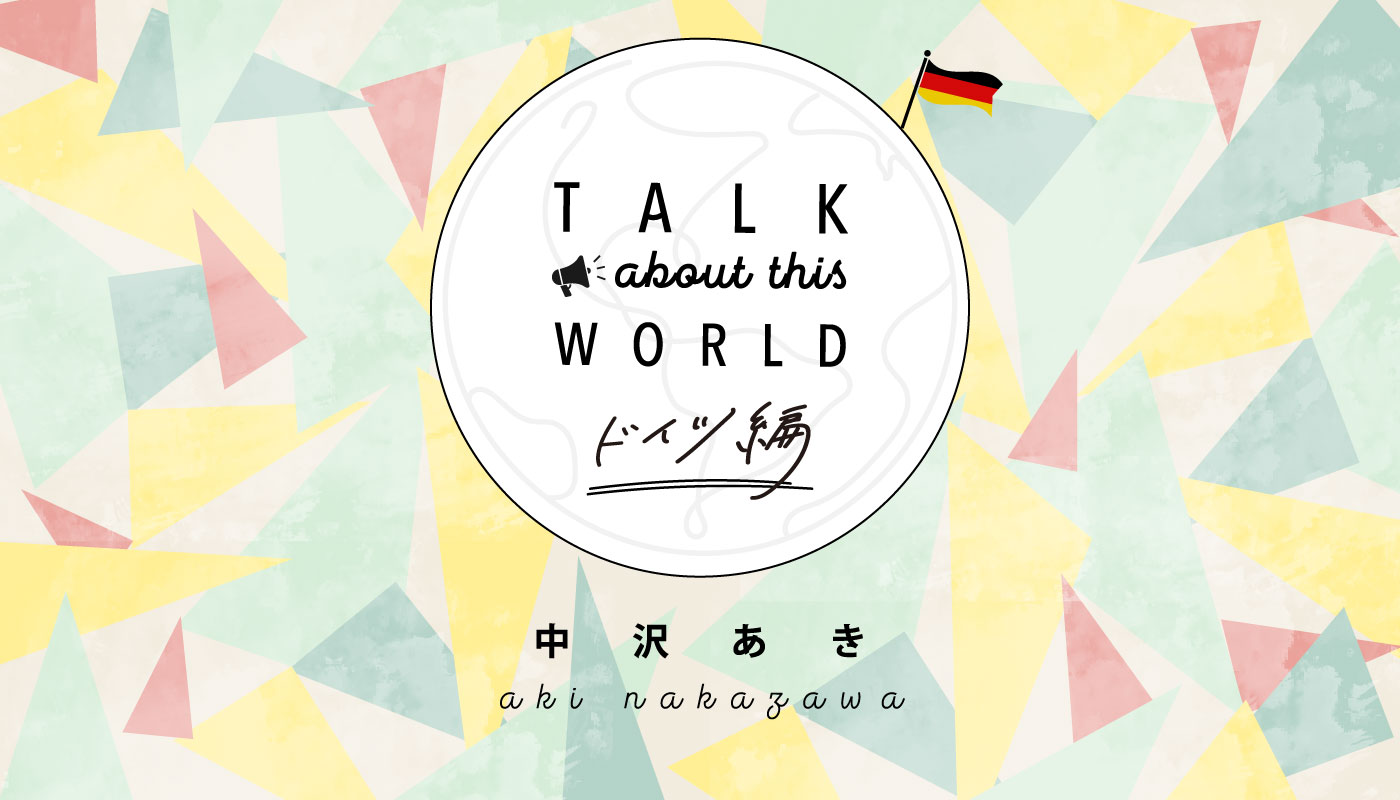
4月も半ばになり、今週からドイツの学校はイースターの春休みが始まった。学校は2週間休みだが、学校関係者以外は子どもに合わせて長期休暇を取る人はそれほど多くはない。イースターの祝日に合わせて何日か休みを取る以外は働く人も多いので、幼稚園や保育園は基本的に通常通りである。というか、普段は人手不足で半分閉鎖状態がたびたび起きる我が子の幼稚園ではこの時期、家族旅行に出かけていない子どもたちもいるのでその分手が回るのか、逆に閉鎖が起きないという安らかな日々である。なんだろね、これ……。
2ヶ月近く続いた保育士不足による半分閉鎖状態は、4月初めにずっと病欠していた副園長が戻ってきたところで一旦終わった。何の病気だったのか?なんてプライベートなことは訊けないが、久しぶりに顔を見た彼女に「先生が来てくれて嬉しいです」と伝えたら、いつもは無愛想な彼女が微笑みながら小さな声で「ありがとう」と返してきた。うん、復帰してくれたのはとっても嬉しいんだけどね。ちなみにこの副園長はイースターの休みに入ってまた欠勤が続いている。子どもの話では、風邪が治ったから米国に旅行に行ってるんだとか。なんだかなあ……。
いずれにせよ、こういう半閉鎖状態が続く事態は初めてではないわけで、今度こそ保護者たちは声をあげて市に直訴した結果、市の担当者も同席し、園長、副園長と保護者との話し合いの場が持たれることになった。その前日、先頭に立って声がけをやってくれているママ友と立ち話をしながらお互い「でも大きな期待はできないよね」と力なく苦笑い。我が子と彼女の上の子はもうすぐ小学校入学だが、下の子はあと2年在園するから、特に夫婦ともに教師である彼女にとってはまだまだ頭の痛い問題なのである。
その話し合いには私は参加できなかったのだが、園からの連絡事項やPTA会の報告をいつもすぐにこまめにやってくれるこのママ友から保護者グループチャットに何の報告もなかったところを見ると、ああ、これは成果なしだなと思った。数日後、相方がこのママ友から聞いた話では、話し合いの冒頭に市の担当者が「皆さんに素晴らしいお知らせがあります!」というから何かと思ったら、「子どもの欠席の連絡が当日朝よりも前にできるように、園の電話に留守番伝言機能を設置しました!」。そこかい!?ギャグかと思ったよ。
その後に保護者たちが閉鎖の状況がいかに大変かを訴えるも、人手不足が解消されないことには、という理由で具体的な解決案は結局出ないままだったらしい。まあ、予想通りだけど、空しくなるね。一年半前に私が別のママ友と市に直訴した時と変わってない。
しかし我が子はあと数ヶ月で卒園、この状況とはオサラバである。小学校からは義務教育だし、もう大丈夫かなって思ってます、と、先日とあるイベントで一緒になった在独日本人のママさんたちに言ったら、恐ろしい話が彼女たちの口から語られた。いわく、いまやどこの町でも小学校から高校に至るまで教師不足の事情で、先生がいないので自習が1ヶ月続く科目があったり、たびたび自宅学習もあるんだとか……。しかもドイツの学校の授業は基本的にお昼までで、昼食を食べた後はそのまま同じ校舎で学童保育に行かせる家庭がほとんどなのだが、この学童保育も万年人手不足。我が家もすでにこの学童保育を申し込んではいるが、この不安がまだ続くとは……。
日本も保育士や教員不足が深刻化していると聞くからどの国も同じ事情を抱えているんだなと思いつつも決定的に違うのは、「ドイツ人は頑張らない」ということだろうか。いや、ドイツ人も大方の人は真面目に自分の責任をこなしているのだが、自分に与えられた責任以上のことは基本的にしない。働く人の権利が守られているから、する必要はないししてはいけない、という考え。逆に言えば、個々の頑張りでなんとか社会が支えられてしまう日本は、そこに頼り切ってしまっている側の傲慢と引き受ける側の忍耐がもう限界で改めるべきなのだけど、日本人の私からするとドイツのこの状況にもう少しなんとかならないのか、というか「それはちょっと考えが甘いんではないかい?」と思うシーンにたびたび遭遇する。
しばらく前に離れた町へ出張に出た帰りのこと。業務1日目から風邪の症状が出たのをなんとかやり過ごし、業務を終えた3日目の夕方、帰りの超特急に乗り込んだ。向かいに座った同僚は私の風邪を貰い受けてぐったりと目を閉じて眠っている。こうなる状況を見越していたわけではないが、たまたま安いオファー価格が出ていて買った一等車の座席はゆったり広く、車内も静かでありがたい。そこへ乗り込んできた中年男性が通路を挟んで反対側のテーブル座席に座ってデイパックを下ろすと、携帯電話を取り出して話し始めた。ここは通話もOKの車両なのでそれはいいのだが、彼の会話がしっかり耳に入ってくる。どうやら職場に電話をかけているらしく、同僚だか部下だかの女性スタッフに話をしているようだ。いわく、重い荷物を肩にかけていたら痛めたのか、肩が張って痛みがひどいので明日は休むね。あ、それは僕がまた復帰してからね。云々。
あら、お気の毒……。でも、肩が張った痛みって肩凝りのことか?肩凝りで仕事を休むんかい!?
そのすぐ後、彼が先ほど乗務員に注文したビーフシチューが食堂車から運ばれてきて、いい食べっぷりでスプーンを動かしながら、彼はさらにもう一本、今度は家族に電話をかけている。最初は妻だかパートナーだかに、続いておそらく子どもに向かって話をしている。ここでも、肩の張った痛みがすごくてねえ、と言いながら彼は大きな皿を平らげ、皿を下げに来た乗務員にブラウニーとコーヒーを注文していた。
対する私たち、駅で買ってきたおにぎりと寿司のパックをほぼ無言で口に運び、薬も飲み込む。そして再び静かに休む私たちの反対側で、その男性は分厚い書類を机に置き、ラップトップをかちゃかちゃと熱心に叩いていた。どこかの会社のマネージャーかまたは大学の教授とかだろうか。
私たちはフリーランスだから、体調不良でもそう簡単には休めないんだよなあ、と、うらやましいというか呆れるというか。何かの問い合わせで何度電話をかけても「休みです」と何日も繋がらない相手がいる、そんな「ドイツあるある」の背景ってこんなかな、と失礼ながら思ってしまう。
先月、仕事で関わったイベントに遊びにきてくれた友人が連れていたそのまた友人がこんな話をしていた。その友人女性はジョージア出身で、本国で大学を出てからドイツに来て、今は近隣の高校で政治学を教えている先生だ。複数の学校で教えていて、彼女の待遇は正規ではなく非正規の雇用契約だそうだが、「どこの学校でも先生たちが『疲れた』と言うのよ」。なんだか聞いたことのある話だなと苦笑いする私に彼女は続けた。「私がジョージア出身の人の専門職免許の口頭試験の教官を行政から委託されて引き受けても、報酬は最低賃金並みの時給制。それでも私は社会のためと思って一生懸命にやっている。なのに学校の先生たちときたら、休みも賃金も保証されている立場で疲れた疲れたって、どんだけ怠け者なの!」
2月から3月にかけて何週間も続いたインフラ従事者たちのストライキは交渉の末に決着がついた。そのストライキで労働組合が主張していたのは週休3日制と賃金の引き上げで、週休3日とはならなかったが今年来年とかけて賃金は約3%まで引き上げられ、年間の休暇日数も増やされるという。その対策の財源は、5月初旬にスタートする予定の新連立政権が予算を出すことを発表したのを頼りにしているので、つまりは税金。周り回って皆のところにその負担がくる。ちなみにこの新政権内で現在、連立相手の党の間で合意に至っていない政策の一つも、国全体での最低賃金の引き上げである。現時点で下降線をたどっているドイツ経済事情において、賃金の引き上げはただでさえ他国に比べて高いドイツの人件費のさらなる高騰を招き、経済停滞の大きな一因になる。そこへもって休暇日数が増えるのはさらなる人手不足を招くだろうという厳しい事情だと思うのだが、この国でたびたび聞く考えはこうだ。「足りない分は外国人に来てもらえばいい」
若い世代を中心に働く意欲が低下している、というのはこの数年、各所で耳にした。各業界の現場で、また最近はメディアの報道でも耳にするようになった。その背景には「ワークライフバランス」を重視するべきだ、という考えがある。2、3年前、このテーマのラジオの討論番組に招かれた10代の女の子はこう言っていた。「私の親は銀行員で忙しく働くのを見ていたので、私は週休4日がいいんです」。さすがにこの発言には司会者も苦笑していたが、週4日勤務の間違いかと思ったよ、私は。週3日勤務で仕事して得られる報酬でちゃんと食べていけるのか、ということをそもそも考えていないような。旧東ドイツ出身で苦労して多国籍企業を築き上げたとある会社の社長は、今の若者は豊かな時代に育ったから甘ちゃんなんだよ、と呆れたように笑っていたっけ。
この女の子の発言は極論だとしても、ワークライフバランスという考え自体は悪いものではないはずだが、では社会を構成していく人間としてどれだけ働き、どれだけの報酬でどれだけの生活レベルを得るのか、というバランスも考えていかないと、それは結果的に自分自身の首を絞めていくことになる、ということに考えが至っていないのだろう。一人一人の権利を尊重することと、社会の成立が相反しないようにバランスを考えるべき、ということが、これまでの個人の権利を尊重する教育に欠けていたんじゃないだろうか。こんな権利の主張にたびたび出会うと、この社会の行き先に不安を覚えてしまう。それは若者たちの話だけではなく、電車で乗り合わせた男性しかり、友人の友人が話してくれた、または別の人たちからも聞いた教師や保育士の様子しかり、大人たちにおいても社会の倫理というものが危うくなってきているのかもしれない。そして不思議とその批判をするのは、私も含め、ドイツ以外の出身の外国人、またはある意味では「外国であった」旧東ドイツ出身の人たちが多い。だって、食べるために必死で稼がなければならない状況ではワークライフバランスなんて言ってられないもんね。


©︎ : Aki Nakazawa
桜の次はリンゴの花が咲き乱れています。さすがリンゴとジャガイモの国。
ちなみに新政権が予定している政策の一つは、両親手当と呼ばれる、子どもが生まれた後の母親や父親が育児休暇を取る間に出産前の給与の約6割を国が支給する制度のお金を減額するというもの。保育士不足で子どもを確実に預けることがままならない状況が全国にある中で、親に働けと急かすこの政府って……。政権が変わってもこの政治家たちには国民の現実がやっぱり見えてないんだなと感じます。だから選挙が終わったばかりなのに極右政党が支持率トップになったりするんだよね……。