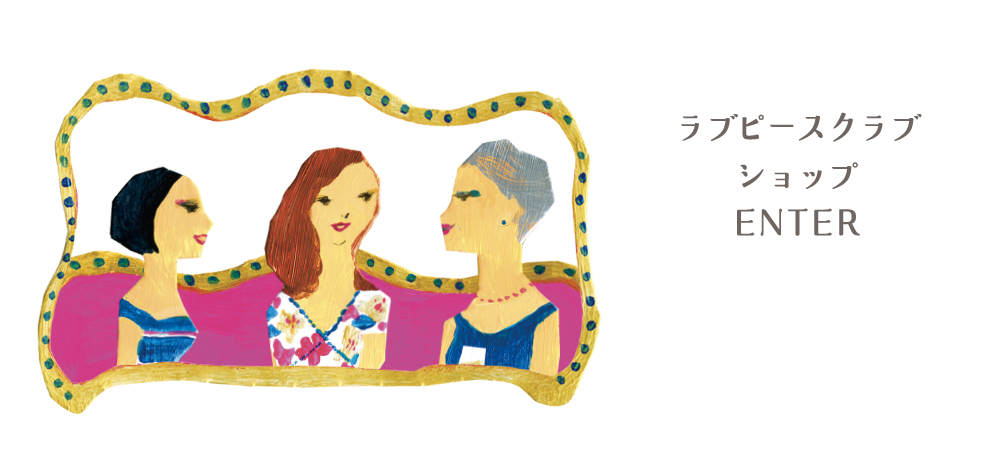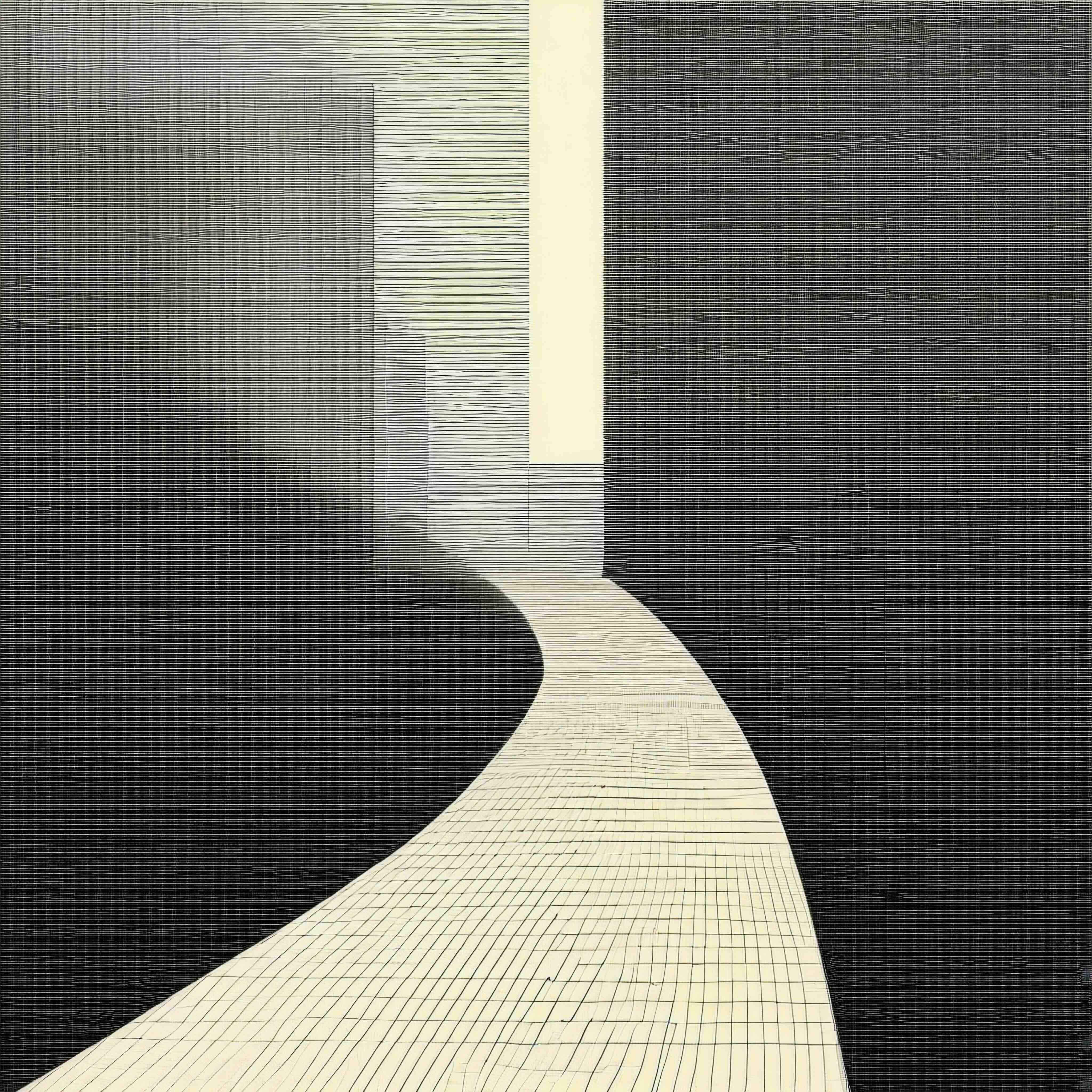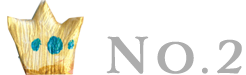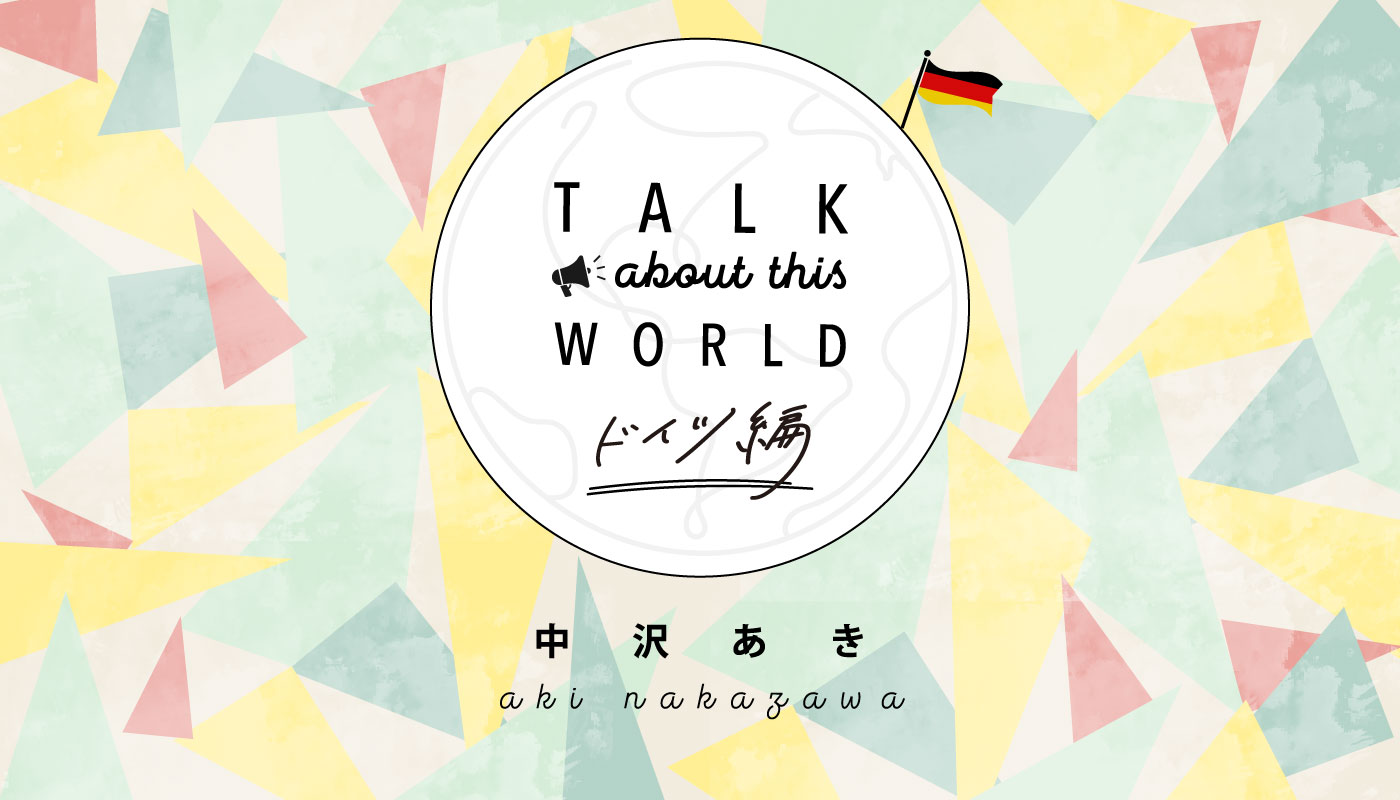
我が州は夏休みの真っ只中。ドイツでは州ごとに夏休みの時期がズレるが、期間は6週間、ただし保育施設はおおかた3週間で、働く親の事情を考えた仕組みにはなっている。ドイツ人によって、特に夏休みの旅行はお金をかけても行くもの、という習慣だが、それでもこの物価高と景気の悪さが影響してか、今年は旅行自体を控える家庭も増えたのだとニュースでたびたび聞いた。我が家はいつもの節約旅行だし、普段はレジャーを控えている分、私も子どもも海には行きたい。ということで今年も車で4時間弱の北フランスへ出かけた。訪れた先は昨年訪れたカレーから海岸線沿いにもう少し先に行ったところにある街、ブーローニュ=シュル=メールという小さな街。行ってから知ったのだが、フランスで最初にできた海水浴場のある街で、もともと海水浴の習慣は英国貴族の間で始まり、彼らが対岸の北フランスにもやってきて海水浴を始めたのがきっかけ、というトリビアもある、そしてローマ帝国時代の名残もある古い街だった。
北の大西洋は風が強く、気温もせいぜい20度前後なので私はとても泳ぐ気にはならなかったが、膝まで浸かれば水温はそこそこ高め、子どもは水に入って楽しげである。遠浅で静かな海はそこそこきれいだし、砂浜も混み合うこともなく、日々の魚市場での買い物や、ヨーロッパ最大の水槽がある水族館に行ったりと、のんびりと時間を過ごせたこの街は、かつては保養に来た客で賑わったのだろう目抜通りはシャッターが閉まったままの店もポツポツとあり、海辺に近い大きなホテルは廃業となったままなど、よくいえば鄙びた田舎の観光地、言い方を変えると寂れた街といった感じである。フランスも移民が多い国だけれども、それよりも気になったのはやや時代遅れのパンクやジャンキーがウロウロ、物乞いの人も目につき、もっと驚いたのは、その大通りでぱっと見、普通の市民といった白人の中年女性がお金もしくはバゲットを恵んでくれとせがんできたことだ。身なりもそれほど見すぼらしいわけでも不潔にも見えなかったので、住居はあるのだと思う。でも物乞いをしなければならないほどお金がないのか。フランスの社会事情にはうといけれど、移民や難民ではなく、一般の市民の一部が貧困に落ちている、つまりおそらく格差が激しくなっているのかなと、ドイツにも似通った状況を垣間見た気がした。
ドイツもこの数年、貧困が進んだなと肌で感じる。それも外国人という風貌ではなく、アル中やジャンキーなどの問題を抱えた人々が街の中心地にたむろする光景が増え、物乞いの数も増えた。旅行を諦める家庭の話にも表れるように、一般の家庭でも生活の厳しさは徐々に肌に迫ってくる感じ。ああ、貧しくなってきたなあと感じる場面が日々の生活の中で増えてきた感じがするのだ。
そんな重苦しい空気が少しずつ色濃くなるドイツとついつい比べてみてしまおうとする今回の北フランス滞在だったのだけど、比べるうちに、あれ?でもフランスってまだ余裕あるのかな?と思ったことがたびたびあった。
これまでフランスに来るたびに感じていた物価の高さ。カルフールなどのスーパーに行っても、各製品どれをとってもドイツより高いな、と思っていた。でも今回はなぜかそれほどその「高さ」を感じなかった。のは、たぶん、ドイツも物価が上がってきて、フランスの物価に追いついてきているからだろう。そんな中でさらに気づいて驚いたことがある。毎朝、近くのパン屋に買い物に行くと、どこのパン屋でもバゲットは1ユーロ10セントから20セントほど。クロワッサンやブリオッシュなどもだいたいそれくらいの値段である。現地の感覚でいえば、パン1個が120円くらい、という感じか。バゲットは軽くてすぐに食べ切ってしまうとはいえ、ドイツよりも安いと思う。聞けば、パンは主食なので政府が介入して値段を安定させているのだとか。ドイツにも食料品への消費税は通常の19%ではなくて7%に抑えるなどの政策はあるが、特定の食べ物の値段を安定させるとかはないと思う。それにしても比べて日本の米騒動ときたら……、やっぱり政治が悪いよね。
ドイツの物価高は今年に入ってまた再び厳しさを増していくように感じていて、この夏、アイスクリームの値段は1玉2ユーロを超えるのが普通になってきた。アイスクリームはドイツの夏の風物詩と言っても過言でないくらい、美味しい手作りアイスを手頃な値段で食べることができていたのに、1玉1ユーロを超える店が出てきたなと友人たちと嘆いていたのは8年くらい前。それがこの数年で一気に値上がってしまい、家族でアイスを気軽に食べに行ける値段で無くなってきてしまった。ベルリンでは貧困家庭の子どもたちでもアイスが食べられるようにそうした家庭には値段を下げる政策を、と謳う政治家までいるんだとか。
さてドイツよりも物価の高いフランスだから、ここも1玉2ユーロ以上は当たり前だろうなー、観光地値段でもっと高いかもと覚悟しながら、海辺の店で子どもにアイスを買ってやったら、1玉2ユーロが2玉になると3ユーロ、という素敵な値段になっていた。ヨーロッパの子どもはアイスを2玉以上食べるなんて当たり前であるので、我が子ももちろん2玉。しかも観光客相手の店でソフトクリームみたいな機械から絞り出されてくるアイスだったから、たいした味じゃないだろうと思いきや、バニラもレモンソルベも甘さ控えめの上品なお味でおいしくて驚いた。さすがグルメの国。
そう、グルメ大国、食文化が豊かな国だから、食材もまた豊かなフランスである。海辺の街なので魚市場があり、ここに並ぶ魚の新鮮かつ安いこと。ドイツではこんな価格とラインナップは期待できないから、ここぞとばかりに毎日魚を買って調理して食べた。カニもアナゴも牡蠣も最高の味。
そしていつもフランスに来るたびに思うが、この国は農業大国であるということ。田舎を走れば車道の両脇に小麦畑が広がり、それがパン屋のバゲットになる。そして街の広場で週末に開かれるマルシェに行くと、そこの青空市場に並ぶ野菜の量や新鮮さの見事なこと。売り手も買い手もイキイキして素晴らしい。私の街のドイツの農家も頑張っているし、いい野菜が買えるけど、マルクトの規模自体はこの10年でどんどん小さくなってしまった。それに比べてこの勢いときたら。もちろん畜産業も豊かで、地元のおじさんが一人で切り盛りして売っていたチーズは値段もドイツよりもグッと安く、とても美味しいチーズだったし、そのそばの農家のおばさんが売っていたカッテージチーズもカルフールのロゴが入った保存ビニール袋に入って売られている自家製パッケージだったが新鮮で美味しかった。フレッシュでエネルギッシュ、元気いっぱいで活気ある市場なのだった。
その市場の裏手にあるモダンなレストランも素敵だった。節約家庭ではあるが、だからこそ外食をするなら、お金を払う価値があるものにしたいと思うゆえ、フランスで行くレストランは楽しみで、せっかくだから自分では作ることのできない、インスピレーションをもらえるお店に行きたいとじっくり選ぶ。今回訪れたのは調理のシェフが一人とスーシェフ、そしてサービスの3人で切り盛りしている小さなレストランだったが、前菜とメインとデザートで36ユーロと、ドイツではこの値段でこのクオリティにはなかなか出会えない。しかも子ども向けのメニューは大人と同じメインの食事を少なめのポーションで出してくれるというのも気に入った。フライドポテトかケチャップかバターだけで和えたスパゲティを所望するドイツの子どもには無理だな。フランス語で「イラクサ」を意味する店名の通り、薄いグリーンでまとめられたインテリアは、センスある友人宅にお邪魔しているかのように心地よい。出された食事は季節のもの、地産地消を意識したものでとてもおいしくて、子どもも大人も大満足しながら店を出る時、調理場から若い男性がサッと顔を出して手を振ってくれた。その彼の隣でニコニコ笑っていた女性のスーシェフもまだ若い。観光客向けの大型レストランが並ぶ裏手で自分たちのコンセプトを持って経営しているのだろうこのお店はシンパシーを感じて、頑張って!と思う。フランス語で伝えられないのが残念だけど。
電車やバスといった交通公共機関は使わなかったのでその辺りのインフラ事情は比べようがないが、別のインフラに驚いた。観光地だからというのもあるのだろうが、街のあちこちに無料の公衆トイレがあるのである。ドイツにはこれがない。つい最近になってベルリンなどの大都市ではたまーに見かけるようになったが、とにかくすぐに気軽に入ることができるトイレがドイツにはない。だから公園の茂みなどでは子どもや時として大人も用を足していたりする。カフェなどで50セントから1ユーロ払えば利用させてくれるところもあるが、結構皆、平気でやる。先日などは友人いわく、大きな公園の芝生のど真ん中で、ふざけていたのかは知らないが男子中学生たちがおしっこをしていたと、顔をしかめていた。品位もここまで落ちると情けない……。
フランスの公衆トイレは場所と時によっては汚い時もあったが、それも我慢できる程度で、おそらく定期的に清掃されているなと感じた。我が街の観光場所の有料トイレなんて、料金機が故障していたので無料で入れてくれたものの、水が出なくてトイレが結局使えずに出てきたというオチまであるもの。
とはいえ、人間のトイレはしっかりしているのに、なぜ道は犬の糞だらけなのか、我が子と「うんこ注意報!」と指差しあいながら歩きつつ、不思議に思ったけれども……。
もう一つ、フランスは豊かだなと思った点は文化面。ドイツへの帰路の途中、レンスにあるルーブル美術館の別館に立ち寄った。「モードと歴史」という展覧会を目当てに行ったのだけど、開催時期を勘違いしていたのですでに展示は終了して見ることはできなかったが、常設展示は無料で見ることができた。日本の建築ユニットであるSAANAが設計したガラス張りの美術館は、同じくSAANAが設計した金沢の21世紀美術館を思い出させる素晴らしいもので、歴史の流れを表現したかのような設計や建物を囲む庭も独特で面白い。規模は小さいとはいえ、数々の収蔵品を見るのも、それから子ども向けのワークショップや野外のスポーツアクティビティなどの企画も全て参加無料だし、併設のカフェレストランはあるものの、持ち込んだものを食べ飲みできる休憩スペースもあって居心地がいい。昨今、文化や教育面への予算が各所で削られていく皺寄せをますます感じるドイツのことを振り返ってしまう。
そういえば話は前後するが、寂れた海辺の街のブーローニュ=シュル=メールを散策したら、あちらこちらから突如、ユニークな絵が視界に入ってきて驚いた。昨年カレーの街でもたびたび見かけたが、街の住居などの建物の壁に描かれたグラフィティ・アートである。どの絵もその建物や街に馴染みつつもシュールな魅力を放っていて楽しい。この街へのリスペクトを添えた情景や風刺の効いた絵などさまざまだが、どの絵もテクニックも表現も素晴らしい。とある絵の前で立ち止まって写真を撮っていたら、すぐそばの家から出てきた若い男性がフライヤーを手渡してくれた。どうやら街を上げてのグラフィティ・アートの企画が進んでいるらしい。気づけば彼がまた入っていった建物は、美術大学で、この学校の学生も参加しているのだろうと思った。寂れてはいるけれども、レストランといい、このグラフィティ・アートといい、この街を再び盛り上げていこうという若いエネルギーが生まれてきているのかもしれない。そんな気配を感じて、本当の社会事情は知らないけれども、少しうらやましいなと思った。



 ©︎ : Aki Nakazawa
©︎ : Aki Nakazawa
海辺の街のブーローニュ=シュル=メールの街中に現れるグラフィティ・アート。街の理解とサポートを得て描かれているこれらの絵は、この街によく馴染んでいます。こういうパブリックアートを受け入れる人々の心の余裕や、その若い世代を中心としたエネルギーを感じて、私もちょっと元気をもらえたかな。久しぶりにアートっていいね!と素直に思えたひとときでした。