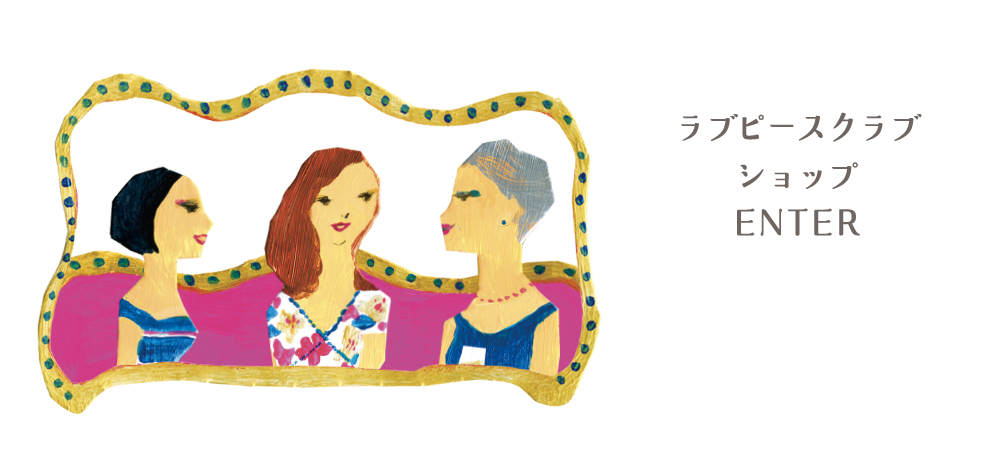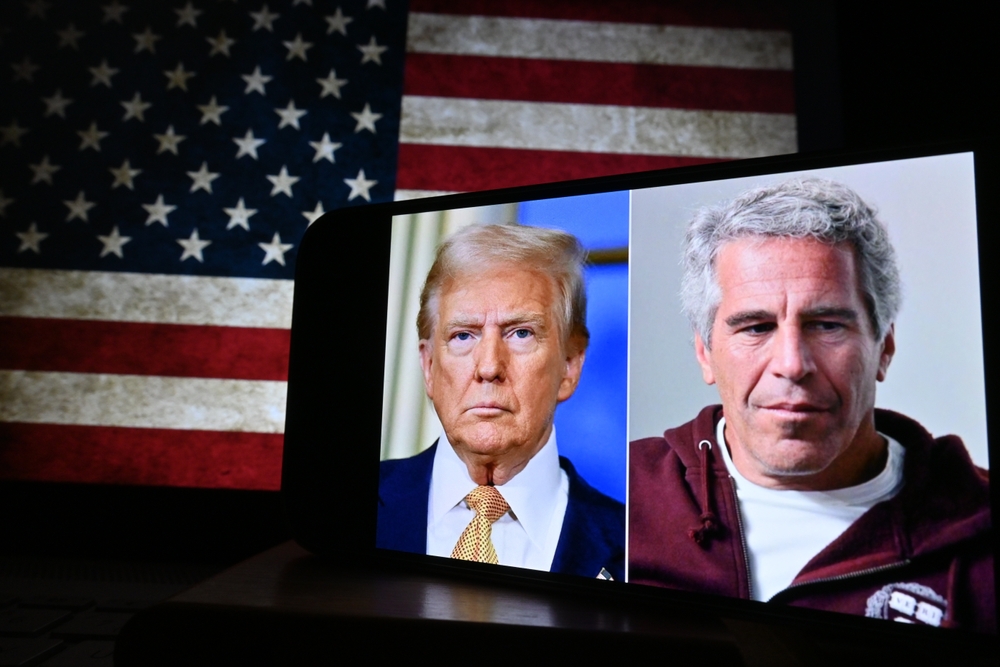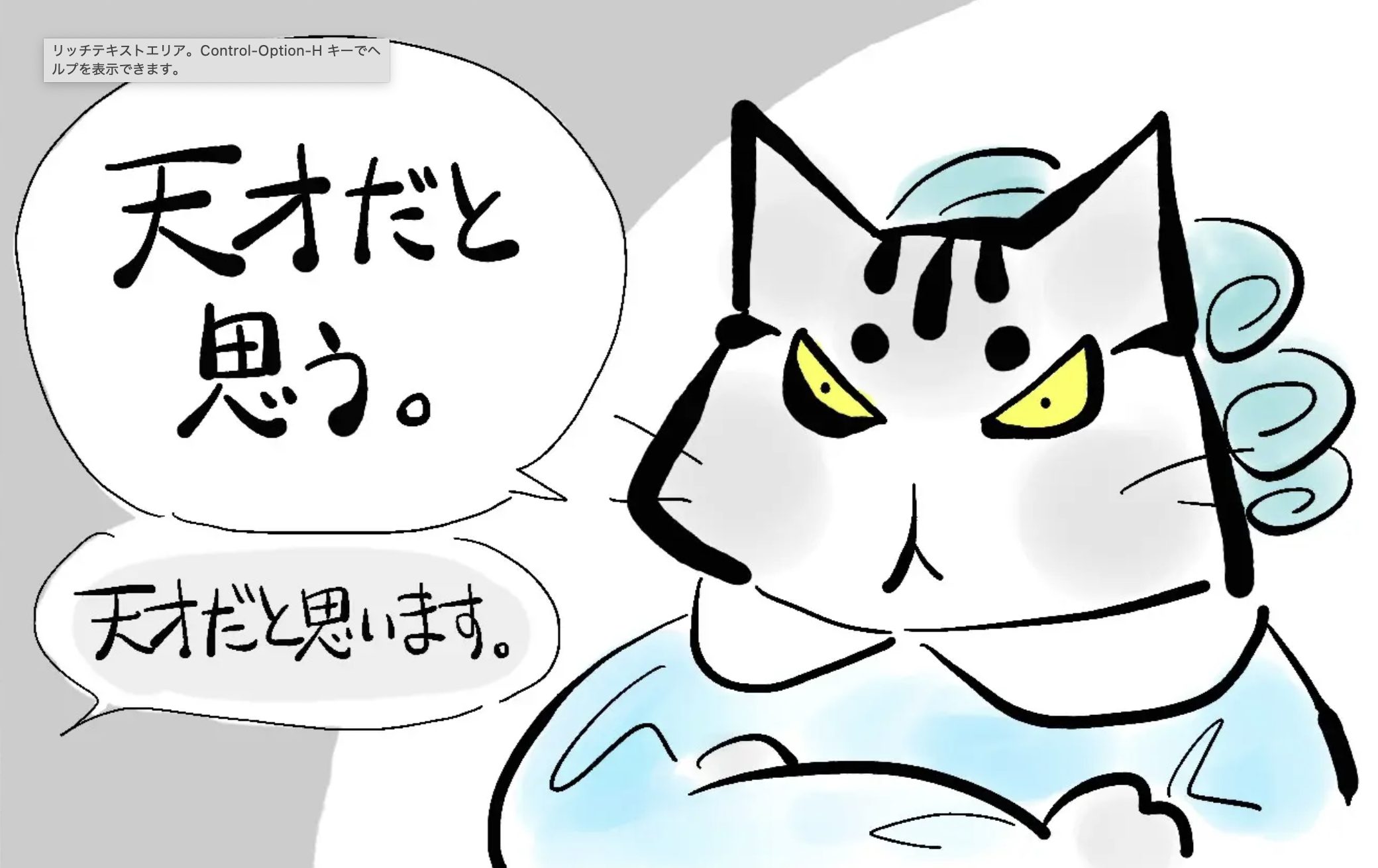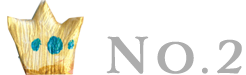今韓国ではYouTubeでのある出来事が、SNS上で大きな炎上を起こしています。俳優でありタレントのホン・ソクチョン(홍석천)氏が、男装した女性ゲストを招き、その本人に向かって「염병 떨고 있다(くそふざけている)」「씨발 짜증나는데(くっそうざいんだけど)」と罵声を浴びせたということでした。私はこの記事を目にしたとき、ただの芸能スキャンダルとは思えませんでした。むしろそこには、私たちが「ジェンダー」という名の幻想をどのように信じ込み、どのように他者をその枠から追い出しているのか――その構造が赤裸々に露出していたように思えたのです。
男装した芸人は女性たちの前で見栄を張る韓国の男たちの物真似をするコンセプトで活動し有名になりました。ホン氏は韓国社会において、同性愛を公にした最初期の芸能人として知られています。セクシャルマイノリティーとして、差別と闘いながら生きてきた人。その彼が、女性ゲストに対して露骨な蔑称を投げつけたという事実は、多くの人にとって裏切りのように映る――はずでした。しかし、SNSでのリアクションは大きく分かれました。
「本物のゲイにとっては本当の男でもないのに男の真似をしている男装役者が不快でも仕方ないよ」
「同じ男性として軽蔑的に感じたんじゃないの?」
そこで私は思わずため息をつきました。なぜなら、ホン氏の肩を持つ人々の多くは、これは女装する男性や、女言葉を使う男性、女性性の過剰なパロディとされるドラァグクイーンに対してはむしろ友好的だったからです。
ジェンダーとは生物学的な性別とは異なり、社会が“男らしさ”、“女らしさ”として個々に課してきた規範の集合体――私たちは生まれた瞬間に「男/女」と名づけられ、その分類に沿って期待され、評価され、罰せられて生きてきました。そして不思議なことに、その人工的な枠組みの中でこそ、人は「本物の男」「本物の女」を競い合うようになったのです。ですから、ゲイ男性が“女らしさ”を演じるときも、そこには既存の性役割のコピーがあり、同時にそれをパロディ化しようとする欲望があるのでしょう。ですが、その模倣がいつの間にか特権化してしまったのではないかと、今回の事件で私は思いました。
それが本人のアイデンティティであれ、単なる芸であれ、これまでテレビの中でどれほど多くの男性が女装をし、女性の真似をして笑いを取ってきたことか。このコラムを読んでいる皆さんも、その光景を何度も目にしてきたはずです。しかし、女性が“男らしさ”を演じることは、既存のジェンダー秩序をわずかにずらす行為である。そして、その行為を「不快だ」とか「やりすぎだ」と言い放つ瞬間、ジェンダーは再び“男を中心に据えた権力装置”として作動し始めるのです。つまり、「男の役割を模倣する権利」は、依然として男性側に独占されているということでしょう。
ホン氏はゲイ男性であれ、社会的には依然として「男性」という立場を持ち、その言葉には権威が宿る。だからこそ、彼が「女」を演じるときは“芸”として許容されるが、女性が「男」を演じた瞬間には“僭越”とみなされるのです。この非対称性こそが、フェミニズムが長年指摘してきた「ジェンダーの虚構性」であると私は思っています。“男らしさ”や“女らしさ”という言葉がいかに社会的な産物であるかを、私たちは改めて問わなければなりません。
“男らしさ”や“女らしさ”が本能や生物的差異ではなく、社会が作り上げた幻想である以上、そこに本物も偽物も存在しません。それでもなお、私たちは“演じ方”をめぐって優劣をつけ、侮蔑し、怒りを正当化してしまう。それは、ジェンダーという虚構に自らの居場所を賭けている証拠なのではありませんか。
この事件が不快なのは、暴言そのものよりも、その背後にあるジェンダー――いいえ、セックス(生まれ持った性別)という秩序の再生産にあります。「ゲイだから理解してあげよう」、「彼にも理由があるはずだ」という言葉は、一見、寛容に聞こえるかもしれません。しかし、それは同時に、「怒る権利は男性に属する」、「女性はその怒りの対象であり続ける」という前提を温存しているのです。ジェンダーの問題は、もはや“多数と少数”の対立ではありません。それは、生物学的な性別と社会の構造そのものに刻まれた、“権力の文法”との闘いなのです。
ジェンダーとは、もともと私たちが安心して生きるために作り出した「物語」だったのでしょう。けれど、その物語が誰かを排除し、誰かの表現を奪う瞬間、それはもはや幻想ではなく、暴力へと変わるのだと思うのです。男が女を演じることが芸であり、女が男を演じることが侮辱になる社会。それは、性器や染色体といった生物学的な違いに由来したのかもしれません。ですが、その歪みを正当化し、持続させているのは――私たち自身の言葉と笑い、そして沈黙の積み重ねなのです。