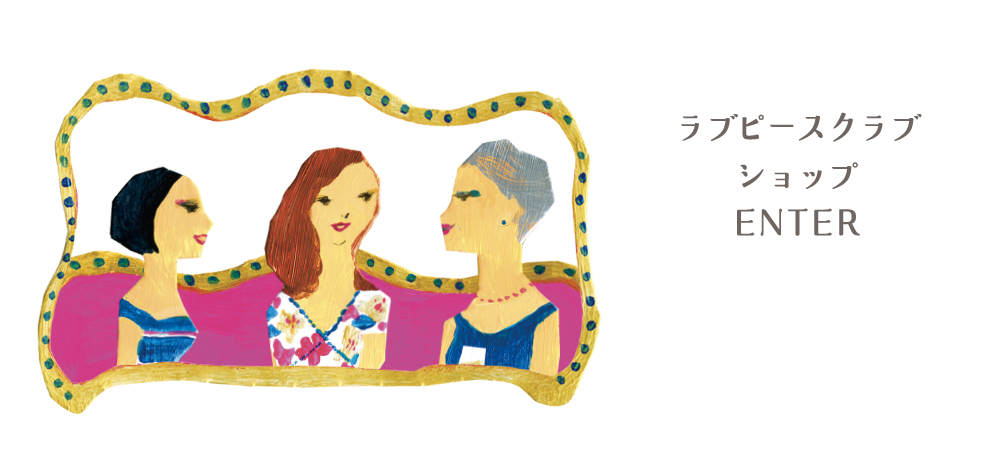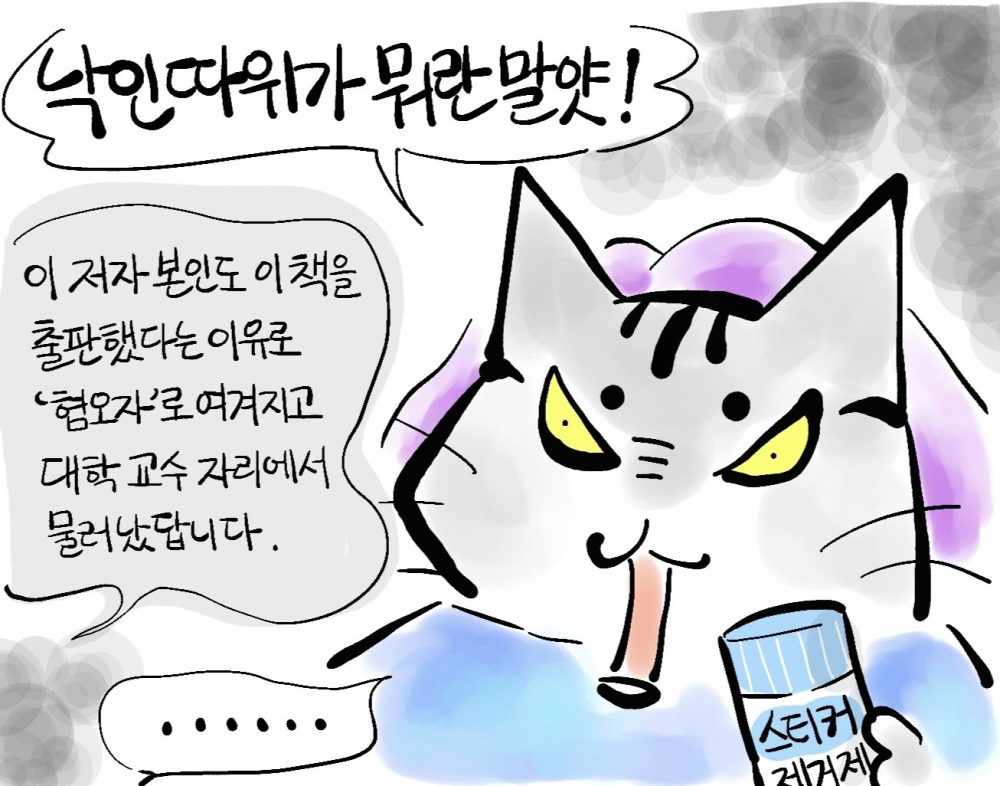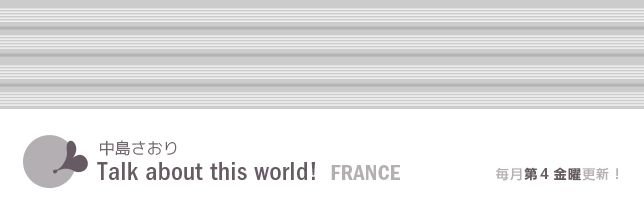
今年の夏、フランスは1900年以来、2003年についで第2番目の猛暑を記録した。リールやベジエで40度を超える日があり、パリでは30度を超える日が26日続いた。パリ市は公園を解放し、原発は4基止まった。
フランスでは今夏の猛暑は、地球温暖化と結びつけて考えられている。2017年の夏の北極からの氷山の分離、2016年の史上最高気温の記録、2017年8、9月の世界で40もの暴風雨の到来といった気候変動が、地球温暖化の進行に由来するというのだ。平均気温は1900年に較べて1,4度上がっている。
「地球温暖化は予想以上の速さで進んでいる。パリ協定は2100年までの気温上昇を2度に止めようとしているが、石油会社のシェルやBPの内部シナリオでは2050年に5度上昇すると予想されている。地球の温度が5度上がれば、地球の20%を覆っている凍土層が溶け出し、そこに閉じ込められている18億トンの炭素が、メタンガスとなって放出される。その温暖化作用はCO2の比ではなく大きいため、実際、5度以上気温が上昇したときに何が起こるのか良く分からない。2億5200万年前、凍土層からメタンガスが放出されて温暖化が急進したときは、生物の97 %が死滅した」
こういう認識に立って、地球温暖化を進めるような生活様式に抵抗し、対策を政治に求めるよう呼びかける本(Petit Manuel de Résistence contemporaine, Actes Sud)が6月の発売以来4ヶ月もベストセラーになっている。著者は2015年に環境問題に個人がどう取り組むかを描いたドキュメンタリー《Tommorrow パーマントラフを探して》を制作した環境運動家の映画監督シリル・ディオンで、この映画はフランスで異例の大ヒットを記録し、諸外国でも成功を収めた。
この9月初め、フランスでは国民的人気のあるニコラ・ユロ環境相が、「私が訴えていることがこの内閣では実現しない。全く何もできないのに、自分が内閣にいることで何かやっているかのような形になるのは潔しとしない」と突然、辞職する事件があった。ユロに呼応して芸能人が連名で政府に抗議声明を出し、支持を表明する人々が街頭デモを呼びかけた。このデモに、エコロジー団体が企画していた「気候のための行進」が合流する形で全国で11万5000人が繰り出した。
一方、夏を日本で過ごした私は、フランスの比ではない猛暑を体験し、豪雨も台風にも遭遇したのだが、地球温暖化と結びつけて語る言説をほとんど目にしなかった。9月の「気候のための人々の行進」は、世界各地で行われていて、ニューヨークでは30万人を集めたが、日本の都市では開催された様子もなかった。
どうしてなのだろう?
最近、「気候変動、政治の盲目」というタイトルで、日本のことを書いた記事が週刊誌『ル・ポワン』に出ていた。その大意は、今年の夏、日本は7月の豪雨、数回の台風で数百人の命を失ったけれども、こうした災害を地球温暖化と結びつける論はなかった。自民党総裁選では、どちらの候補者も地球温暖化とその結果がもたらす悲劇に触れなかった。災害予防については語られるのに、地球温暖化との戦いとはスッパリ切り離されている。野党も何も言わない。国民も災害に慣れてしまっているのか、地球温暖化とは結び付けないようだというものだった。
地震が地球温暖化と関係ないということもあるのかもしれないし、たしかに日本人は昔から天災に慣れているのではあるが… フランス人記者の持った違和感は、私の素朴な疑問とピッタリ重なったのだった。