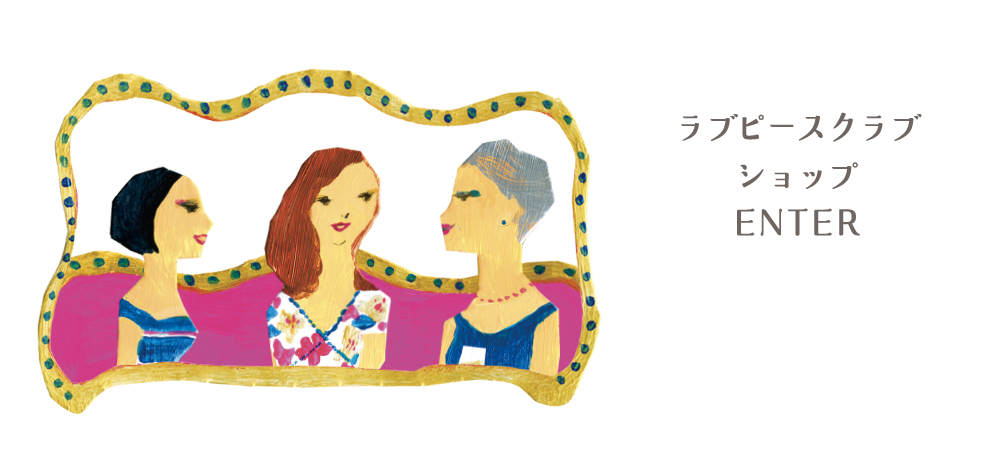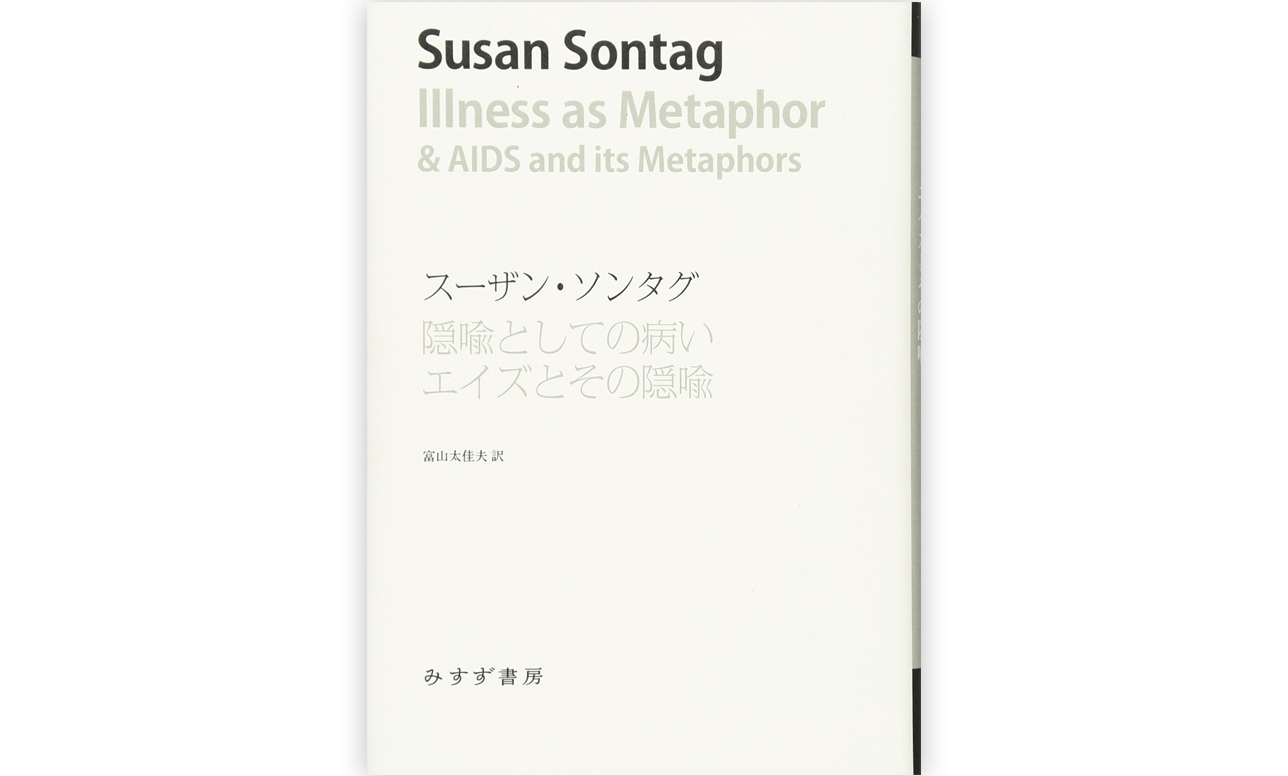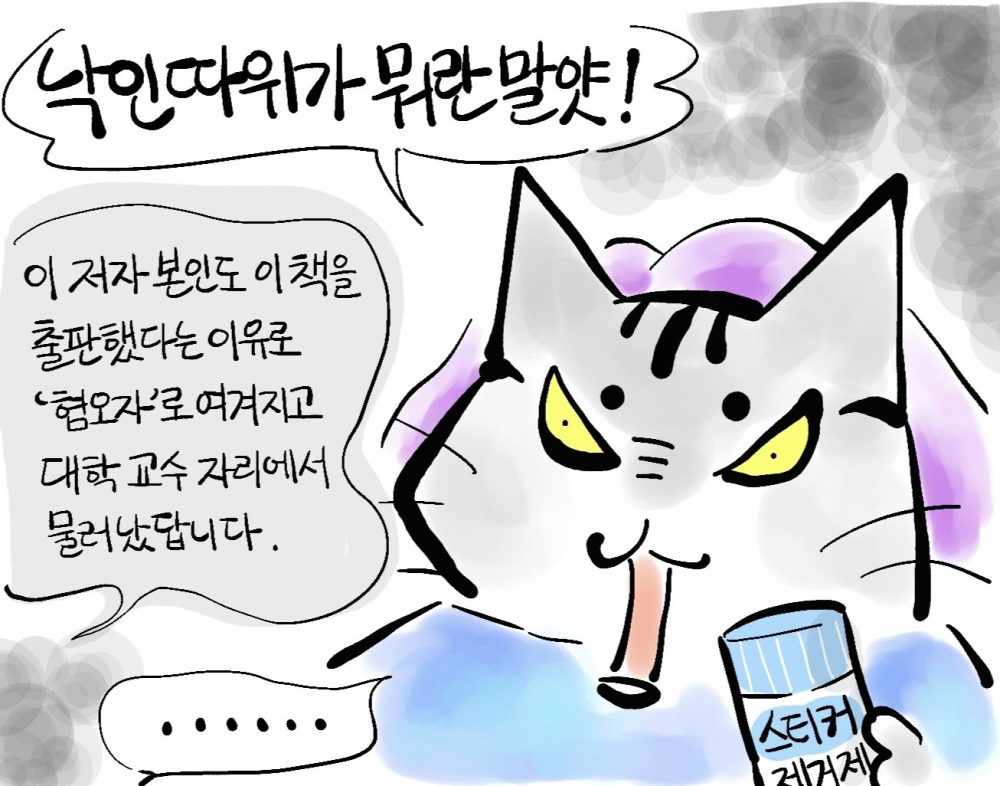『紅白』が放送されたのはもう1ヶ月も前のことなのに、いまだ話題に出すのは恐縮ですが、中島みゆきの『麦の唄』は、全出場歌手のベストパフォーマンスだった、と多くの人が感じたのではないかと思うの。声の張り、歌の最中のオーラ、歌が終わってすぐに朝ドラ『マッサン』の主演ふたりのところに歩み寄り、握手の手を差し出すまでのノーブルな立ち振る舞い。感激の涙を浮かべるふたりの横で、ドヤ顔のようにも見える自信満々の笑みを浮かべるエンディング……。どれをとってもモンスター級の仕上がりだったわ。
中島みゆきが80年代の中盤あたりから、発声の仕方にさまざまな試行錯誤をしていたことは、ファンの間ではけっこう有名なことらしいのね。あたくしは中島みゆきに関してはシングルとアルバム数枚ずつを所有しているだけのライトなユーザーなので、はっきりと指摘することはできないのだけれど、それでも、70年代の『わかれうた』と90年代の『浅い眠り』や『ファイト!』とでは、明らかに声が違うのは知っている。「声を体のどの部分から出すか」というテーマに取り組んでいたことが素人にもわかるわけ。その試行錯誤が、たとえば『地上の星』や今回の『麦の唄』において、「70年代とは大きく違うし、好き嫌いは別れるかもしれないけれど、迫力が増した」ボーカルとなって実ったのでは、と。もちろん、「そういった試行錯誤に耐えうるフィジカル(特にノド)を備えていた」という「ギフト」が中島みゆきに与えられていた幸運と、ドスの効いた声になってくるのと歩調を合わせるかのように「恋の恨み唄」から「人生そのものを描く唄」へと作風が変わっていったことも見逃せませんが。
前回のコラムで少し書きましたが、あたくしはそんな中島みゆきの姿を見ながら、もうひとりの偉大なるシンガーソングライターを思い出していました。松任谷由実、ユーミンです。
30代以上の人ならご存じでしょうが、80年代の松任谷由実は、そりゃもう飛ぶ鳥を落としてバリバリと喰ってしまうほどの勢いを持っていました。ちょうど中島みゆきが、セールス的にはひと段落ついた頃だったから、世間的にはよけいに「ユーミン独り勝ち」という空気感があったの。と言うか、中島みゆきとの比較そのものをされていなかった時期だったわね。
ユーミンは、過去2回、『紅白』に出ています。一度目はアジアの歌手たちとコラボレートした曲を上海からの中継で歌い、2回目は東日本大震災があった2011年、『春よ、来い』をNHKホールで歌ったと記憶しています。ファッションオタクとしては、1度目も2度目も見事すぎる友禅(たぶん森口華弘の作品)にまずは目を奪われたわ。ユーミンって実はオーセンティック好きよね。デビュー時は「異常なほど新しくて、オジサンたちにはチンプンカンプン」的な扱われ方をしたそうだけれど、本人的には「ワールドクラスでは、これがオーセンティックなポップスだもの」と思っていたのではないか、と、あの堂々たる着物姿からそんなことまで想像してしまったり。
で、歌のほうですが、『春よ、来い』は、緊張を差っ引いても、出なくなってしまった声と必死に格闘するユーミンの姿がありました。でも、それは想定済みだったのよ。と言うのも、あたくし(というか、多くのディープなユーミンファン)はそれにさかのぼること約2年、2010年の年明けに『MASTER TAPE』というBSの番組を見ていたから。
『MASTER TAPE』は、ユーミンのデビューアルバム『ひこうき雲』のマスターテープを37年ぶりに紐解いて、参加してディレクターやエンジニア、ミュージシャンたちと「音」そのものを批評(というか自画自賛)していく……という番組。まあ素晴らしい番組だったわけですよ。自画自賛、おおいにけっこう。あたくしは音楽はまったくの素人ですが、なんというか、息づまるような濃密さと適度な抜け感、気高さが信じられないレベルで曲の中に込められているのがわかるわけ。「音」そのもの、「メロディー」そのものが、いま聴いてもフレッシュ、というか古臭くなっていなかったんだもの。これこそ「オーセンティック」よね。
ただ、番組の中盤で、かつての録音スタジオに入り、ミュージシャンたちと即興で『ひこうき雲』を演ったとき、ユーミンの声があまりにも出ていないのに、あたくしは衝撃を受けたの。いやね、覚悟はしていたわけですよ。ユーミンがもともと「自分で歌うなんて考えていなかった。作曲家になりたかった」人であることは知っていたし、コンサート中のMCで「私はニューミュージック界(フォーク界、だったかしら)の浅田美代子」と自虐交じりに話す場面に客としていたこともあるし。だから、なんというか、衝撃とともに「ああ、ついにここまで出なくなったか……」という諦念を受け入れなくてはいけない、と思ったわけ。
だから、『紅白』での『春よ、来い』も、むしろ「身を削って出ない声と格闘する」様子にほとんど感動すら覚えていたくらい。このコラムで「松田聖子のタメ問題」を過去に2度ほど書いていますが、ユーミンはさすがに「音楽=リズム命」と知っているから、「声を出す」ことと「リズムを守る」ことの両方に必死で取り組んでいたことがわかったし。中島みゆきほど強いフィジカルを持って生まれてこなかったこと、そして、ほかのどのシンガーソングライターより「生涯コンサート数」が飛びぬけて多いがゆえに経年劣化が早く来たというボーカリストとしての悲しい宿命はあるものの、それでソングライターとしての能力にケチがつくわけでは一切ないものね。
ほかの出場歌手に囲まれて歌い終わったユーミンは、両手を合わせて、どこか頼りなさげで、なんか泣きそうに見えた。そうね、中島みゆきだったらこういう場面で絶対に個人的感情で泣きはしないだろうし、松田聖子だったらもっとわかりやすい泣き顔を作ったかもしれない。あのラストの表情は、ユーミンがイケイケドンドンのときには押し殺していた(あるいは「そういうのは作品世界の中だけに投入するの」という「意志の強さ」を保持していた)フラジャイルな部分が露わになった瞬間だったような気がするの。コンサートの、たぶんアンコールで『卒業写真』を歌うもののまったく声が出ず泣き出して、観客のほうがリードする歌声にかすれた声でついていく姿をYouTubeで見たことがあるんだけど、それも含めて、いまのユーミンなんだろうな、と。
前回のコラムで、美輪明宏や松田聖子や中島みゆきを「モンスター」と表現したのは、この3人にはいまさら何がどうなろうと揺るがない「強さ」が充分すぎるほど備わっているから、という部分もあるの。それはもしかしたら、「表現」をする上ではマイナスになってしまうかもしれない、と思うほどの強靭さ。それを結果として自ら剥ぎ取ってしまった後のユーミンが、今後どんな姿をさらしていくか。それを楽しみにしているあたくしは残酷なのかしら。でも、『ひこうき雲』や『ミスリム』や『悲しいほどお天気』あたりで見せた、フラジャイルむき出しでありながら完璧にオーセンティックだった世界観を、現在の肉体、そしてこれからの肉体でどのようにプレゼンテーションしていくか、それをどうしても見たいのよ……。
思えば80年代、飛ぶ鳥を落としてバリバリと喰ってしまうユーミンは、あえてそれを演じて、結果、自信満々でいたような部分もあるとあたくしは感じている。でも、それは決して悪いことじゃない。追い風があったのは確かだろうけれど、「言いたいことを言うオンナ」としての矜持をあたくしは確かに感じていたもの。
『松任谷由実のおしゃまします』というラジオ番組が、もっともユーミンがすっ飛ばしていた番組だったのですが、もうそれはそれは名言連発、「芸能史上、あんなにイケイケドンドンだった人間は後にも先にもいない」というアクセルの踏み方でした。
「パリにいたときは……って、パリに『行った』じゃなくて『いた』というあたりが、あたしもねえ(笑)、第二の故郷だし(笑)。フォーブルサントノーレを何往復したかな。ホント、買い物フリークでね」と語る中、アシスタントの女性放送作家に「ほんと、パリに指紋を残さない女。さわったものは何でも買っちゃうから」と突っ込まれ、「うまい!」と大喜びしたり。当時のアイドル本田美奈子が「アーティスト宣言」をしたのを受けて「あの子がアーティストなら、私は神様ですけどね」と断言したり。番組中に自分の曲『地中海の感傷』をかける際に、「じゃあ、次は私の曲ですね、『乳かゆいの不感症』です(笑)」と紹介したり。強気と放談のオンパレードで、当時ミドルティーンだったあたくしは度肝を抜かれつつも、そうねえ、間違いなく影響を受けたわね。
そうしたユーミン像は、いまは数年に1度くらいのサイクルでしか見られない。でも、その程度の頻度になったことは、別にもうどうでもいい。あれはあれで大好きだったけれど、いまの年齢と肉体を受け入れながら「創り出す」ことに向き合うユーミンに、どうしても興味をひかれてしまうから。ええ、どういう分野であれ、その年齢ごとに、さまざまなものと向き合い、格闘していくオンナが、あたくしは大好きなのです。