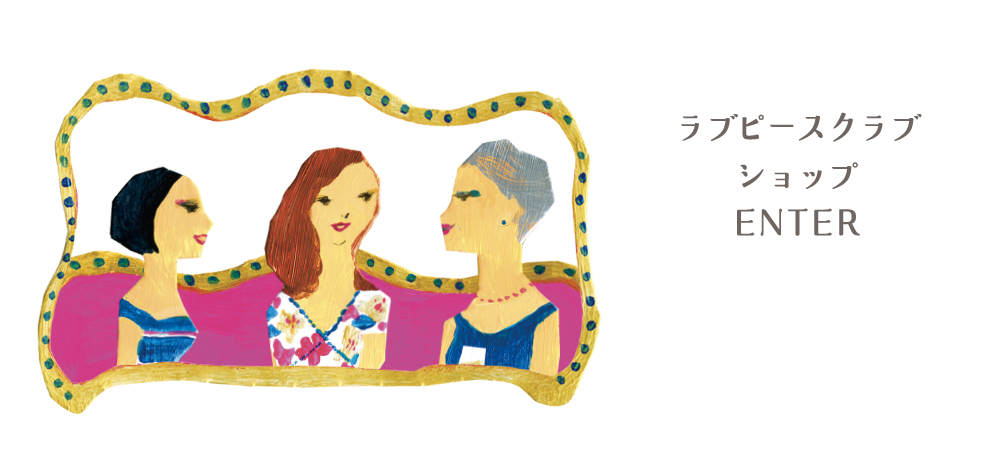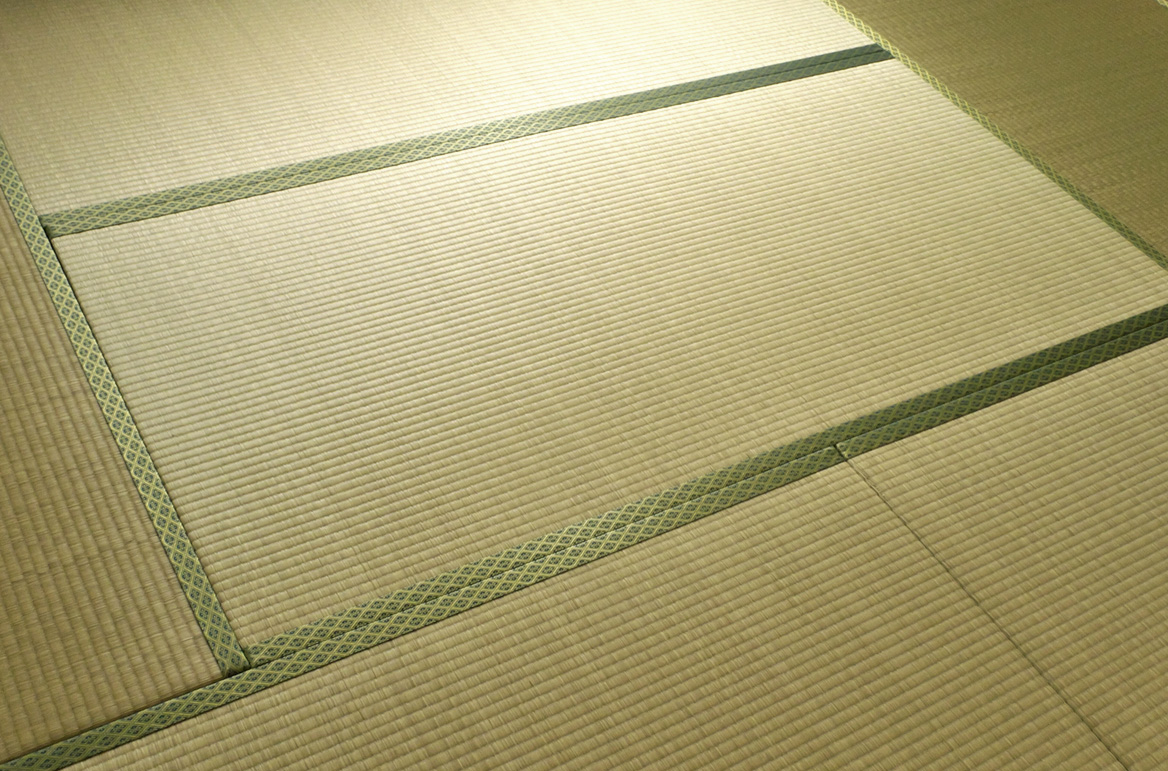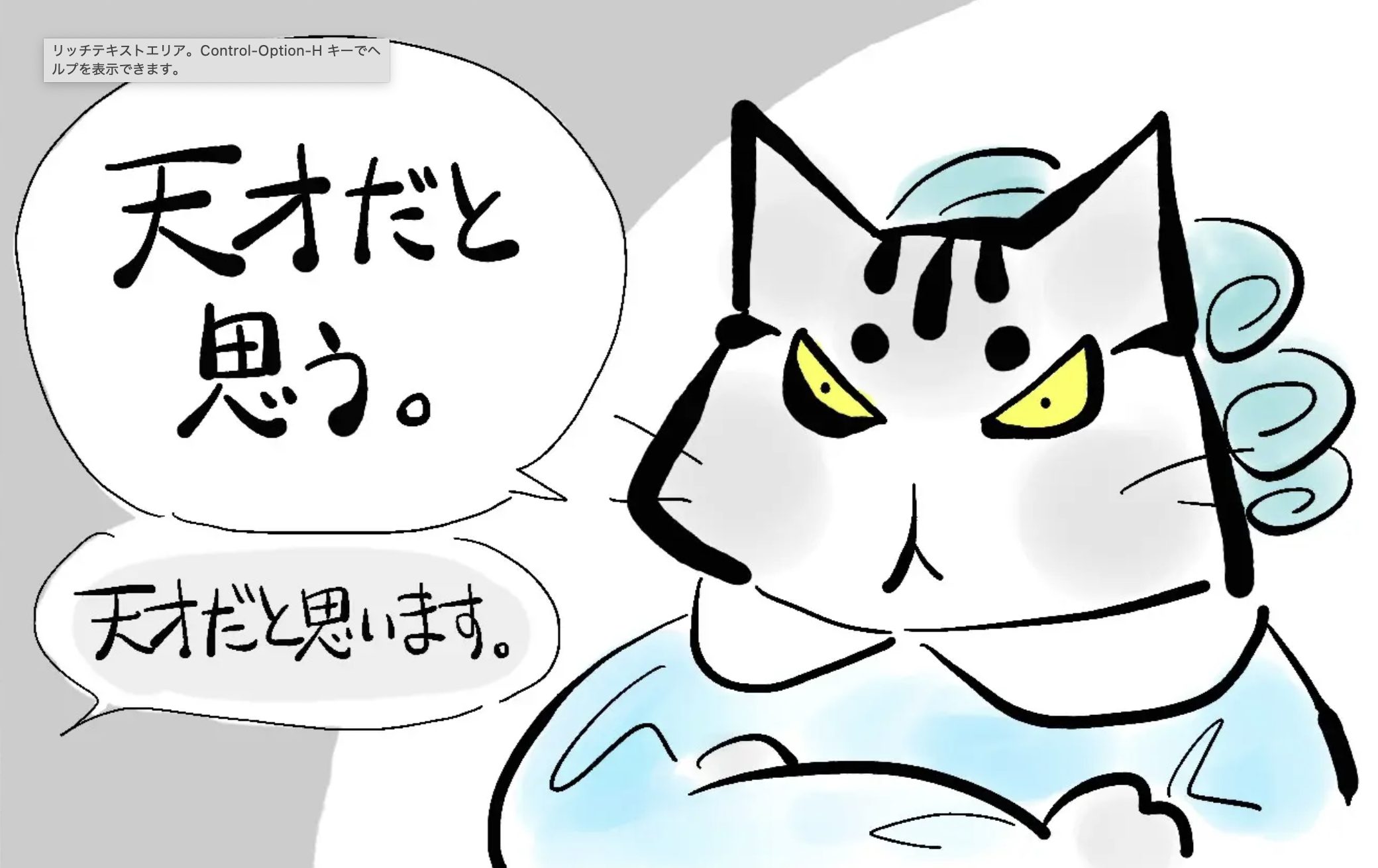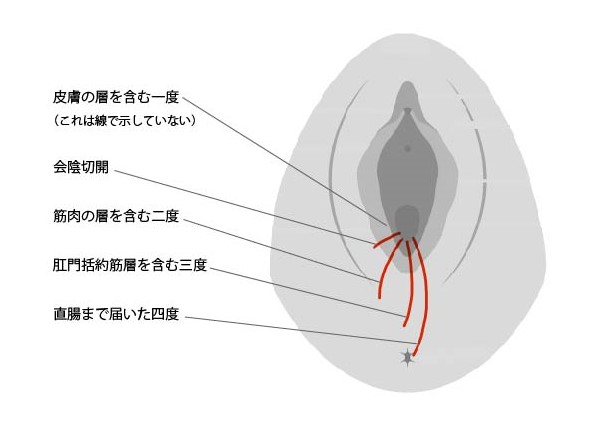お花ちゃんは、いつもの店の奥に陣取って、びっしりと薀蓄と解説で埋め尽くされたビールのリストを眺めていた。ちゃんと上座のソファー席を外して座っている。こういうところはちゃんとしているのだ。けれど、「お花ちゃん、待たせてごめんね」と背後から話しかけると、「ほんとにね」と、ビールのリストから顔も上げずにサラッと言い放った。その後に続く二言目は、彼が口を開く前から察しがついたので、目を上げたタイミングで私も言ってみた。
「「おせーぞデブ」」
お花ちゃんは、私のことを「デブ」「ブタ」「ババァ」の三単語を使い分けて呼ぶ。二人でいる時も、もっと大勢で遊んでいる時も、その三大二人称問題は何度となく話題に挙がっているので、お花ちゃんもその自覚がある。その、暴言とも言っていい呼び方の為に、その場に居合わせた私の女友達から、後々までお花ちゃんが糾弾されることも珍しくなかったが、友人は皆、私が何と呼ばれようとへいちゃらなことをよくわかっているので、その場では一瞬ぎょっとした後、軽くたしなめる程度である。
私は三分の一の確率を言い当てて「わーい、当たった」などと言いながらコートを脱ぎ、畳んでソファに腰かけた瞬間、「自覚があるなら痩せろブタ」と言われた。
趣味はランニングと筋トレで、私の知る限りこの8年弱、一度もお腹が出ていたことのないお花ちゃんに比べたら、健康体重の私は「ふくよか」のカテゴリに振り分けられて当然であるし、お花ちゃん一人にレッテル貼りをされたところで、今更どうということもない。
「お花ちゃん何か注文したの?」
「ビール。そのリストの、ゲストビールの上から二番目」
それももう飲み終わっており、空になっていたグラスに触れると、もう冷たくなかった。
「おいしかった? 私好きそう?」
「シラネ」
お花ちゃんはもう次のビールが決まっているらしく、ビールのリストをこちらに回してきた。ゲストビールの上から二つ目を見ると、アルコール度数は12%で、一般的なビールの倍以上。私はそれほど酒に強いわけではないので、これは駄目だわ、そもそも今日の私はお花ちゃんにプロポーズして、たぶんまたいつもの調子で断られて、でも、いつもと違うのは、そこから別れ話にもっていくんだから……と、ビールのリストを凝視したまま今晩のミッションを脳内で復唱していると、お花ちゃんは、何を勘違いしたのか「俺はそれ好きだけど、あんまり飲みやすくないから」と、何やら言い始めた。
「ブタちゃんは、いつものにしたら」
「あっうん」
ブタちゃん……。「デブ」「ブタ」「ババァ」の中で、「ブタ」だけにはごくまれに「ブタちゃん」に進化することがあり、出現する割合は限りなくゼロに近い、レア二人称である。
よりにもよって今晩。まぁ、聞き納めになるのだろうし、冥土の土産でも受け取ったかのような心持で、私はしばしお花ちゃんを呆然と眺めた。お花ちゃんは視線に気付くと即、「早く決めろババァ」と言い放った。
その後、何度も私は、自分のミッションを脳内で復唱した。
じわじわと酔いが回るにつれ、当初の計画を完遂するのは困難なような気がしていた。
四杯目を飲んでいる時、私たちはへヴィメタルのライブとハードコアのライブにおける客層とファッションの傾向について下らない議論をしていた。私のグラスにはまだ三分の一ほど飲みさしのビールが残っていたが、メタルバンドが売っているTシャツの多様性が実は限られたバリエーションの中に納まっているという、本当にどうでもいいようなことを一生懸命説明している時、ふいに喉を湿らせたくなりグラスに手をかけたものの、やはり水をもらおうと思って手を離した。
一杯が終わる前に、特徴的な味に飽きてしまったのだ。
すると、お花ちゃんがサッとそのグラスに手を伸ばして、一瞬でグラスを空にした。テーブルの上のもう一つのグラスにはまだビールが残っている。
わたしの静かな視線に気づいたのか、お花ちゃんはグラスをテーブルの隅に置きながら、「ん?」と言った。
「お花ちゃん、それ私のビール」
「別のが飲みたいんだろ」
私はビールのリストを受け取りながら「うん」と呟き、また、本日のミッションを反芻した。
現在の自分は、過去の自分の忠実な奴隷だ。だから、過去の自分の決定に従う。疑問は挟まない。熟慮の末にたどり着いた結論なのだから、疑っても意味がない。
お花ちゃんとのことに限らず、大体のことはそうやって決めてきた。
継続は力なり、と、大抵の道徳的な大人は言い、諦めずに努力し続けることが美徳とされる世間で私は、少なくともやみくもに現状を維持し続けることを美しいと思ったことは一度もない。継続とはただ、過去のある一点において己で決めた決定事項を遵守し続けている状態で、どこかでその状態が途切れたら、そこでまた改めて思考して道を定めればいい。
理性的に思考した自分は、その後の自分自身を奴隷にするだけの資格がある。
だから、結婚していない状態に耐えられなくなりつつある私は、お花ちゃんとどうしても結婚できないのなら、次に行くしかない。
私は最後に、ベルギービールのジェラートを注文した。お花ちゃんは同じタイミングで、ビールを注文した。
お花ちゃんは酒に弱い方ではなかったが、多少は酔っぱらっているようで、少し目が潤んでいた。大して明るくない店内で、目がキラキラして見えた。
豚の煮込みの大皿に残ったジャガイモを直接フォークで刺し、「今日もうまかったなー」と言ってちょっと笑う。お花ちゃんは時折、一人で頷くように首を振る癖があったが、ジャガイモをもぐもぐやりながら首を振ると、何だかよくわからない良い匂いが私のところまで漂ってきた。
「お花ちゃん、結婚しよう」
お花ちゃんはジャガイモをもぐもぐするのを止めず、口のジャガイモを飲み込むと笑顔で「やだ」と言った。
「いいじゃん、結婚しよう」
「やだよ」
「今日楽しかったでしょ?」
「うん」
「私も楽しかった」
「そりゃよかったな」
「私はお花ちゃんを幸せにできる」
「そうなの?」
「そうだよ! だから結婚しよう」
細部の差こそあれ、バージョン違いで何回も繰り返してしまった内容なので、お花ちゃんの対応が薄いのもしょうがない。
お花ちゃんの少し笑っているような眼差しが大皿のジャガイモから私に移り、またジャガイモに戻った。
「ジャガイモ、残り食べていいよ」
「お前も食えよ、デブ」
デザート食べちゃったんだけどな、と思いつつ、私もジャガイモを食べた。
「冷めても美味しいね」
「だよな」
どちらも声を荒げることもなく、激昂することも興奮することもなく、老人のような穏やかさで、我々は平然とジャガイモを食べていた。
「お花ちゃん私と結婚してくれないのか……」
「うん」
「じゃあ私、婚活しちゃうよ?」
「そうなの?」
「そうなの!」
婚活をする、という、ある意味脅し文句とも取れる内容だったが、私は、お花ちゃんの耳にあまり重苦しくなく届くよう努めた。プロポーズは何度もしているから、すらすらと口が動くが、それ以上のことはそうもいかない。
お花ちゃんは少し考えるような素振りをしたが、すぐ、「そうか、頑張れよ」と言って薄く笑った。
私は、自分の感情のことを考えるのを止めた。自分に備わっている(と信じ込んでいる)理性についてだけ考えることにした。
私にはお花ちゃんが必要だった。自分自身の為に彼が必要だった。だから、その為には何でもできると思った。仕事の鬼になって昇給昇進に励み、彼一人ぐらい養ってみせる、とも思った。全ては私自身の為だ。
けれど、私はやり方を間違えたらしい。
一人でも生きていける私と、一人でも生きていける誰かと、その二人で結婚してしまえばいいんだ、と私は思い、そう結論付けた自分を当面の主とすることに決めた。