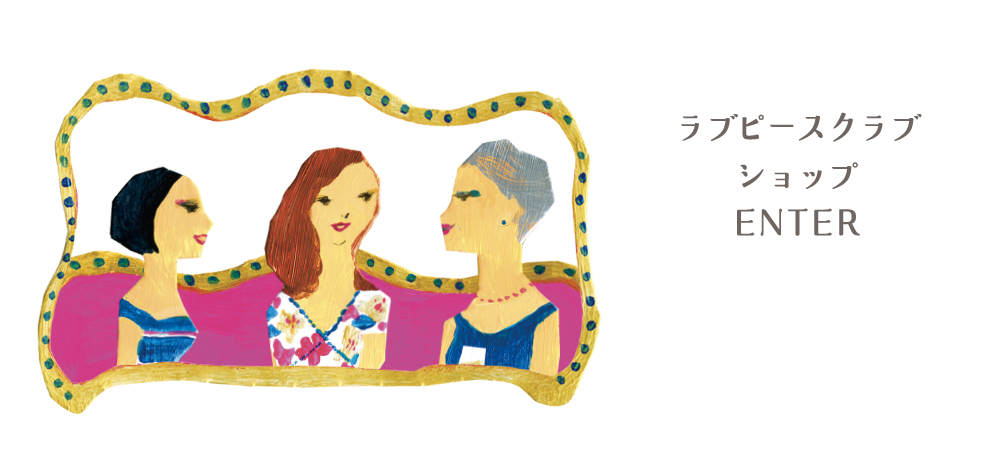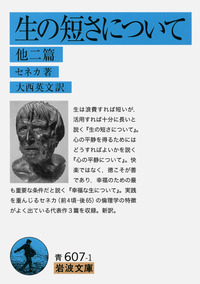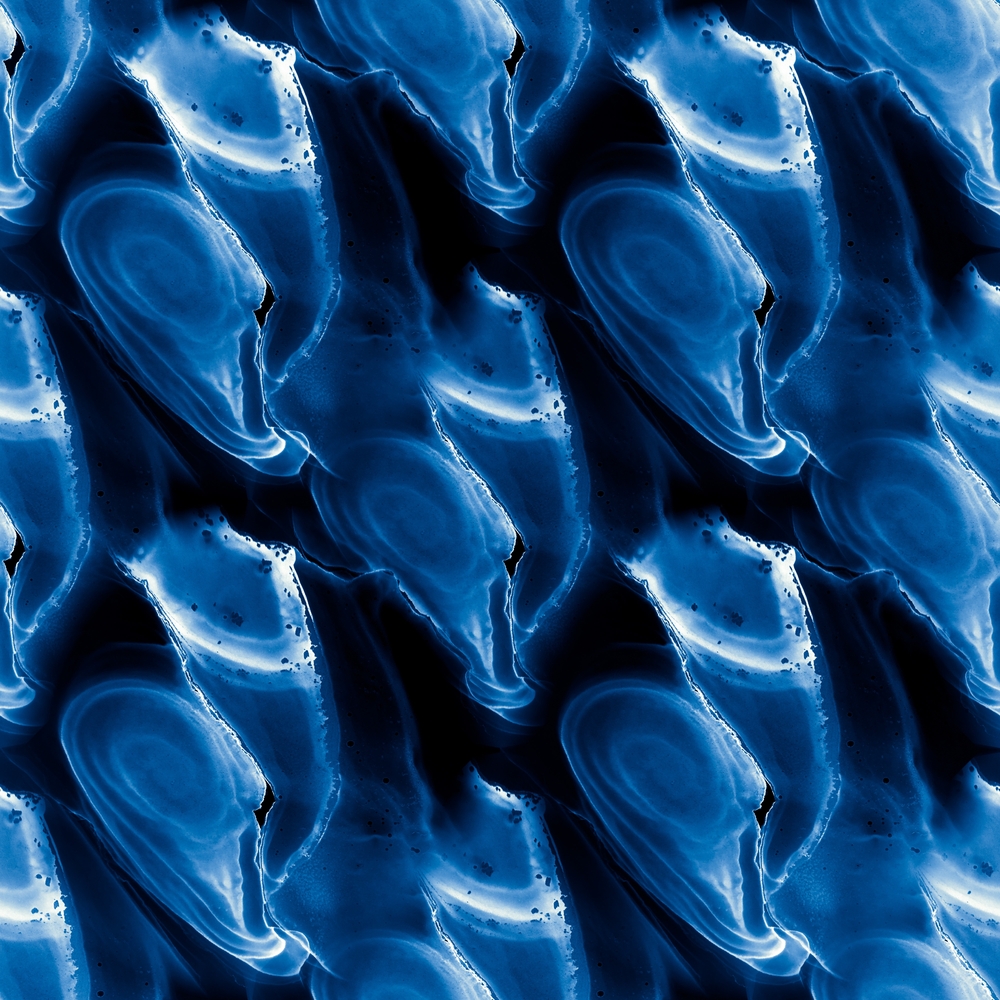モテ実践録(1)
2019.03.29

ご多分にもれず(?)海外ドラマを見始めると、すべてのシーズンを見てしまう。去年の春、私が30分×62話=約31時間を捧げたのはレナ・ダナムが主演・制作した「GIRLS」だった。
言わずと知れたこのドラマは、大学を出たけれど就職できずに無給インターンを続けている24歳の作家志望の女の子(ハンナ)を中心とした、女子4人の群像劇である。誰もが苦言を呈すハンナの性的関係も描かれることになるのだが、私の心を捉えたのは、時に画面に大写しになる一糸まとわぬハンナの、そのお腹まわりだった。というのも、ハンナ演じるダナムの(ざっくり言って)160cm、70kgという体型は、私が普段鏡の中で見慣れたものに限りなく近かったからだ。
私はときどき、自分じゃなくて歩いているのはお腹じゃないかと感じることがある。私という体の中にある軸が移動しているのではなく、膨らんだ、水っぽいかたまりが私の中心じゃないかと。そして私は小さな頃からずっと「学年で一番太った子」であったし、いろんな聞きたくもなかった言葉を向けられ、それゆえ(と言ってしまっては自己努力のなさを責められそうだけれども)ずっと自信がなかった。
一方で、画面の中のハンナは、迷走しながらも、毎回オリジナルな可愛い服を着て、自分の言葉を持って友人に対しても意見を堂々と述べ、キャリアを築き、そして何より男性にモテる。(う、羨ましいーー!)
その時から私の中で「ニューヨークに行けば激しくモテるんじゃないかしら」という希望が芽生えた。それと同時に(「ここがロドスだ、ここで跳べ!」)私も今ここから、モテを開始しよう、と心に決めたのである。
この連載は、31歳、年収300万円(額面)が、失われたモテを求めて(?)奮闘するモテ実践の記録である。
* * * * * * * * * * * * * *
さっそく今月の実践報告に移ろう。
<実践1>
以前、友達とやっているウェブマガジン「沼ZINE」にも書いたが、9年前、ドイツに留学した際に、日本から服を持っていくことができずに現地で服を買い直した。それ以前は、服は「着られればよい」というように、ほとんど興味がなく、そもそも上記のような事情から「入れば、よし!」というような気持ちで、試着室に入る前は脈拍も上がり汗ばんでいたのが、ドイツではサイズの問題がなかったので、友人とわいわいと、現地の感覚に寄り添った服を買いあさり、「ファッション」の楽しさに目覚めた。
ファッションと言ってしまうと、私にその言葉がふさわしいのかどうか、気負いすぎていないか等々、「くすぐったい」気持ちがするけれども、個々の服や小物を選ぶことで、総体としての、自分がまとうオーラのようなものがガラリと変わる。「フランス人は服を10着しか持たない」と言うけれど(フランス通には異論があるらしいけれど)、遅咲きの私にとって一番幸福なのは、朝クローゼットを開け、「今日はどの服を着ようかな、どのアクセサリーと合わせようかな」と考える瞬間である。
先日、私のファッションは新たなフェーズに到達した。というのも、私はその日たまたま映画を観るために銀座にいて、開始時間までにはまだ数十分あり、財布には貰い物の商品券があったのだ。そして私は少し前から「口紅が欲しいな」と漠然と思っていた。それも、普段着ている赤のコートに似合うような、真っ赤な口紅が欲しい。全くブランドを知らない私にとっても、なんとなく、赤の口紅と言えば〈シャネル〉と頭に浮かぶ。[私はお金がないしシャネルなんてめっそうもない]という頭の中の声を振り払い、デパートの地下階へ向かい、ブースまで行くも、店員さんに声を掛けられず回れ右をしてフロアを一周。そして、今度は勇気を出して「赤の口紅ください、これ!」と一つを指差す。
シャネルの口紅には、番号と名前がついているものらしい。赤系統にはなぜか「アーサー」、「ディミトリ」、「ガブリエル」と男性の名前がついている中で、私が指したのは「カルメン」という種類だった。店員さんはとても優しく、試してみませんか、と丁寧にその赤色を唇に乗せてくれた。
うん、悪くない。
何よりも、真っ赤な唇からは、私はもっと自信を持って言葉を出すことができそうだ。それに、鏡に大写しになった口元は、口角がいつもよりずっと上がっている。何よりぼやぼやとしたイメージの「シャネル」が自分のものになった、しかもその色が、自分にも似合うものであるということに、足取りも軽く、背筋すら伸びる思いがしたのである。
<実践2>
そうして真っ赤な口紅をつけてもらって、観た映画が「マイ・ブックショップ」である。
この系統の、女性が新たな生き方を見出す映画、は、日本の配給会社の狙いでタイトルが変えられることもあると知っていても、それでも必ず観に行ってしまう。
1959年のイギリスの田舎町。何年も未亡人として慎ましく暮らしていた主人公は一念奮起し、この港町で書店を開くことを決める。戦争で亡くなった夫とは、ロンドンの書店で働いていた時に出会ったのだ。書店は順調にすべり出すも、田舎町特有の僻み・歪み・妨害により、彼女は苦境に立たされていく――。まるで、救いのないジェイン・オースティンのような物語に、私は夢中になってしまった。
しかし、この映画の肝(キモ)は、映画のPR文にあるように、「英国俳優が紳士な引きこもりに!」なのだ。
推定70代で、城に籠っている読書家の老人と、彼女との関わりはこの映画最大の見せ場である。特にふたりが、あまりにも美味しそうなケーキを目の前に会話を交わすシーンでは身を乗り出してしまった。
しかし同時に、「わあ!紳士なオジサマ!萌え~」という風に思ってしまってはいけない、と、スクリーンを前に一瞬、冷静になってしまう。それは私の内面の、年上男性が好きだという思い込みに対するここ最近の疑問をもともなって浮かんできた違和だった。
確かに老人は主人公にとても優しくしてくれるけれども、それが恋愛感情である必然性はないだろう。年齢も立場も大きく異なる二人が恋に落ちることを否定しないけれど、なぜ、読書好き同志の友情に終始してはいけないのだろうか?
二人の物語に心動かされながらも、善意と好意を一緒くたに考えることはしていけない(たとえ「そうだろうな」と明確な場合でも)、と私はひとつの学びを得た。そうしてピンと背筋が正されたので、私はまた一歩モテに近づく強さを得た(に違いない)。
以前の、自信がない私は、善意を向けられたとき、何か対価を支払う必要があるんじゃないかとソワソワして、謝ってばかりいた。モテに目覚めた私は顎を上げ、「ありがとう」と心の底から言う。以前の自分から見れば偉そうな態度でも、それで十分なんだろうなと思っている。
帰り道、原作本も購入した。編集者による前書によると、原作者のペネロピ・フィッツジェラルドは60歳近くになってから作家デビューをし、63歳で権威あるブッカー賞を受賞したそうである。映画の中で主人公は、偏見なしに新たな書籍を読み、その世界にいざなわれる。私もまた新たな本を読み、映画を見ることによって、思考の柔軟さという「モテ」を手にしたい。
……と、ここまで書いて、私は気づく。私の「モテ」はどうやら男性に向けたものではないらしい。私が日々を、楽しく生きられるために必要なものであるのだと。
来月も新たな「モテ」の報告をお楽しみに!