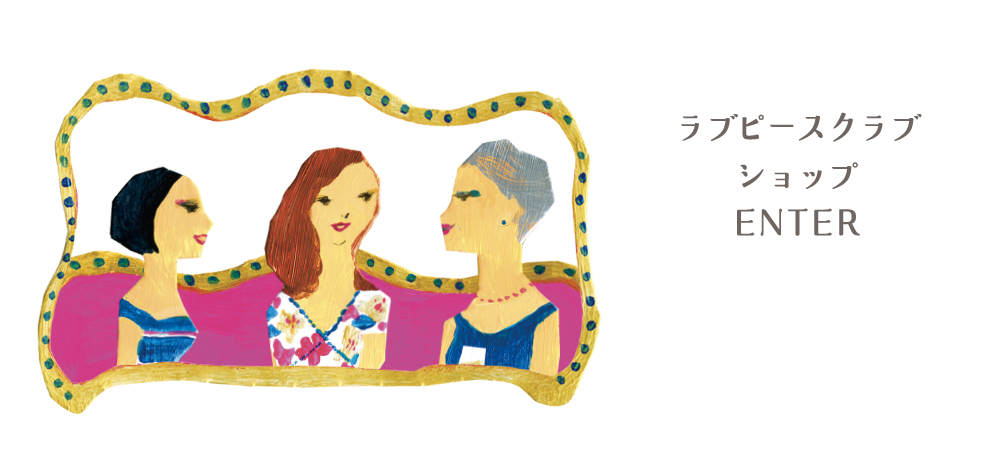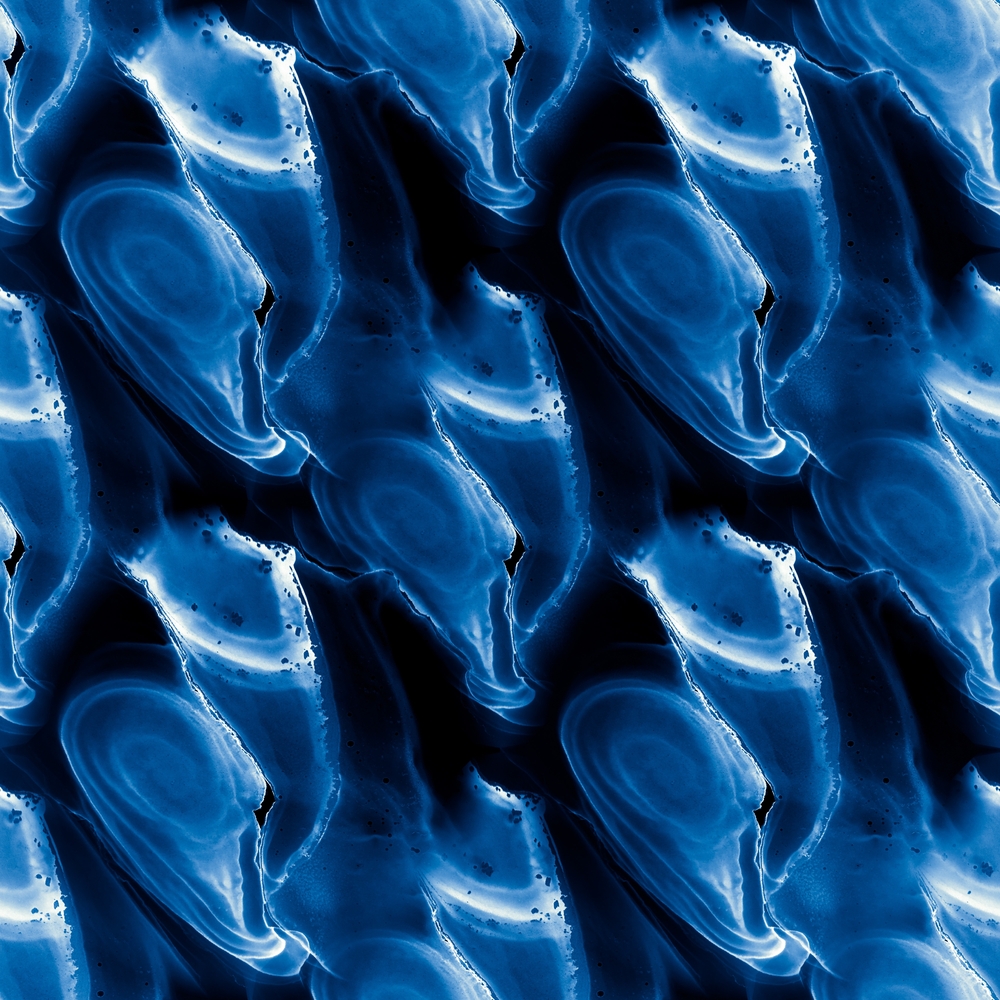ピーポーピーポー。遠くから聞こえる救急車のサイレンを聞きながら、私は後悔を募らせた。またやってしまった。
まだ冬が終わりきらない休日。私は友人と温泉に行った。おぞましい男湯の景色にすっかり滅入り、男湯に入ることができなくなってしまったFTMの私はここ数年、体毛を剃り女湯に入っている。今回ももちろん女湯だ。そこは地元の人しかいない公衆浴場だった。70歳オーバーのおばさんたちが、世間話をしている声が聞こえる。
私は怪しまれないよう、切除した平らな胸をタオルでしっかりと隠し、女であることを強調するために、下半身が丸見えのちょっとおかしな恥ずかしがり屋になりながら、いつも以上に内股で歩き、モザイクをかけられたニュース映像の目撃証人のように甲高い声を出し、お湯につかった。
--あ~あ、気持ちいい
友人から離れないようにぴったりとくっつき、湯船から外を見る。雄大な山に夕日が落ちるところだった。そのときだった。友人が私から離れ、サウナに行こうとした。
「えっ! 不安だから一緒にいて」
「人がこんなに少ないから大丈夫だよ」
そう言って、友人は人口密度が高いサウナに入って行った。
「行かないで~、行かないで~、行かないで~」
無理にトーンを精一杯張り上げた不自然な声が、小さくこだまする。
友人がいなくなり、さらに用心深くなった私はまわりを見渡し、誰もいないことを確認した。
--ここにいれば大丈夫。
そう思っていると、2人の女性が湯船に入ってきた。
--向こうのお風呂に移らねば。
私は湯船を出て、2メートル先にあるりんご風呂に移動しようとした。
ズルーーーーー、どてんーーーー。
床で足をすべらした。気がつくと、生まれたてのバンビのような妙な内股で床にぺたっと座っていた。
--何が起きたの?????
何もわからない。
--早く起きないと目立ってしまう! 早く平然と湯船につからなきゃ!
転んでも胸にタオルをしっかり当てている自分に安堵し、私は大丈夫! と立ち上がろうとしたとき、激しい吐き気が押し寄せてきた。1ミリも動けない。足をやられたか?! ならばのぼせた人を装い、寝てしまおう。そう思って横になろうとしても激しい吐き気で横にもなれない。動けない。
--これはまずい。
とあせっていると、友人がサウナからサウナに移動する姿が目に入った。
--助けて。
その声はまったく声にならなかった。私の足から、どぶどぶと血が流れていた。
ちょっと気が遠くなっていく。私のまわりには4、5人ほどの人が集まっていた。声を聞く限り70代から80代のおばあさんだ。
「あんた大丈夫か?!!!」「どこが痛いの?!!」「今すぐここの人が来るからね」
私は精一杯甲高い声で答えた。
「大丈夫です」
--気を失ってなんかいられない。
--いちばん存在を消さなければいけない場所で今私はもっとも目立っている。
--ピンチだ。
胸をタオルでしっかり隠せているか心配だった。
誰かがしきりに桶で私の足から流れる血を流している。その姿が目に入ったとき、剃り忘れていた右足に気がついた。
--やばい!
それは濃い足毛。そんじょそこらの男より立派な体毛だ。
--まずい!!!
しかし、タオルは小さい。胸を隠すので精一杯だ。足をもじもじさせ、右足が隠れるポーズを模索する。“カトちゃんのちょっとだけよ”みたいなポーズになった。
「あんた痛いのかい?!! 大丈夫すぐに担架来るよ。ここに非番の看護師さんもいるよ」
「担架来たよ。まずはこれに乗りな」
顔を直視されないよう、床に顔を押しつけていた私には、集まっている人たちの顔は見えない。わかるのは、みんなおばあさんで裸だということ。温泉施設の人が担架を持ってきて、私はごろんと転がるように担架に移動した。
「いいですか。みなさん協力してください。担架を脱衣所まだで運びます。みなさん、担架を持ってください」
集まっている人たちよりは若く40代くらいの声の温泉施設の女性が声をかけたと同時に、ぴたぴたと足音を立て、集まる音が聞こえる。
「私は神経痛で右肩やられてるから左手で持つからこっち持つよ」
「私は腰やってるから、脱衣所のドア開けるよ」
「あんたまだ70だろう。頭のほう持ちな」
「松本さーん、手伝ってくれますか?!!!」
「あいよーー」
「せーの」
あとから友人に聞いたところによると、おばあさんたち7人ほどと、友人とそして温泉施設の人が脱衣所まで運んでくれたそうだ。私は70キロ近い。
私は担架ごと、脱衣所の長椅子に置かれた。
「大丈夫だよ。私はこの前、膝の手術でここぱっくり切ったけど、へっちゃらだったんだから」
「寒いだろう。このタオルかけときな」
「ここに看護師いるから安心しな。町一番のベテランなんだから。非番で風呂に入っててラッキーだね。あんた」
地元のおばあさん同士の絆を感じる。私はそんな声の中、右足を見られないように、胸を見られないように必死にタオルの中に逃げ場を探した。
「名前言える???」
ベテラン看護師が声をかけ、私は、
「はい! アンティルです!!」
と必死にソプラノ声で名前を言った。
「大丈夫だと思うけど、こりゃ、救急車呼んだほうがいいね。腫れてきたよ」
「私、ロキソニンテープ持ってると。あと1枚だけど、これ、あげるよ」
足の痛みがひどくなっていたときだったので、その町一番の看護師の見立てに骨折かもと震えた。
--このまま東京に帰るわけにはいかないし、しょうがない。
「救急車呼んでください」
そう言った。
「あと10分で救急車来るそうです。松本さん、すみませんが中に入っている人が脱衣所に出てこないように門番しててください」
「あいよ!」
温泉施設の方に指示を受けた裸のままらしい常連客の松本さんがお風呂に戻る足だけが見えた。
「ここにあと少しで救急車が来ます! はやくお風呂に入ってください」
温泉施設の人が脱衣所にいる人に声を上げる。
「急いで脱ぐのよ。ほら早く」
お母さんが子どもの服を脱がしている。私は子どもだけにはこの体を凝視されまいと固くタオルでガードした。子どもは正直だ。
「なんだ。あの毛。男なの?」ということを平気で言う。油断ならない。
「松本さん。私、もう、じいさんのところ帰んなきゃ。まだ出られないの?」
「克子さん、もうちょっとだから。待ってやんな。サウナもう1回入っておいでよ」「菊江さん、だめだよ。まだ出られないよ。救急車来るから。見られちゃうよ」
「早く脱いで、お風呂行って。ほら早く。ほらほら」
裸のおばあさんたちが、事故現場を道路封鎖する警察のように警備体制に入った。顔をタオルに押しつけ何も見えない私にもわかる。テキパキと仕事をするおばあさんたちの熱気と気迫。私の頭の中で「踊る大捜査線」のテーマが流れた。
「大丈夫ですか?!!」
救急隊員がやって来た。引き続き必死に高い声を出して答える。
「大丈夫です!」
「あんた、しっかりしなよ。大丈夫だよ。私もこの膝、ぱっかり切ったけど・・・・」さっきのおばあさんの声が遠ざかる。
温泉施設を出て、ガタゴトと揺られながら救急車に乗り込むほんの数秒の間、見上げた夜空には星が瞬いていた。
「寒いです!! 寒いんです!!!!」
病院を探す間の救急車で私は寒さを訴えた。
車内には3、4人ほどの人がいるのに誰も私に何かをかけようとしない。
人差し指につけた脈拍の機械がはずれていないかばかりを気にしていた。
私は、抗議するように人差し指から機械をはずし、横に置かれたダウンを着る。それでも誰も補助しない。ある男は私の痛めた足にバンバン体に当たっているのに気がつかず、病院との電話に夢中になっていた。
「これはずさないでください」
「ダウン着られると体温計入れにくいんだよね」
心強いおばあさんたちと比べ、なんと気のきかない人たちだろうか。
目先のことしか見えていない! 察しない!! 考えない!!!
おばあさんたちに病院に運んでほしい。本気で願った。
おばあさん! 助けて!!!
「アンティルさん、この辺りの病院で整形外科の先生がいるところはなくて、100キロ離れた病院になります」
「そこまで行けばレントゲン撮れますか?」
「いや、そこでもレントゲンは無理です。今日は休日だし、夜ですから」
「東京では夜間でも休日でもレントゲン撮れますけど、本当に無理ですか?」
「無理です」
「では帰ります……」
救急車に乗ってから40分。私は静かに救急車を降りた。
友人に運転してもらい、東京に向かう。車窓に映る盆地の暗闇の中で、そこにないはずのおばあさんたちの顔がはっきりと浮かんだ。頼れるばあさんたち。女風呂を目指し、家を出るおばあさんたちが、お風呂で共に時間を過ごし、世間話をして家路に戻る。そんな日常で、女たちはしっかりと繋がっている。その連携プレーのなんとみごとなこと。救急隊員がおばあさんなら、警察官がおばあさんなら、政治家がおばあさんなら、この国はもっと住みやすいかもしれない。そう思いながら痛む足を引きずり自宅に戻った。
おばあさんたち、ありがとう。
私は元気に歩けるようになりました。