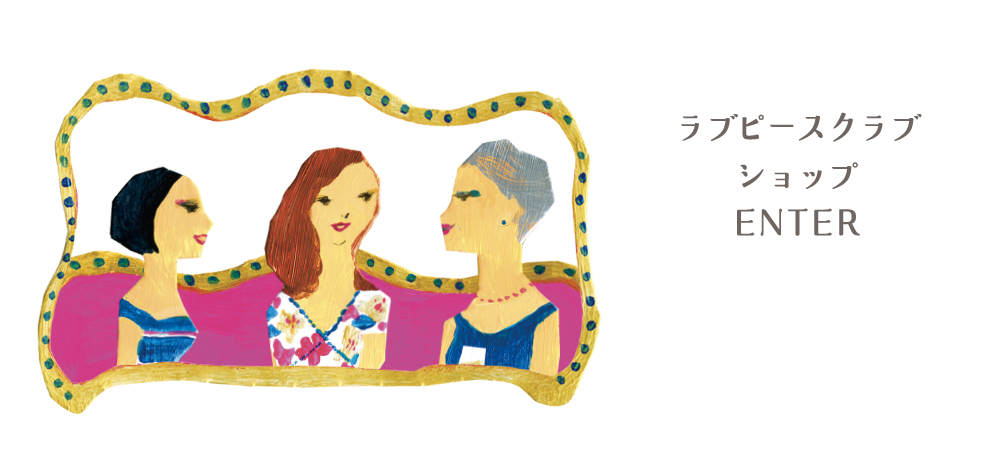以前、訳した本に「罪悪感と恥の違いは、罪悪感は自分がしたことに対して感じるものだけど、恥は自分がそうであることに対して感じるものなんだって」というセリフがあった。小学校時代の私は、自分の生活をひどく恥じていた。
私の家は小売りの商店をしていて、店には父方の祖父母と曽祖母が住んでいた。私の両親は店で働いていたのだけれど、別のところに2DKの小さなアパートを借りていて、私、両親、妹たちは店から離れたアパートに住んでいた。アパートは、私が通っていた小学校の学区外にあったので、朝、私たち姉妹は自転車で母と一緒に店まで行き、まだ閉まっているシャッターの前に自転車を置いて、店から歩いて学校に通っていた。小学校が終わると私たちは大人のいる店に帰り、夕方までそこで過ごしてから、母と一緒に自転車でアパートに帰るのだった。
たったこれだけのことだけど、たったこれだけの小さなことが、子ども時代の私にはたまらなく恥ずかしかった。
私が通っていた小学校では、自転車通学は禁じられていた。学校に届け出ている住所も店の住所で、教師が家庭訪問に来るのも店のほう。子どもの私には、店が社会的に公認された「ほんもの」の家で、アパートは人に言ってはいけない「にせもの」の家のように見えていた。人には言えないことをしているのだと思っていて、アパートに住んでいることは、友達にもできるかぎり隠していた。
店とひと続きになった祖父母の住居には、倉庫や「裏」と呼ばれる別棟もあり、敷地はそれなりに広かった。私は、広い祖父母の家から狭いアパートに帰るのが嫌だった。にせものの生活が、早く終わればいいのにと思っていた。
アパートから店までの間には同級生の男の子が住んでいて、自転車で移動する私たちを見ると、その子はにやにやと笑い、「いけないんだ」と言うのだった。私は言い返すことができなかった。
アパートに引っ越す前、私がまだ幼稚園に通っていたころは、私たち一家は店のある祖父母の家に住んでいた。ある日、その祖父母の家から、母がいなくなった。真ん中の妹を連れて買い物に行ったまま、戻らなかった。このとき、5歳違いの一番下の妹は、まだ生まれていなかったように思う。ということは、私は4歳くらいだろうか。大人たちのなんとなく慌てたような雰囲気を覚えている。その夜は、父が寝かしつけてくれた。母はどうしたのかと聞く私に、父は「帰ってくるからね」と言って、安心させた。
父はやさしかった。私は子どものころ、ときどき呼吸の仕方がわからなくなった。呼吸に意識を向け始めると、息を「吸う」「吐く」という動作をどうしていいのかが、わからなくなるのだった。この発作があんまりたびたび起こるものだから、私は解決法まで編み出していて、呼吸の仕方がわからなくなったら思い切って限界まで息を止めることにしていた。そうすると、もう我慢できないところで自然に口が開き、呼吸が始まるのだった。この話をしたとき、母は「何バカなこと言ってるの」と取り合わなかったが、父は「うん、考えるとわかんなくなっちゃうよね」と私に寄り添うのだった。私の性格は母に似た。
母は、家出をした翌日に帰ってきた。父の兄の家に一泊したのだと言う。実家に心配をかけたくない母は、すぐにばれる父方の親戚の家にいきなり押しかけたのだった。どうして私を連れて行ってくれなかったのか、私は母を問いただした。「おつかいに行こうって、いくら誘っても来なかったから」というのが返事だった。そう言われてみると、たしかに前日テレビを見ているときに、「おつかい行くよ」と言われ、「うーん」と生返事をしているうちに妹と母が消えたような記憶があるのだった。
母の家出の原因を、私は知らない。けれど、母の家出から程なくして、私たち一家はアパートに引っ越した。そして、自転車の日々が始まった。
家出のことは母の記憶にも強く残っていたのだろうか。母は自分の子ども時代のエピソードとして、祖母が家出したときの話を何度も私に語って聞かせた。「おじいちゃんとおばあちゃんは仲がよくなかったから、なんで早く離婚しないんだろうって思ってた。お母さんがすごく小さいときね、おばあちゃんが家出をしようとしたことがあって。それで、お母さんを連れて夕方に家を出たんだけどね、“毛糸のパンツ忘れた。戻ろう”って言うの。それで家に帰ったの。毛糸のパンツなんてどうでもいいから離婚してほしかったのに」
毛糸のパンツとは、小さい母が冬場に履かされていた防寒用のパンツのことだが、初めてこの話を聞いたとき、毛糸のパンツのために家に帰るという理屈が私にはわからなかった。母によればそれは、祖母が家に帰るための口実ということだった。「ほんとうは家出したくなかったんじゃない」と母は言った。でも、私が気になったのは、母の兄たちのことだ。母には兄がふたりいる。どうして祖母は母だけ連れて行ったのか、子どもの私はそこのところが知りたかった。「いちばん小さかったからじゃない?」と母は言った。
小学校3年生くらいだっただろうか、どうして私たちはアパートに住んでいるのか母にと詰め寄ったことがある。どんな言葉で説明されたかは覚えていないが、ようするに母と祖母の折り合いが悪いからということだった。私にはそれが、母のわがままのように思えた。わが家では多くの家と同じように、母が私を教育し、叱る役で、父と祖母は私を甘やかしていた。私はやさしい父と祖母が好きだった。
子ども時代、私は母のことを恐れていのだけれど、父と祖母がいると急に強気になって母をからかったりもした。たとえば、家族が集まる昼食の席で、私は母に「お母さん、厚化粧だからお化粧しないで」と言ったりした。小学校低学年のころだったと思う。祖母は「クククっ」という、声にならない小さな声を立てて笑っていた。祖父か父がその場にいたと思うが、何も言わなかった。
商売をしているわが家では、母は店の仕事をし、家事もほとんどひとりで引き受けていた。「店」で、祖父母と曽祖母、従業員の昼食や夕食を作り、アパートに帰ってまた夕食を作り、家事をしていた。母はいつも疲れてイライラしていて、私にとても厳しかった。叱られなかった日に、ふと「あ、今日は怒られなかった」と思ったのを覚えている。誕生日のプレゼントに何が欲しいか聞いたときに「自分の時間」と言われたこともある。さくらももこが何かのエッセイで「実家は商店をしていて、母親はいつも疲れ切っていた」と書いていたのを読んだとき、私の家と同じだと思った。
最近、離婚して実家に住むようになった私は、母と話す機会が増えた。中国育ちのアメリカ人女性作家パール・バックに『大地』という小説がある。母は、この小説が大好きだ。何度も読み返しているそうだ。先日、母が言った。
「お母さん、パール・バックの『大地』に出てくる奴隷だった女の人がすごく好きなんだけど、なんでだかわかった。その人、徹底的に人間扱いされてないの。お母さんと同じだって思った。美人じゃないし、その女の人のおかげで家は金持ちになるんだけど、旦那は妾をつくって、その人には見向きもしなくなるの。主人公はもともと農民だったんだけど、動乱のときにその女の人が宝石を手に入れて、それでその宝石を主人公が取り上げてお金持ちになったのに」
私は動揺した。「お母さんとお父さんとの関係のことを言いたいの?」と聞いてしまった。母は、少し考えてからこう答えた。
「でもね、女の人は誰でも人間扱いされていないと思うの。女性の権利は、意識の高いフェミニストの人が闘ってくれてるんだと思ってたんだけど、そういう人たちだって、女というだけで人間として扱われてない。お母さんみたいな地を這う生活をしている人だけじゃなくて」
たしかにどんな女性も、この社会では人間扱いされていない。それはそうなのだけど、「徹底的に人間扱いされてない」「地を這う生活」。そこまで言う母に、私はひどく戸惑った。
私が中学生になったころ、私たち一家はアパートを出て、2世帯住宅のように改築した店の別棟に引っ越した。
「女性の権利は、意識の高いフェミニストの人が闘ってくれてるんだと思ってた」と言う母は、まるで自分は何もしていないようなことを言うけれど、私は母が闘っていたことを知っている。
ベル・フックスは『フェミニズムはみんなのもの』で次のように述べている。
フェミニズム運動は、あらゆる年齢の女性や男性が、性差別をなくすために努力しさえすれば前進する。そのためには、必ずしも組織に参加する必要はない。どこでも、自分のいる場所で、フェミニズムのために努力することができる。たとえば自分が今住んでいる家で、フェミニズムの仕事を始めることができる。フェミニズムについて勉強したり、愛する家族を教育したりすればいい。
(ベル・フックス『フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学』堀田碧訳、エトセトラブックス、2020年、p.178)
私と妹は、フェミニストでありながら、父の世話をなんでもする母に矛盾を感じていた。でもたぶん母は、そうしながらも自分にできる範囲でベル・フックスが言ったようなことを実践していたのだと思う。母は私が子どものころから、家の中での男女の立場の違い、その理不尽を折りに触れて語っていたし、男女は対等なのだと繰り返し教えてくれた。性教育の絵本も買い与えてくれ、性犯罪というのは男による女の支配が目的なのだと子どもに対してもはっきりと説明していた。ボーヴォワールの話をしたり、『青い目茶色い目』というドキュメンタリーの本で人種差別について教えてくれたりもした。『橋のない川』『カムイ伝』「慰安婦」のこと。母は子どもにもきちんと説明した。そうやって、私をフェミニストに育ててくれた。
子どものころ、母ひとりのせいだと思っていた私の苦しみの原因が何だったのか、今ならわかる。母は闘っていた。たとえ一晩、私を置き去りにしたとしても、私の心に恥と混乱をもたらしたとしても、母は闘っていた。娘にさえ味方してもらえなくても、母は闘っていたのだ。
家父長制がなかったら、男女がほんとうに対等だったら、「嫁」が「婚家」でも尊重される世の中だったら、家のことが母ひとりにまかされていなかったら、子どものころの私と母の関係は、ぜんぜん違ったものになっていただろう。これは、私と母だけの問題ではなく、日本中のたくさんの母娘の身に、今でも起こっていることだ。
私はよく「怒りを抱いている」と言われる。そうかもしれない。最近読んだ、イギリスの小説にアメリカの黒人レズビアン・フェミニスト詩人オーロドリー・ロードの言葉が引用されていた。
私は、母の秘められた詩と彼女の怒りの反映なのである。
(Deborah Levy, The Cost of Living: A Working Autobiography, Bloomsbury Publishing, 2018, trad. fr. Le Coût de la vie, éditions du Sous-sol, 2020)
私は詩人でも小説家でもないけれど、この言葉は私のことをとてもうまく言い表している。私も、母の怒りの反映なのである。