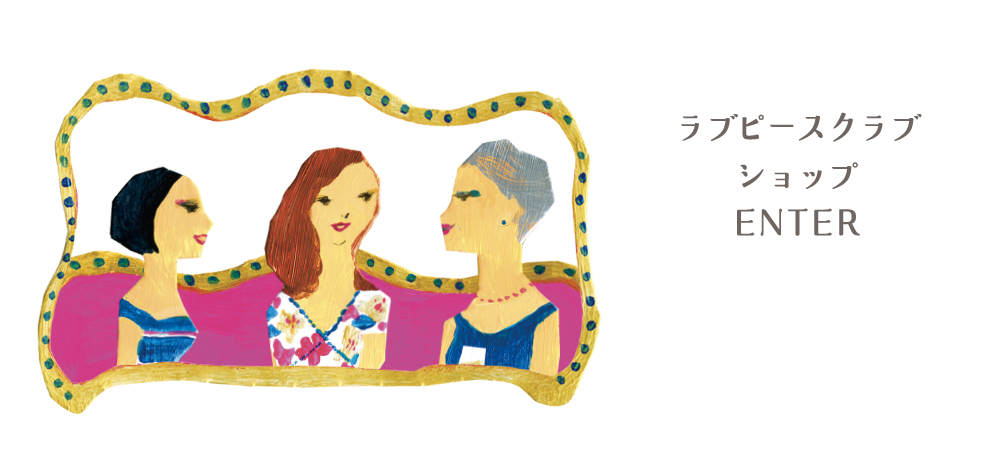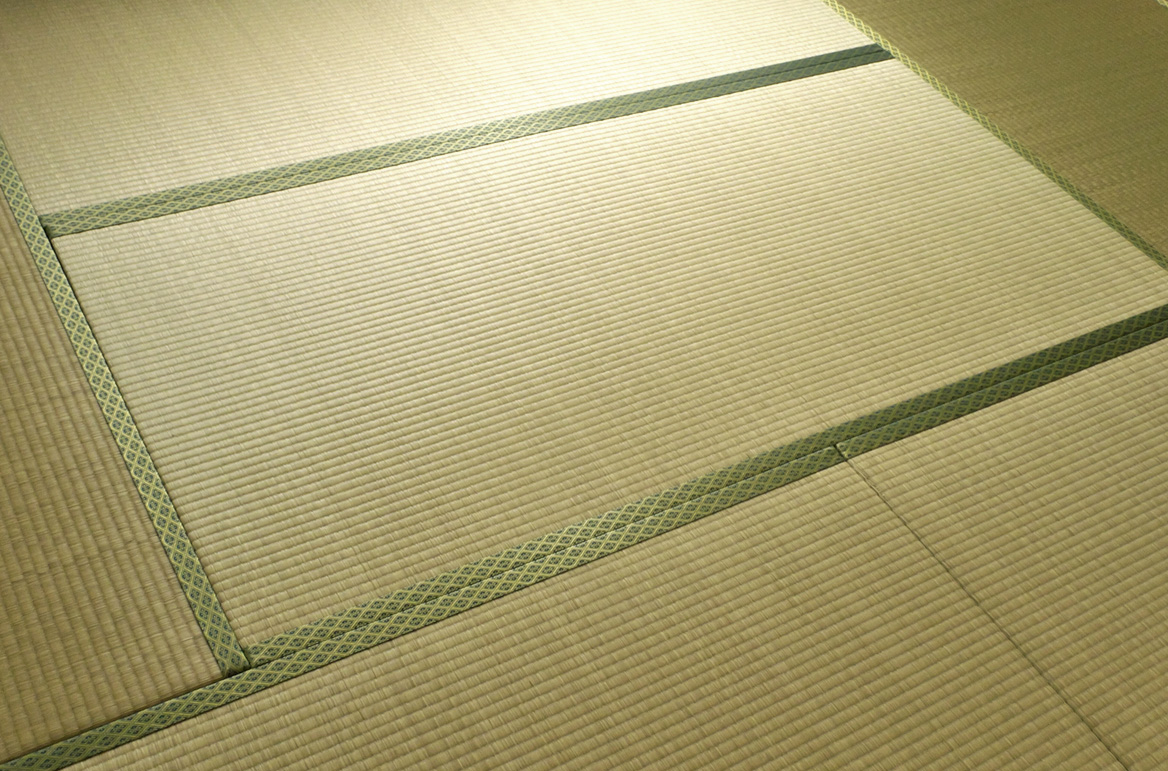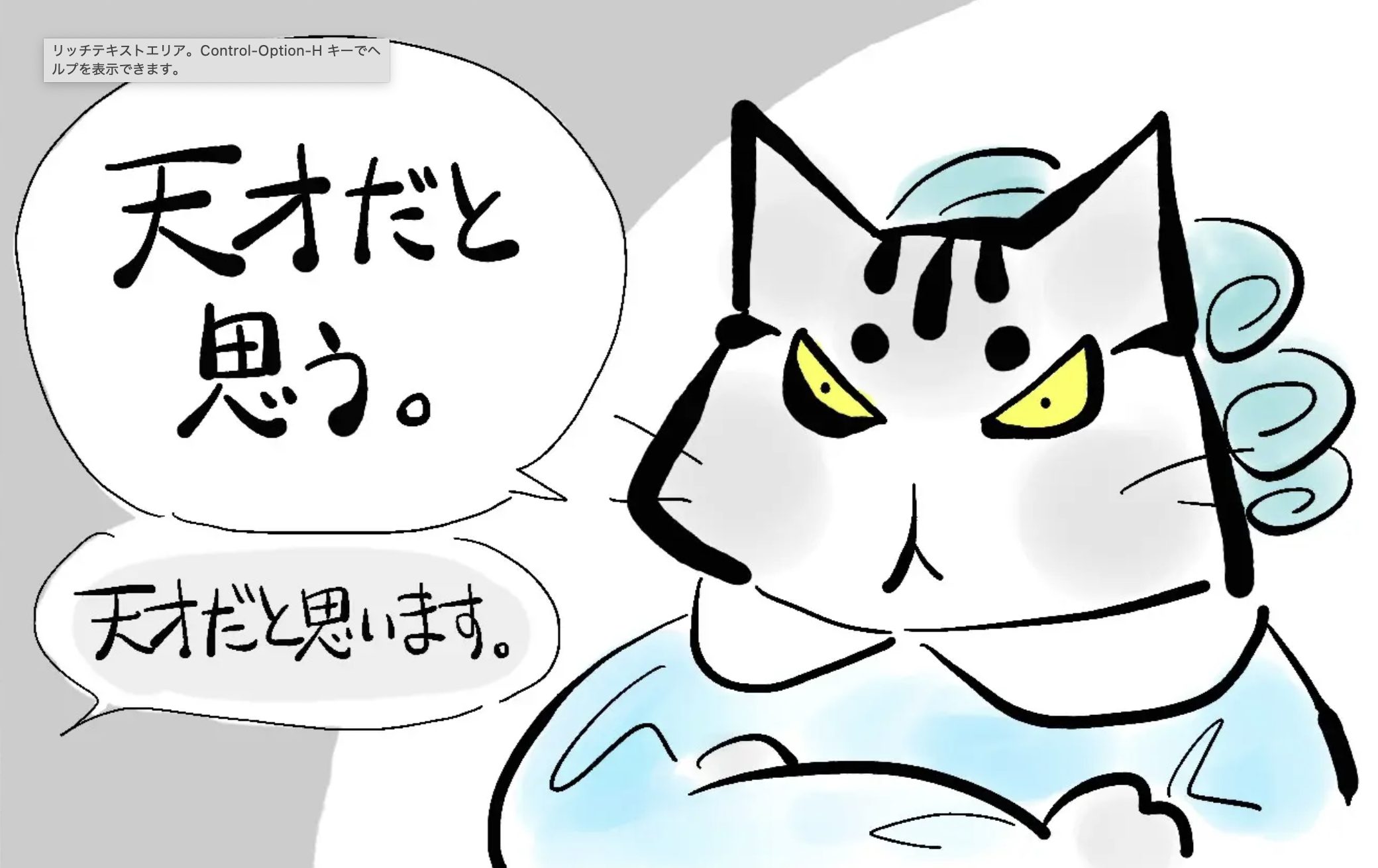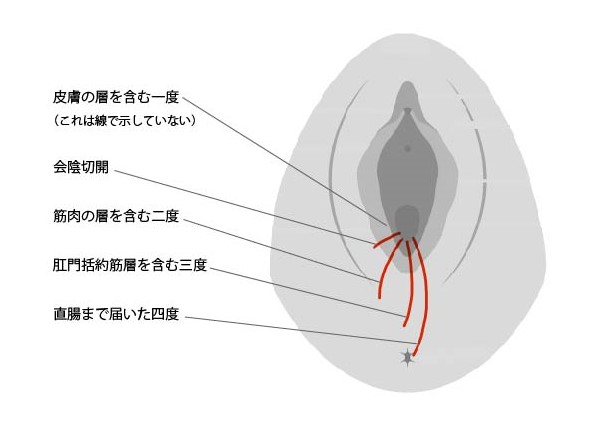結婚式まで半年を切った頃から、私は山田仕郎と大ゲンカをするチャンスを窺い始めた。
もう、てっとり早く口喧嘩でもしない限り、踏み込んだコミュニケーションは取れそうにないと思ったのだ。
二人きりでいても会話のラリーはせいぜい続いて3往復がいいところだったし、恵美子さんやお嬢さんが同席していると、結局その二人との会話になってしまう。山田仕郎に関する質問を投げかけても、本人よりも二人の方が饒舌に喋れてしまうからである。
半年後の2月には結婚式が挙がってしまうというのに、山田仕郎本人のことはさっぱりわからないままだった。
これは営業職の沽券に関わる大問題だわ、と私は思っていた。
営業としてお客さんから情報を聞き出すことはむしろ得意な方だと思っていたのに、全然ダメだ。
結婚式の打ち合わせや恵美子さんの監督下の食卓など、顔を合わせる回数が増えるごとに私の居ても立っても居られないような、焦るような気持ちは強くなっていった。
最初に自分がブチ切れるタイミングをはかっていると気づいたのは、他のカップルが結婚式の打ち合わせをしていて口論になったのを目撃した時だ。大体の結婚式場には商談スペースのような4人掛けから6人掛けのテーブルが幾つも並んだ空間があって、同時に何組かのカップルがそれぞれの担当者と打ち合わせを進めていることがある。
「もぉ、なんでそんなに適当なの?!」
そう声を荒らげた女性の横で、パートナーの男性が「ごめんごめん」と困ったような顔で笑っていた。二人と同席していたウエディングプランナーの表情はこちらに背を向けていたせいでわからなかったが、きっと慈母のような微笑を浮かべて見守っていたに違いない。
そう言えば、つばさちゃんから聞いた同期の子のところでも『大体毎回喧嘩になっちゃう』とか何とか言っていた。初めて生で見たなぁ、と他人事のように思っている私のテーブルは今、プチギフトの打ち合わせをしているところだ。
背後の喧騒をものともせず、熟練のウエディングプランナー、サトウさんはカタログを広げた。
「送賓の時にお渡しすることが一般的ですね。披露宴の前はディスプレイとして置いておいて、そこから一つずつお渡ししていくスタイルが人気ですよ」
どういうことなのかと思ってカタログをまじまじと見つめると、入浴剤やキャンドル、マシュマロやキャンディーなどが入った小箱が大きなウエディングケーキのように積み上げられている写真が載っていた。可愛い。
「仕郎さんは、これまでに受け取ったプチギフトで何か印象に残っているもの、ありますか?」
そう私が尋ねると、即座に「いや、記憶にありません」と政治家のような答えが返ってきた。
サトウさんが間髪入れず、「ミナトさんは何か印象深かったプチギフト、ありましたか?」と聞いてくる。
山田仕郎で会話が止まってしまうことを既に理解しているのだ。
私は暫く考え、紅白のプチギフトを思い出した。
「赤麻婆と白麻婆の簡単調味料を配ってた式があって、それは普通に嬉しかったですねぇ。辛いものが苦手なゲストの為に、新郎は回鍋肉の素も何箱か手に持っていて」
「まぁ」とサトウさんは頷き「行き届いてらっしゃいますねぇ」と褒めた。
山田仕郎は何も言わない。そもそも私とサトウさん、どちらの顔も見ていなかった。視線の先を見ると、さっき言い争っていたカップルの方を眺めていた。二人は落ち着いた様子で打ち合わせを続けている。
「新郎の格好って、どうしても落ち着いた色合いになるじゃないですか、そこに緑色のパッケージ持ってて、やたら鮮やかで凄く印象に残ったんですよね。麻婆の素、あったらあったで使いますしね」
サトウさんと私が笑っていると、山田仕郎が突如こちらに視線を戻し「やめましょう」と言った。
「ミナトさんのような人はそれでいいかも知れませんが、年寄がどう思うか」
水を差された私とサトウさんは共に微笑を浮かべたまま沈黙し、私の脳内では今の発言が『ミナトさんのような人はそれでいいかも知れませんが/年寄りがどう思うか』に分解された。
先に後半の方を潰そう。
「恵美子さんのことをおっしゃってます?」
私は具体的に人名を出すと、山田仕郎は憮然とした表情で「そうですが」と言った。
すんなり聞き入れられなかったので癪に障ったようだ。
駄目だなぁ、ここで「いえ、主賓の教授です」とでも言っておけば、まだ大丈夫だったかも知れないのに。
「たしかに、普段使いのものをお渡しするは、ハレの日にふさわしくないと思う方もいらっしゃるかも知れませんね。でも、何も披露宴の引き出物でお渡ししようって言うんじゃないんですよ。引き出物は引き出物で、ちゃんと百貨店の包装紙に包まれたものが用意されていますし、プチギフトはゲストをお見送りする時に手持無沙汰だからお渡ししているようなものですしね」
たしかに私は、恵美子さんが人さまからの贈り物にケチをつけているのを聞いたことがある。
それは恵美子さんのお嬢さんの夫の親類が持ってきた手土産で、そもそもお嬢さんの夫を含めそちらサイドの全ての人間を恵美子さんは嫌っていた。姑にあたる恵美子さんは、娘の夫とめちゃくちゃに不仲なのだ。嫌いな相手が持ってきたものなんだから、その時点で既にハンデ戦であるし、「手作りだなんて、どういうつもりなのかしらね」と恵美子さんが文句を言いながら切り分けた手作りのパウンドケーキはジューシーなドライフルーツがたっぷりでとても美味しかった。恵美子さんは、嫌いな相手が料理上手なのも気にくわないようだった。
その時の私は、恵美子さんの文句に頷き続け、神妙な顔のまま手を出そうとしない山田仕郎を尻目にパウンドケーキをパクッと食べて「おいしー!」とか何とか言った気がする。別に恵美子さんは私の振る舞いに怒ったりしない。
「それに、赤麻婆と白麻婆がプチギフトだった話、恵美子さんにお話ししたことがありますよ」
「まぁ」と言ったのはサトウさんだ。
このタイミングで相槌を打たれるとある意味火に油なんだけどな、と思ったけれど、私はそのまま続けた。
「恵美子さん、『面白いじゃない、安いクッキーなんかよりも、よっぽど気が利いてるわね』っておっしゃってましたよ」
嘘じゃない、本当の話だった。
恵美子さんの名前が出てきてしまうと山田仕郎は自分の意見が無くなったのか、
「それならそうと、最初に言ってください」
と言って黙った。そうして、カタログを引き寄せて自分だけで読み始めた。
けれど本題はそっちじゃない。
さっきポロッと口に出した『ミナトさんのような人はそれでいいかも知れませんが』だ。
私を何だと思っているんだろう。
「ところで、私のような人はそれでいいかも知れないって、どういう意味ですか?」
そう微笑んで尋ねると、山田仕郎は心を閉ざしたような顔をしてしまった。
お花ちゃんはよく、「怒ってる時のお前こわい」とか「王様に怒られてるみたい」とか、幼児のようなことを言っていた。
そういう話をするのは特に喧嘩をしていない時だったので、お花ちゃん王様に怒られたことあるのかよ、と笑い飛ばしていたが、要するに対等な喧嘩を出来ていないという指摘だったのだと今では思う。
お花ちゃんとはもう喧嘩は出来ない。
反省は今目の前にいる相手に活かすしかない。
心を閉ざした山田仕郎の横で「そう言えば可愛いアイシングクッキーのお店があるんですよ」「ディスプレイしなくても籐のかごに詰め込めば可愛いですね」などと打ち合わせを続けながら、私は、山田仕郎がちゃんと言い返せるような環境で口喧嘩をしよう、と思った。