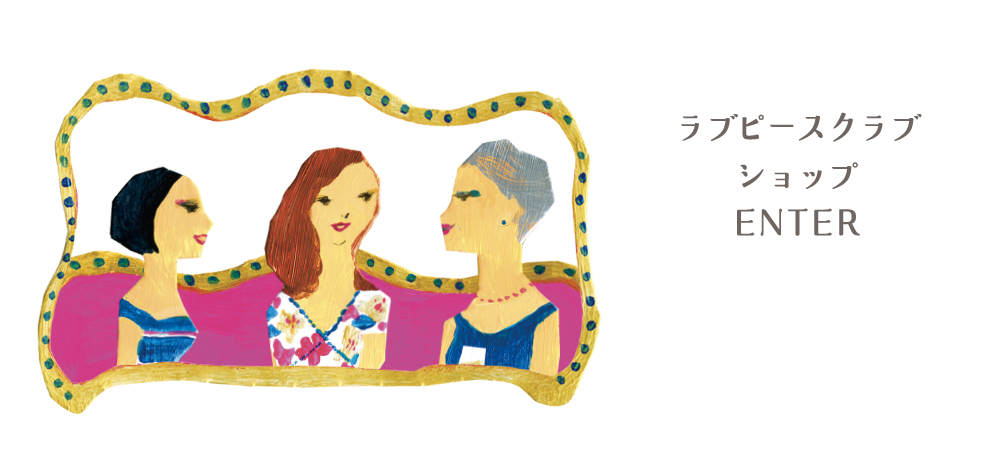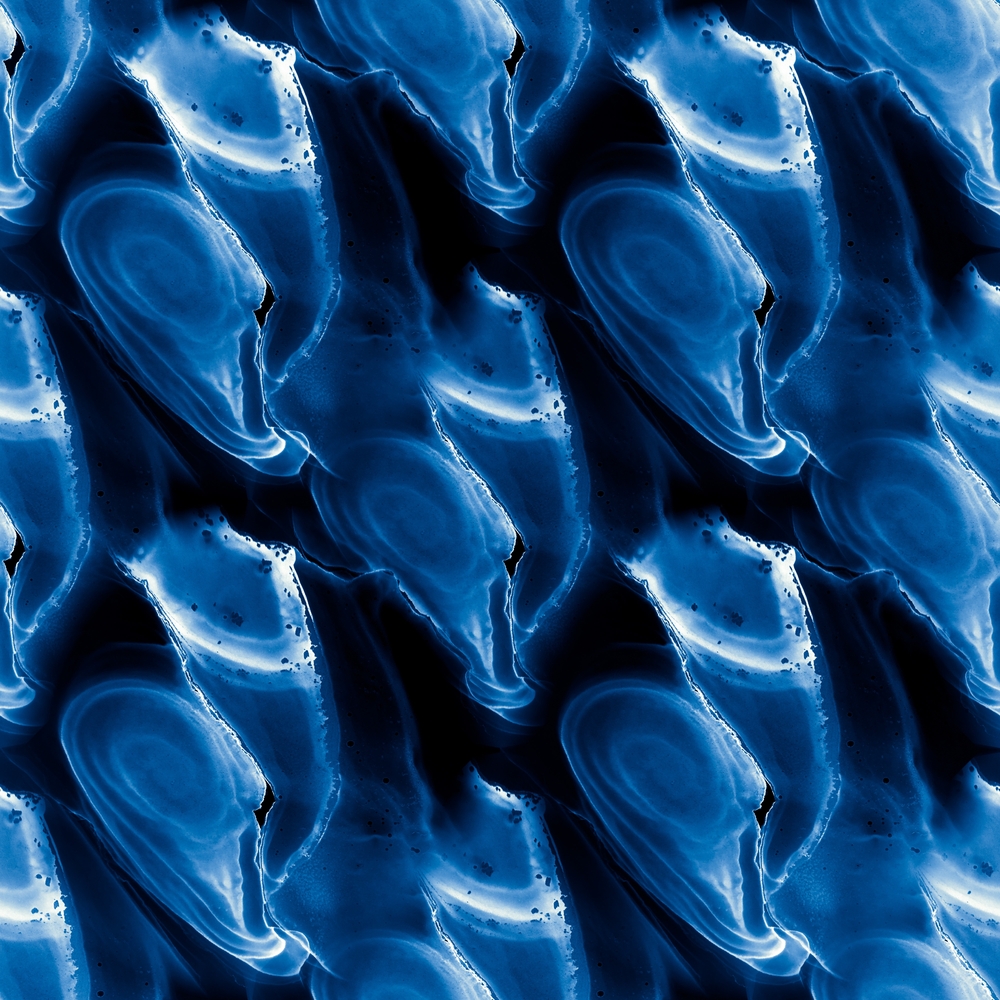こんにちは。先月に続きお会いできてうれしいです。行田トモです。
やっと梅雨が明けましたね。行田は7月31日生まれ(ハリポタと同じだよ!)なのですが、誕生日に梅雨が明けていないなんて、びっくりでした。そして猛暑さんがブルペン入りした感じですね。みなさまくれぐれもお身体大切になさってくださいね。
それでは、今月も行田の話におつきあいください。
今年、コロナが猛威を振るい始める前、「VOGUE JAPAN」(コンデナストジャパン)が革新的なプロジェクトを開始していたのをご存知でしょうか?
https://www.vogue.co.jp/vogue-change
その名も“VOGUE CHANGE”
ジェンダーや多様性、サスティナビリティ、社会課題を中心としたトピックスや、女性をエンパワーメントする話題を広めようという活動です。「え、めっちゃ勉強になる。ありがてぇ……」と思ったと同時にとても大きな一歩だと感じました。書店で目立つところに置かれる本の表紙に「ジェンダー」と書かれていたら、通りすがりの人の目に触れる機会が多いからです。それだけでも十分な影響力があります。
そんなことを思っていたら次は雑誌「PEN」6/15号(CCCメディアハウス)。
https://www.pen-online.jp/magazine/pen/497-talkaboutgender/
ガッとつかんでサッとレジに向かいました。
少しずつだけど、確実に変わってきている。そう感じました。
サスティナビリティとダイバーシティ。
これからのわたしたちの生活になくてはならないものになりつつあるのでしょう。そして、さらなる出会いの連鎖がわたしに訪れます(モテ期……?)
今度はとある書店の片隅。
絵本のコーナーでした。
美しい少女の横顔とその頭から広がる海。
『ねえさんの青いヒジャブ』という本でした。
カバー袖にはこう書かれています。
“ねえさんのヒジャブは、海みたい、空みたい。
どこまでもつづく青にさかいめなんてない----”
6年生で初めて学校にヒジャブをかぶって登校するアシヤと、その青いヒジャブとねえさんに憧れながらも、うまく言葉にできない不安もある妹のファイザー。
ファイザーの目線で描かれるこの物語は、ムスリム女性が幼い頃から直面する偏見や差別を訴え、それに立ち向かう姉の強さと美しさを讃えています。
実はこの本の著者であるイブティハージ・ムハンマド氏は、アメリカのスポーツ史、そしてムスリム史に名を残した人物です。
彼女は、フェンシング選手であり、アメリカ女性として初めてヒジャブをつけてオリンピックに出場したアスリートなのです。2016年のリオ・デ・ジャネイロ五輪では団体戦で銅メダルを獲得しています。本書によると、初のヒジャブをつけたバービー人形のモデルにもなったそうです。
彼女はあとがきで、ヒジャブをつけた際に「なんでテーブルクロスを頭につけているのか」とクラスの男子にからかわれたと話しています。そしてこう続けます。
“その時、実感しました。自分の信仰がもとになって周囲のわたしに対する接し方がかわり、自分が「よそ者」になりうるのだとと̶̶̶----(中略)でも子ども時代から大人になるまで、外見を気にせず、心ない言葉をかける人を無視できるようになるまで、ずいぶん時間がかかりました。それは簡単ではありませんし、今の女の子たちも同じこと----ときにはもっとひどいことに----直面していると思うのです。”
『ねえさんの青いヒジャブ』あとがきより
(文 イブティハージ・ムハンマド&S・K・アリ/絵 ハテム・アリ/訳 野坂悦子/BL出版/2020)
これを読み、胸が痛むと同時に、わたしはあることを思い出しました。
わたしは、緑のランドセルがほしい女の子でした。
本人はすっかり忘れていて(友人がお姉さんのお下がりの横長の黒いランドセル(私立?)なのがうらやましかったことを覚えていました)、母から聞いた話です。
ランドセルのカタログを見ながら「ともちゃんはどのランドセルがほしい?」と聞かれ、
「この色!」とわたしが指をさしたのが緑のランドセルだったそうです。
そういえば、ホームビデオにも、兄の幼稚園の運動会の弟妹参加コーナーで、他の子が素直に渡されたものを受け取り喜ぶなか、自分が好きな青い風車をもらえるまで待ち続ける姿が映っていました。三つ子の魂百まで……!
母も6年間も使うものだから、本人が好きな色がいいだろうと、緑のランドセルを買おうと思う、と同じ社宅の人に話したそうです。すると、相手の方はこう言ったそうです。
「転勤先でランドセルの色ひとつでイジメにあうかもしれないから、やめたほうがいいんじゃない?」と。
そう、わたしは転勤族でした。緑のランドセルでは、ただでさえ「よそ者」なのに、変に目立ってしまう可能性がぐんと上がったことでしょう。
その意見を聞いた母は、娘を心配して、赤いランドセルにしました。わたしはそれを6年間大事に使いました。
問題は別のところにありました。教科書をフルに詰め込んだランドセルを背負ったら立てなかったのです……。
この話を聞いたのはランドセルのCMを見ている時でした。「えー、全然覚えてないやー」と振り返ると、母は泣いていました。ずっと緑のランドセルを買ってあげればよかったと後悔していたと。ごめんね、と。
わたしは思いました。
あぁ、この人の娘でよかった、と。
イブティハージのお母様も、毎日つけるようになる前に、特別な日などに娘にヒジャブを着せて登校させ、少しずつ周囲を慣れさせようとしていたそうです。
ここでもまた母が重なり、目頭が熱くなりました。
それでも心ない言葉を浴びせてくる人はいるものですね。実に悲しいことです。しかし、イブティハージはあとがきで力強く語ってくれています。
“さいごに大声で言いたいのは、「わたしのヒジャブはわたしの一部」だということ。ヒジャブは、アッラーに対する信仰と愛の証です。母や妹たちとわたしが、誇りをもって分かちあうひとつの伝統です。わたしのヒジャブは美しい。このお話をそこで読んでいる、ヒジャブ姿の少女の皆さん。つまり、あなたのヒジャブも美しいのです。”
『ねえさんの青いヒジャブ』あとがきより
(文 イブティハージ・ムハンマド&S・K・アリ/絵 ハテム・アリ/訳 野坂悦子/BL出版/2020)
なんと美しく、力強い言葉でしょう。
わたしはこの絵本が日本の書店に並んでいることを改めてうれしく感じました。このお話は、ヒジャブに限らず、大切な、キラキラしたメッセージをたくさん含んでいるからで す。そして、ヒジャブ姿の人を街で見かけても当たり前の光景だと感じる子がひとりでも多くなることを願ってやみません。
さて、次はオーストラリアからのお話です。この絵本とは病院の待合室で出会いました。
『くまのトーマスはおんなのこ ジェンダーとゆうじょうについてのやさしいおはなし』
(ジェシカ・ウォルトン著/ドゥーガル・マクファーソン著/川村安紗子訳/ポット出版プラス/2016)
主人公のエロールは、くまのぬいぐるみのトーマスといつも一緒に遊びます。自転車に乗り、野菜を植え、ツリーハウスでサンドウィッチランチをとり、雨の日はお部屋でティーパーティです。
ところが、ある日、トーマスの様子がおかしくなってしまいます。元気がなく、エロールも心配でなりません。つらそうにしている理由を話してほしいと彼が頼むと、トーマスはその理由を知ったらもう友だちではいられなくなるかもしれない、と答えます。
そんなことはないと断言するエロールに、トーマスは深呼吸をして言います。自分は男の子のクマではなくて女の子のクマだと。
心の中ではいつもわかっていて、自分らしくいたいのだと。
そして、名前も「トーマス」ではなく「ティリー」がいいと思っていたと。
さて、エロールはどんな反応をし、ティリーはどうなるでしょうか? みなさん、ぜひ絵本を手にとって読んでみてください。あえて、ここで結末は書かないことにします。
この絵本はクラウドファンディングによって発売されました。きっかけは著者のジェシカが18カ月の息子、エロールに家族の多様なあり方を伝える絵本がほしかったからだそうです。というのも、ジェシカ自身はバイセクシャルであり、彼女の父親は女性へと性別移行をしたからです。
彼女はジェンダー・アイデンティティに関するサイトも立ち上げています。
www.jessicawalton.com.au
やさしい笑顔があなたを出迎えてくれますよ。
そうそう、わたしが出会ったもうひとつのステキなものについてお話ししてもいいですか?
ある日、ピルを処方してもらいに婦人科に行きました。定期的な、いつものルーティー ン。待合室にめぼしい雑誌もなく、あくびをしながらあたりを見回すと、看護師長と思われる女性の胸にレインボーバッジが。普段はあまり気にしないリーフレットコーナーを見ると、レズビアンに向けたものが。なんと。「面倒だなぁ」と通っていた病院は、アライ全開だったのです。
今では診察の際も女性のパートナーがいると話をしています。そして、診察を待つのも楽しい通院日に変わったのでした。
今回ご紹介した絵本はどちらもわたしが偶然見つけたものです。病院も偶然選んだものでした。このようなステキなギフトに出会えると、未来がほんの少し明るくなるように思えます。
でも、ギフトを待っているだけではいけませんよね。わたし自身がギフトを与えられる人になりたい。このコラムを書いていてそう感じました。
そのためにできることはなんだろう? 頬杖をついて考える夏です。