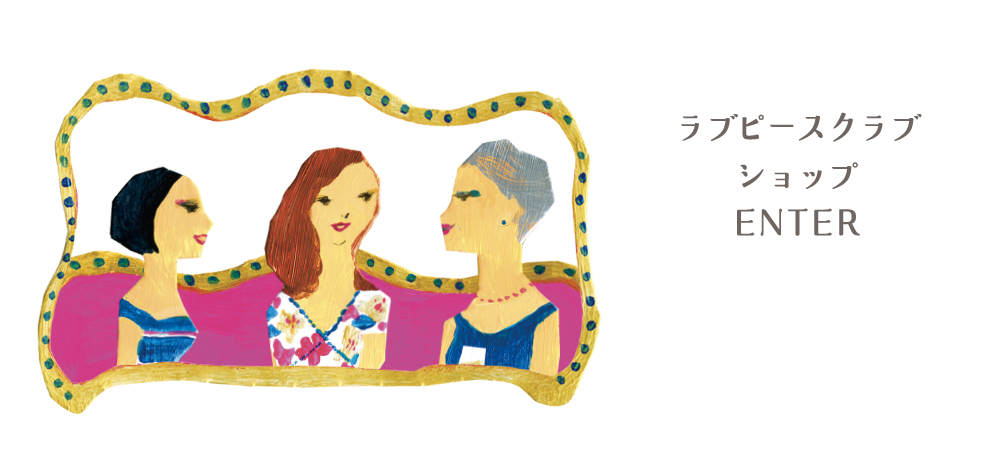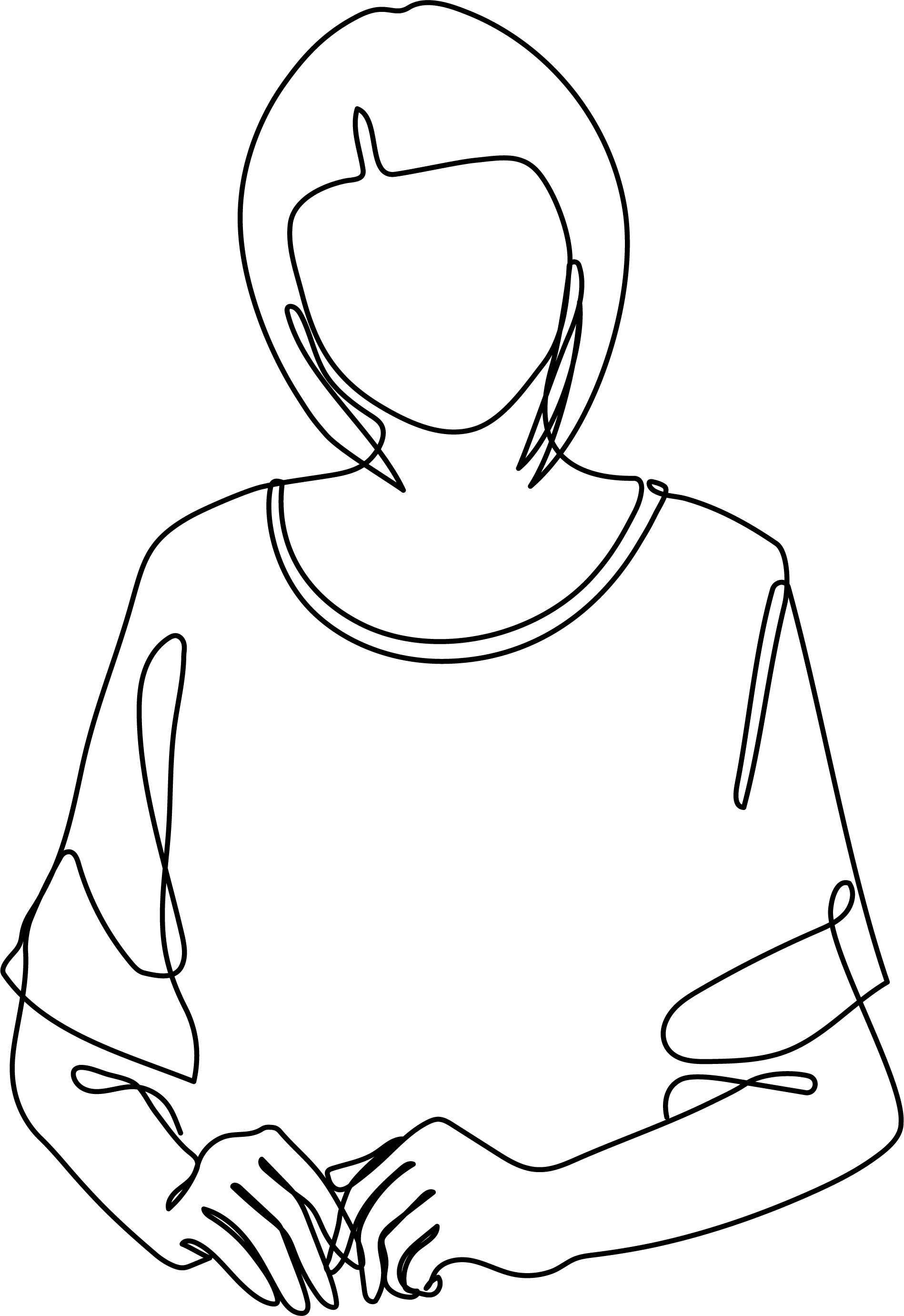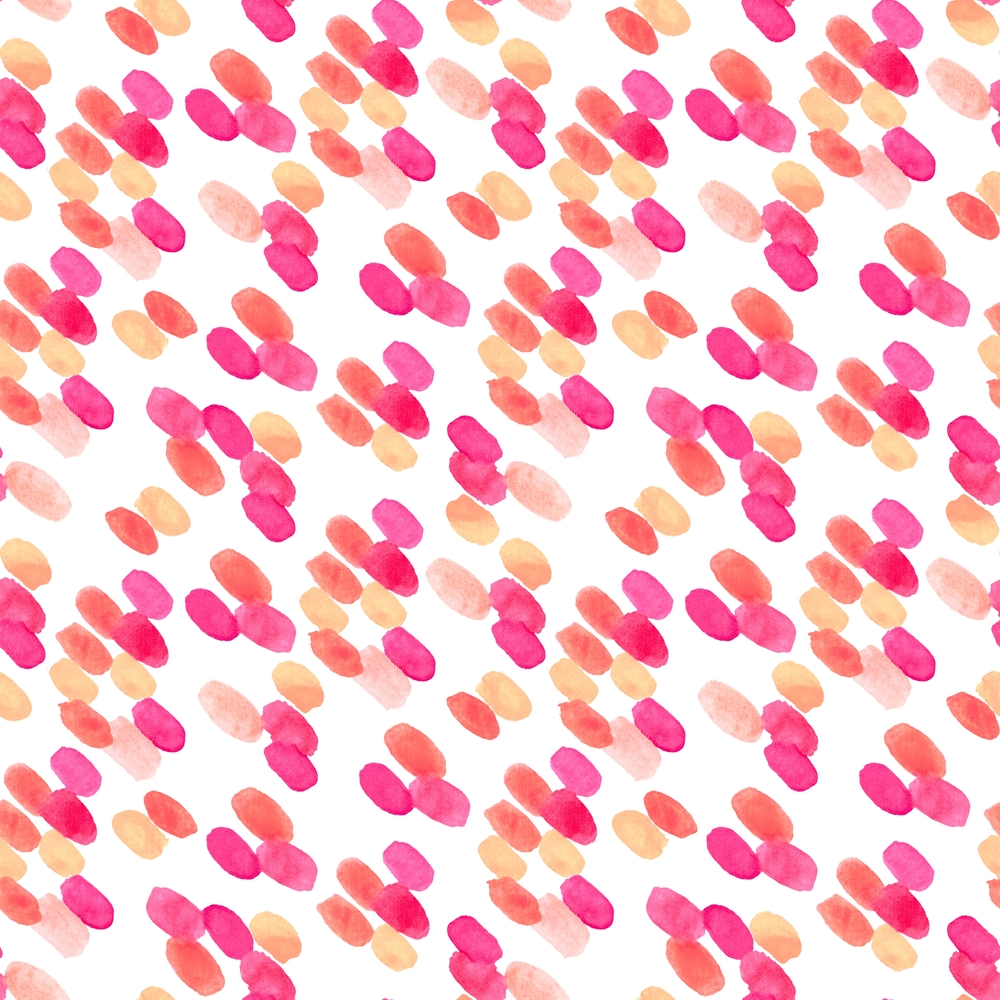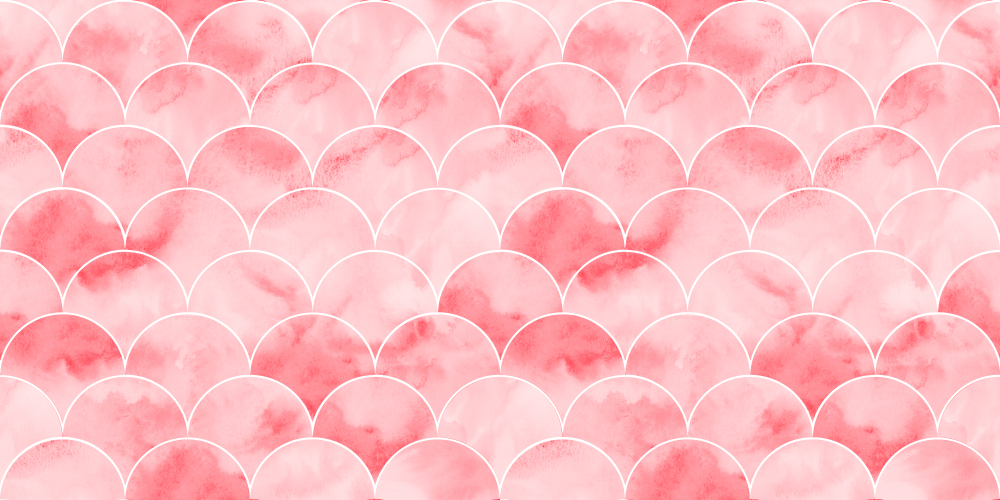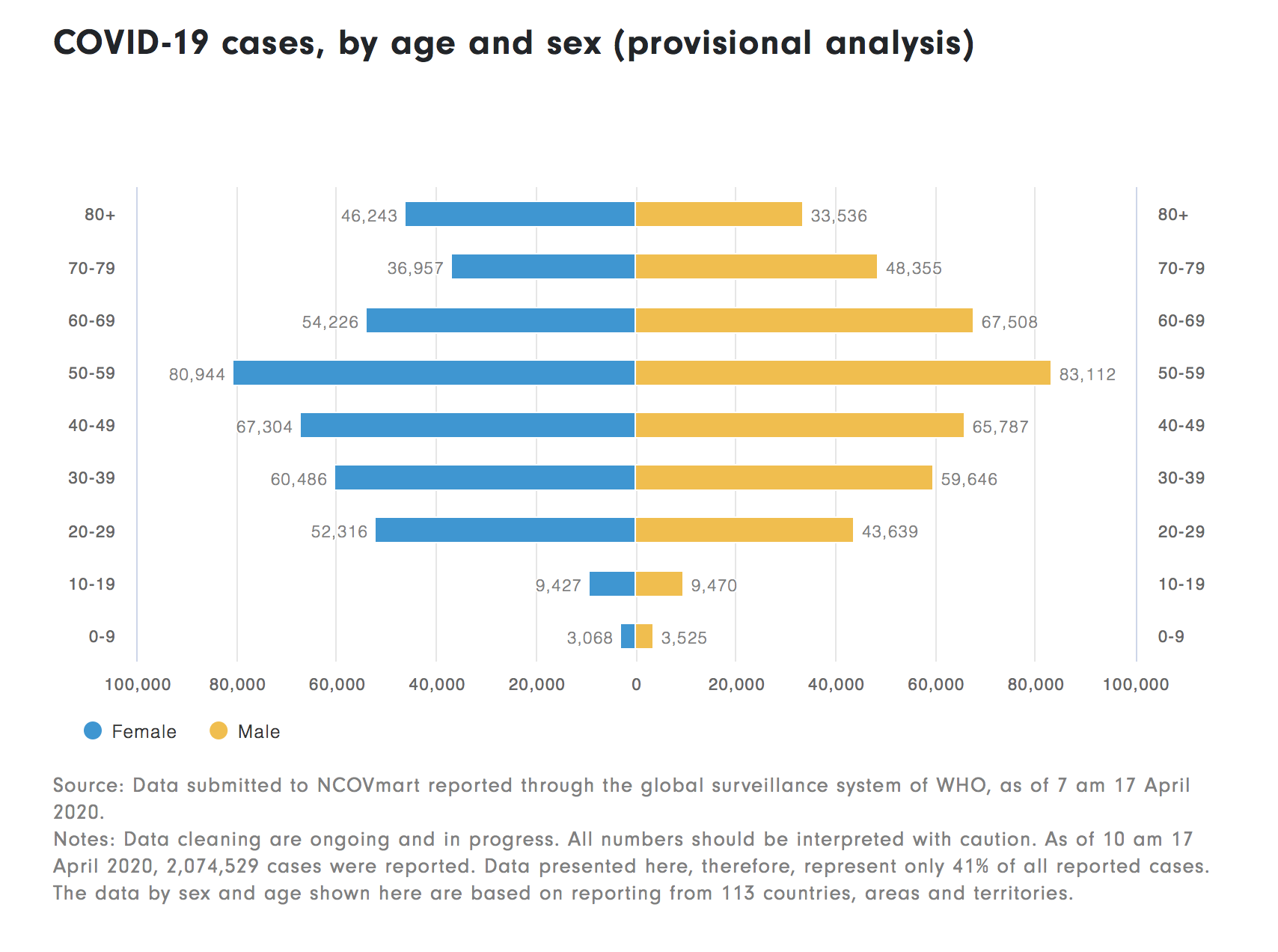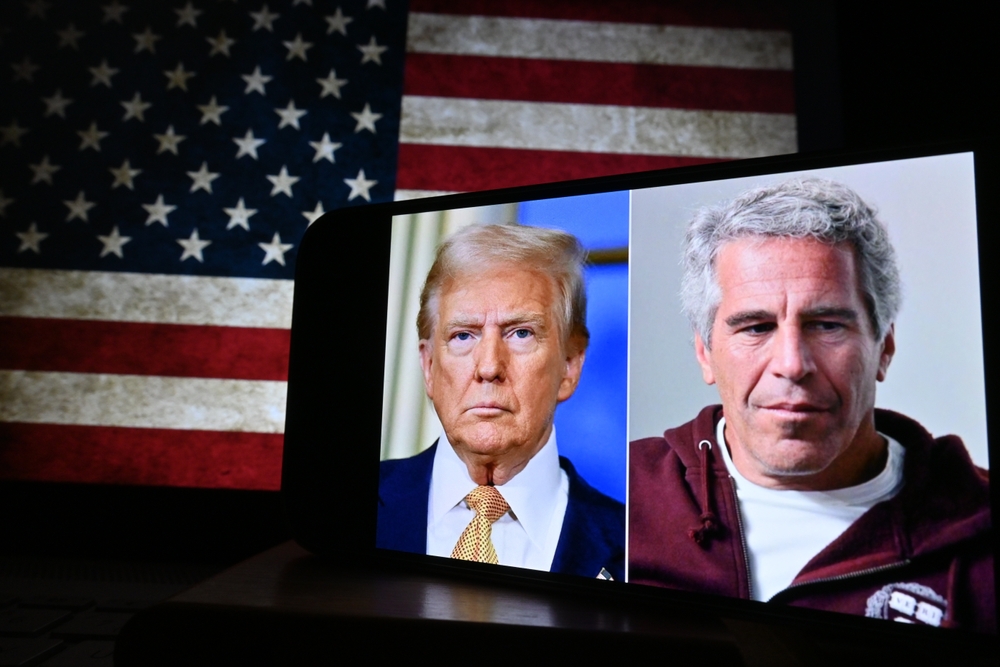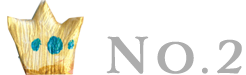中絶再考 その50 声にならない自由──日本にリプロの権利が根づかない理由 後編
2025.08.19
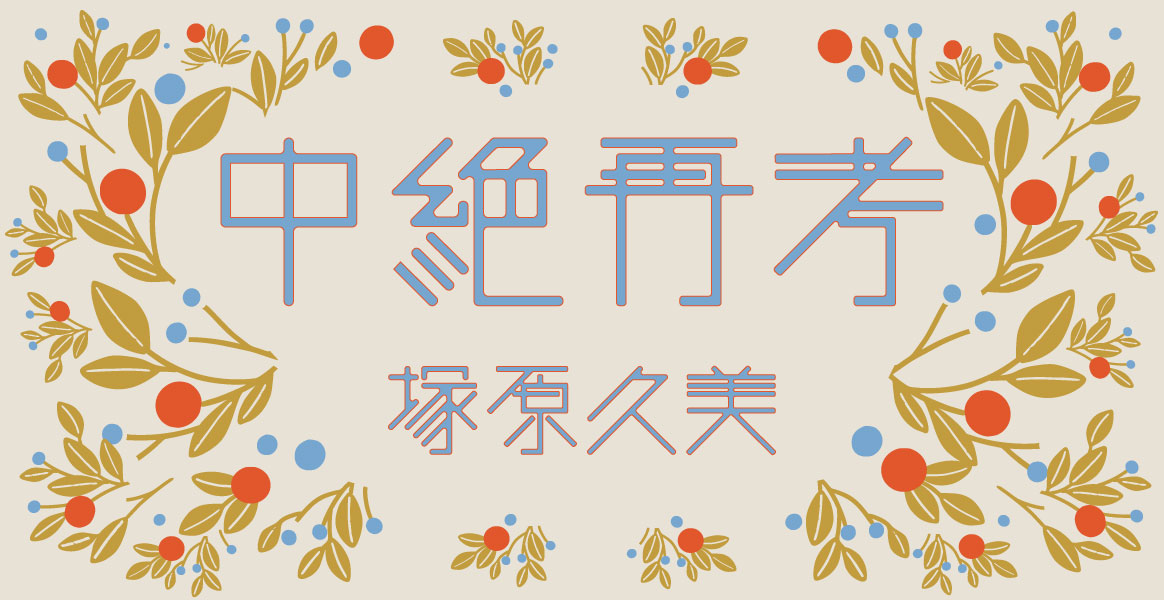
「声の届かない場所で──リプロの権利とジェンダー不平等の政治構造」
なぜ制度が変わらないのか。なぜ政治が動かないのか。
前編で述べたように、日本における中絶薬の普及率はわずか1%台にとどまり、その背景には制度的制限と政治的判断がある。しかし、話はそれだけでは終わらない。その根本には、「声が届かない構造」という問題が横たわっている。
政府も認める「期待どおりには進んでいない」現実
2025年6月、政府が発表した年次報告書は、ある意味で率直だった。男女共同参画の推進が「期待どおりには進んでいない」との認識を示したのだ。 女性国会議員の比率は依然として1割程度にとどまり、企業の管理職における女性比率も15%前後と低迷している。政府自身、「性別役割意識が社会に根強く残っている」「意識の変革が必要である」と結論づけた。
このような文言は一見、誠実な自己評価のように見える。しかし、そこには決定的に欠けている視点がある。
「なぜ変化が起きないのか」という問いである。
この問いに対する答えの一つは明白だ。そもそも、女性の声が制度設計や政治判断の中枢に届いていない。声が届かなければ、議論は始まらない。議論がなければ、制度も動かない。そしてまた、「声を上げにくい空気」だけが社会に蓄積されていく。
世界では「公共の議論に値するテーマ」として
対照的に、国際的に見ると、中絶はすでに政治的争点として活発に論じられている。
アメリカでは最高裁が憲法上の中絶の権利を否定したことを受け、各州で中絶禁止法や中絶薬の規制が急速に広がった。その一方で、それに抗う草の根運動や住民投票も活発化している。フランスでは中絶の自由を憲法に明記する改正が成立し、チリでは中絶の条件拡大を目指す法案が大統領によって提出された。
これらの国々では、中絶が「公共の議論に値するテーマ」であることが明確に認識されている。
翻って日本はどうか。中絶が選挙の争点として取り上げられることはほとんどなく、政治家の多くが語ろうとしない。メディアでもほとんど報道されず、議論は深まらない。中絶薬の承認や価格、高額負担、使用条件の厳しさといった現実的な問題でさえ、「政治に持ち込むこと」に慎重な空気がある。
なぜここまで語られないのか。
「わきまえる女」だけが歓迎される社会
2021年、当時の東京オリンピック組織委員会会長だった森喜朗氏の発言を覚えているだろうか。「女性がたくさん入っている会議は時間がかかる」「わきまえる女性でないといけない」──国内外で批判を浴びた言葉だった。
多くの人々がこの発言を「昭和の価値観」として笑い飛ばした。しかし、あの言葉が社会の奥底に潜んでいる価値観を可視化したことは間違いない。
「わきまえる女」だけが歓迎され、「自己主張する女」は煙たがられる──その構造は今も変わっていない。とくに中絶や避妊のような、身体や性に関わる話題について語る女性は、「うるさい」「政治的すぎる」といったレッテルを貼られがちである。
こうした「語りにくさ」は、職場や家庭、地域、そしてSNSなど、社会のあらゆる場面で再生産されている。
不平等を感じても「変えよう」という声にならない理由
イプソスが2022年に発表した調査「Flair Japan」は、日本社会の特殊性を浮き彫りにした。日本人の多くが「男女には本質的な役割の違いがある」と考えていることが明らかになったのだ。また、「ジェンダー平等は必要ない」「今のままでよい」とする意識も強く、他国と比べて際立って保守的な傾向がある。
つまり、こういうことだ──日本では不平等を感じていても、「変えよう」という声にはなりにくい。
この沈黙の空気が、中絶薬の話とも直結している。制度があっても、使われない。声をあげたくても、あげづらい。語ろうとする人が少なく、語らないことが「普通」になる。
「黙って従う」ことの終わり
中絶の権利とは、「妊娠を終える自由」だけではない。それは、妊娠・出産・避妊・性に関する選択について、誰にも遠慮せずに語り、決定できる自由である。
日本では、「黙って従う」ことが未だに美徳とされている。しかし、黙ることを強いられてきた人たちがいることを、私たちはもう知っている。
中絶薬の制度だけでなく、その「語りにくさ」こそが変わるべきである。しかし、語りにくいこの社会の中で、語れるようになるためには、「語ってよいのだ」という確信が、そして「語れる言葉」が必要だ。
今、私は「リプロの権利」が国際社会のなかで人権としてどれほど重要なものであるかということを、これまで日本語ではほとんど語られてこなかったことを明らかにする本を書いている。
中絶の権利は女性の人権の核である。
そのことをぜひ知ってもらいたい。今、妊娠する可能性に怯えている人に言葉を届けたい。
リプロダクティブ・ライツとは、声を持つ権利でもある。
1.1%という数字の重みを、私たちはもう一度考えなければならない。それは単なる統計ではない。無数の女性たちが、声を上げられずにいる現実の表れなのだから。
そして今、その現実を変えるための言葉を、私たちは手にしようとしている。