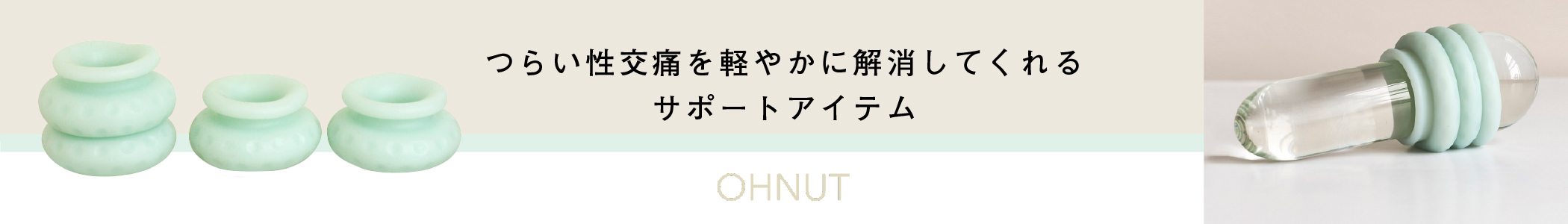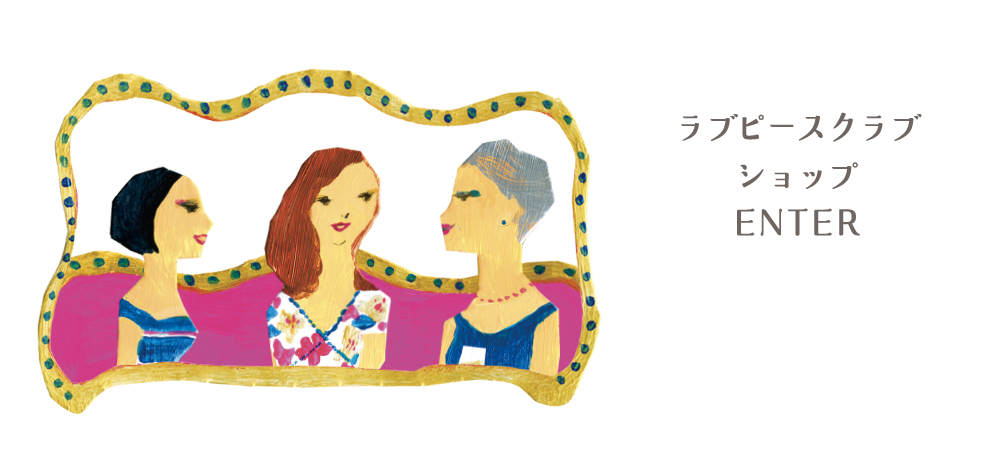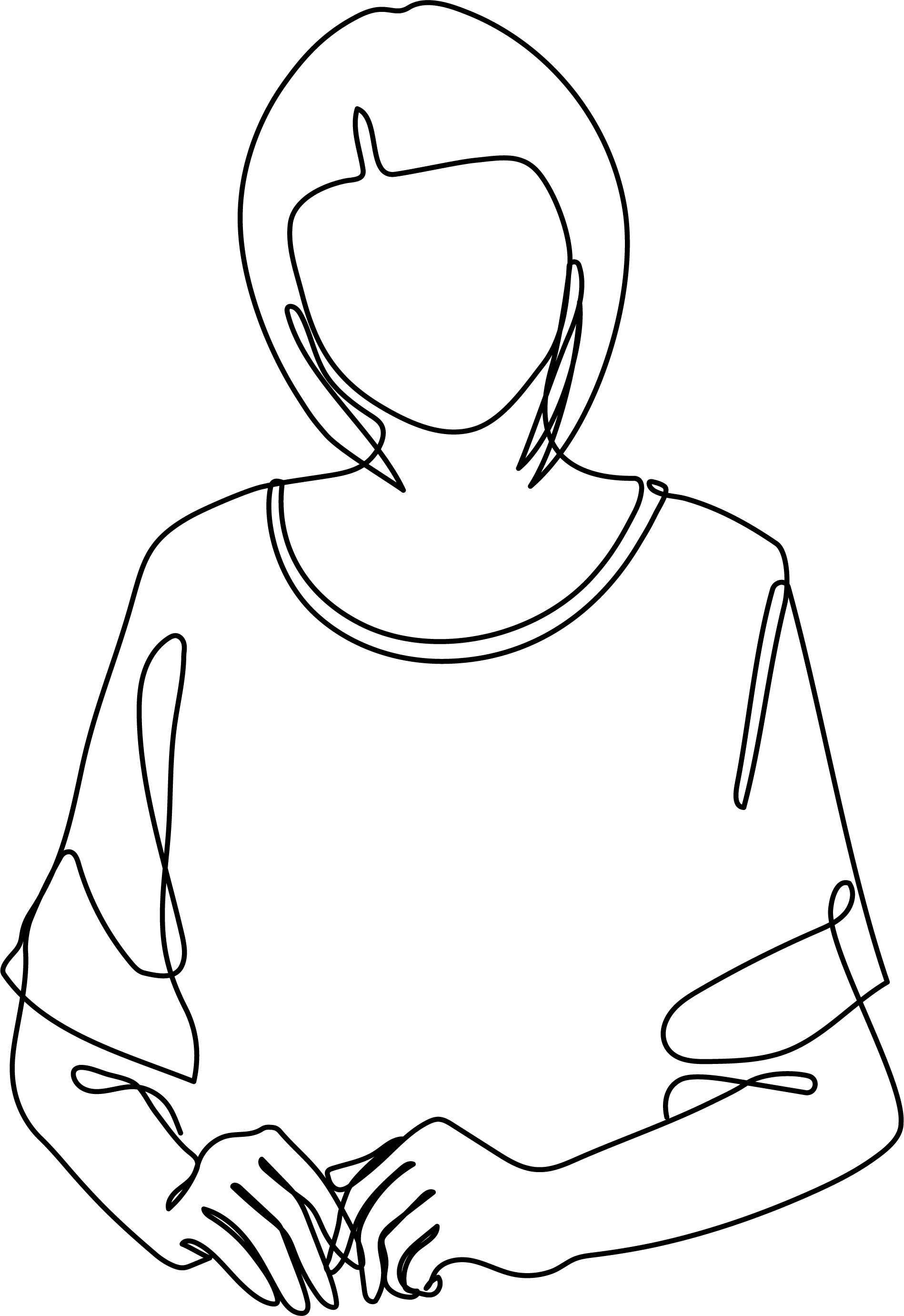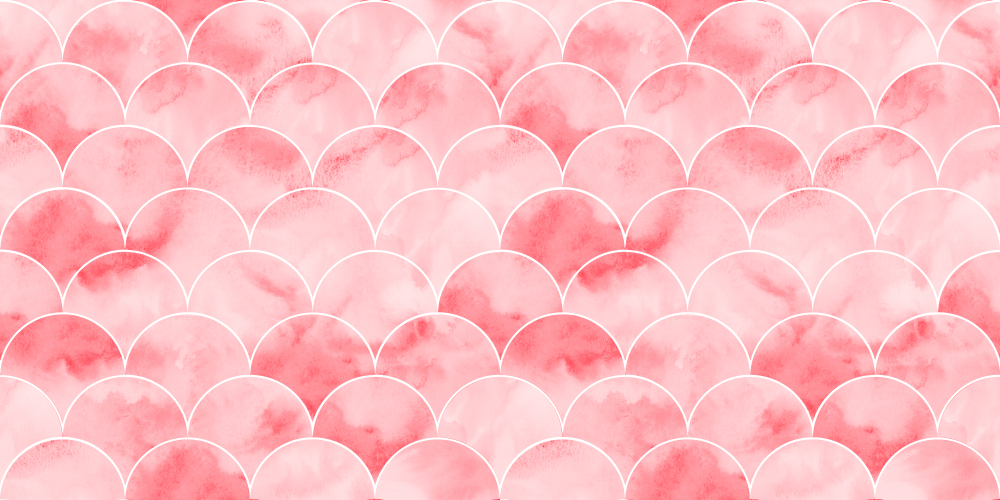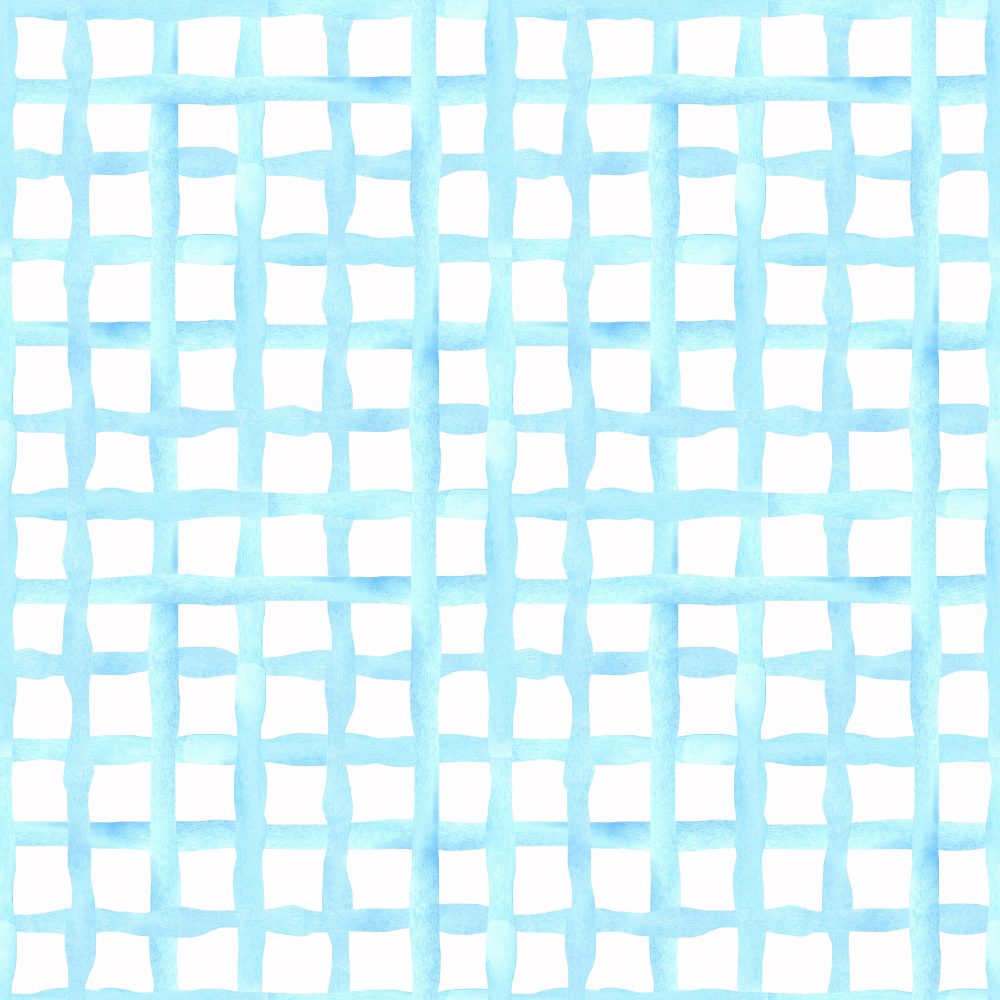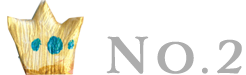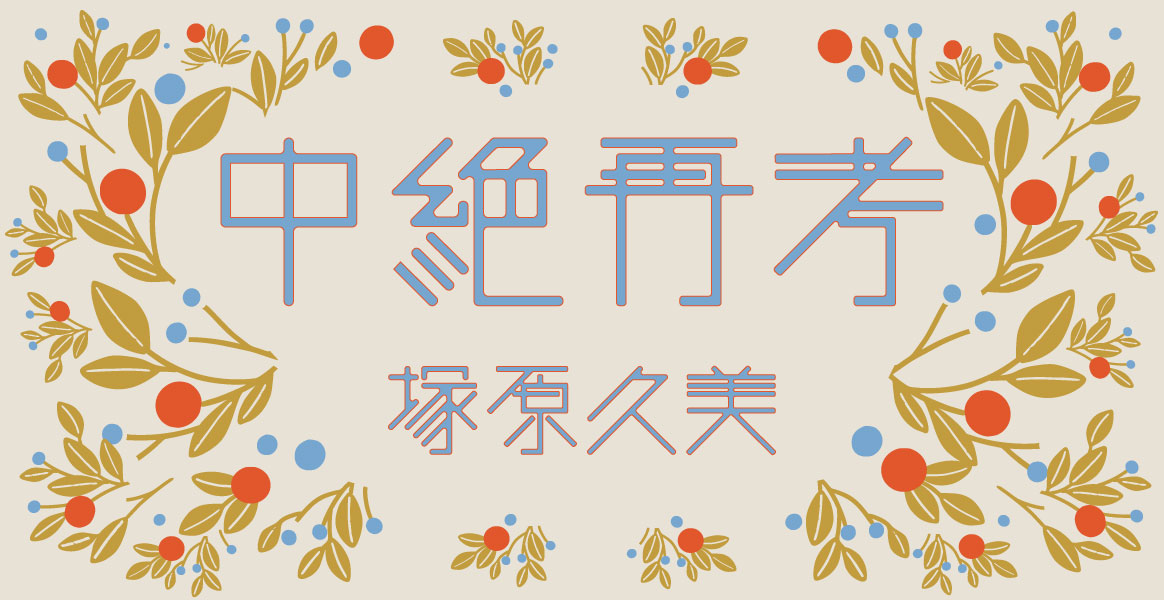
現在、アメリカで中絶薬ミフェプリストンへの執拗な攻撃がくりかえされている。科学的根拠ではなく、不安と物語という武器によって。
プロチョイスの立場を支持するガットマッハ―研究所が先ごろ発表した分析結果は明確だった。反対派が使っているのは医学ではなく、女性を信用しない文化そのものだ。
ミフェプリストンは、手術を必要とせず、診察室の支配から女性を引きはがす。つまり、女性が自分で自分の身体を扱える。
そのことこそが問題なのだ。中絶薬をめぐる攻撃は、一見、安全性の議論に思えるが、実際の争点はもっと原始的で、単純なのである。「この身体は誰のものか」である。
「自己決定権」という言葉は便利だが、日本でもアメリカでも、この言葉はときどき意味をなさなくなることがある。なぜなら、選択ができるかどうかは、身体の所有者が誰であるかによって決まるからだ。
身体を自分のものと認めない社会では、「自己決定」はただの形式にすぎない。選択肢を並べているだけで、選ぶ権利は最初から当人に手渡されていない。
だから、反中絶の人々は「胎児」や「道徳」や「家族」や「愛」など、あらゆる概念を用いて、身体の所有権を女性の手から奪おうとする。
だから、私たちが最終的に言いたいことは常に同じだ。「わたしの身体はあなたのものではない」。
日本でも、中絶薬はすでに承認されたのに、一人で飲むことすら「認めない」という方向に政策が傾き続けている。その理由もまた単純だ。規制派にとって「女性が一人で決められるという事実」自体が許しがたいことだからだ。だから、彼らは監視、管理、同意書、診察、指導…に突き進む。それらは医療ではなく、所有の証明として配置されている。
「あなたは自分の身体を、自分だけで扱うことはできません」と言うために。
ここで「自己決定権」を使うと、論点がぼやける。言うべきことはもっと短くていい。
「身体は私のもの。だから、選ぶのは私だ。」
それだけの話が、なぜこんなにも争われるのかというと、社会はまだ、女性が自分の身体を所有している世界を受け入れていないからだ。
中絶薬が攻撃されるのは、ミフェプリストンという薬が危険だからではない。女性が自分の身体を持ち歩く未来を想定できない人々がいるからだ。
中絶をめぐる議論は「権利の獲得」ではない。本来有しているのに奪われているものを「取り戻す」だけなのである。争われているのは「身体所有権」だ。
誰の所有物として生きるのか。それだけのことが、今も政治で揉まれ続けている。