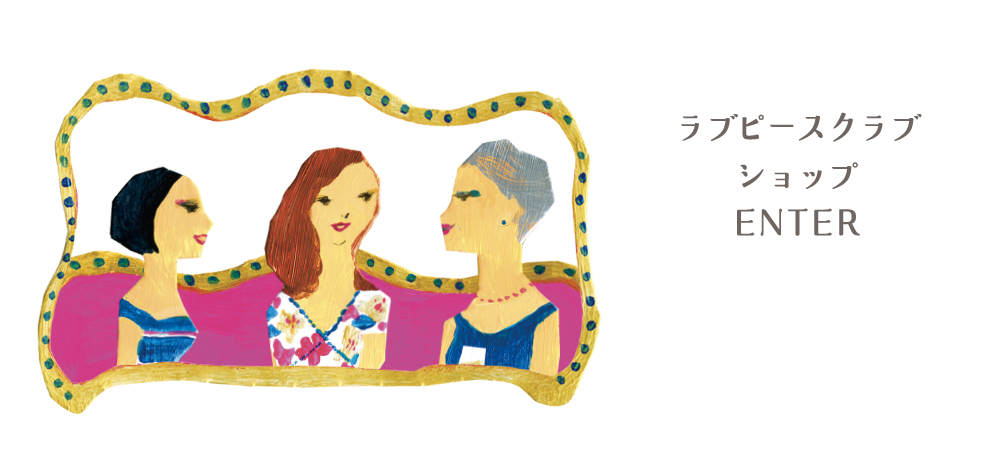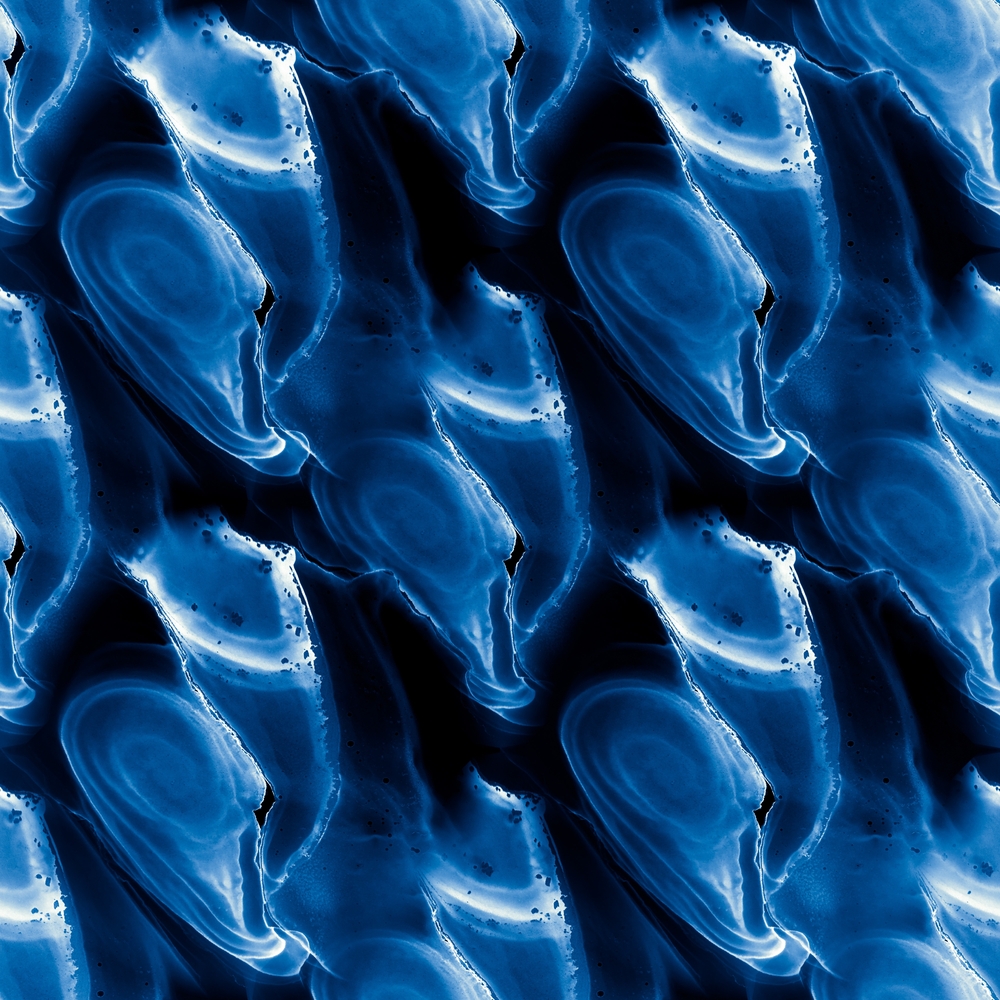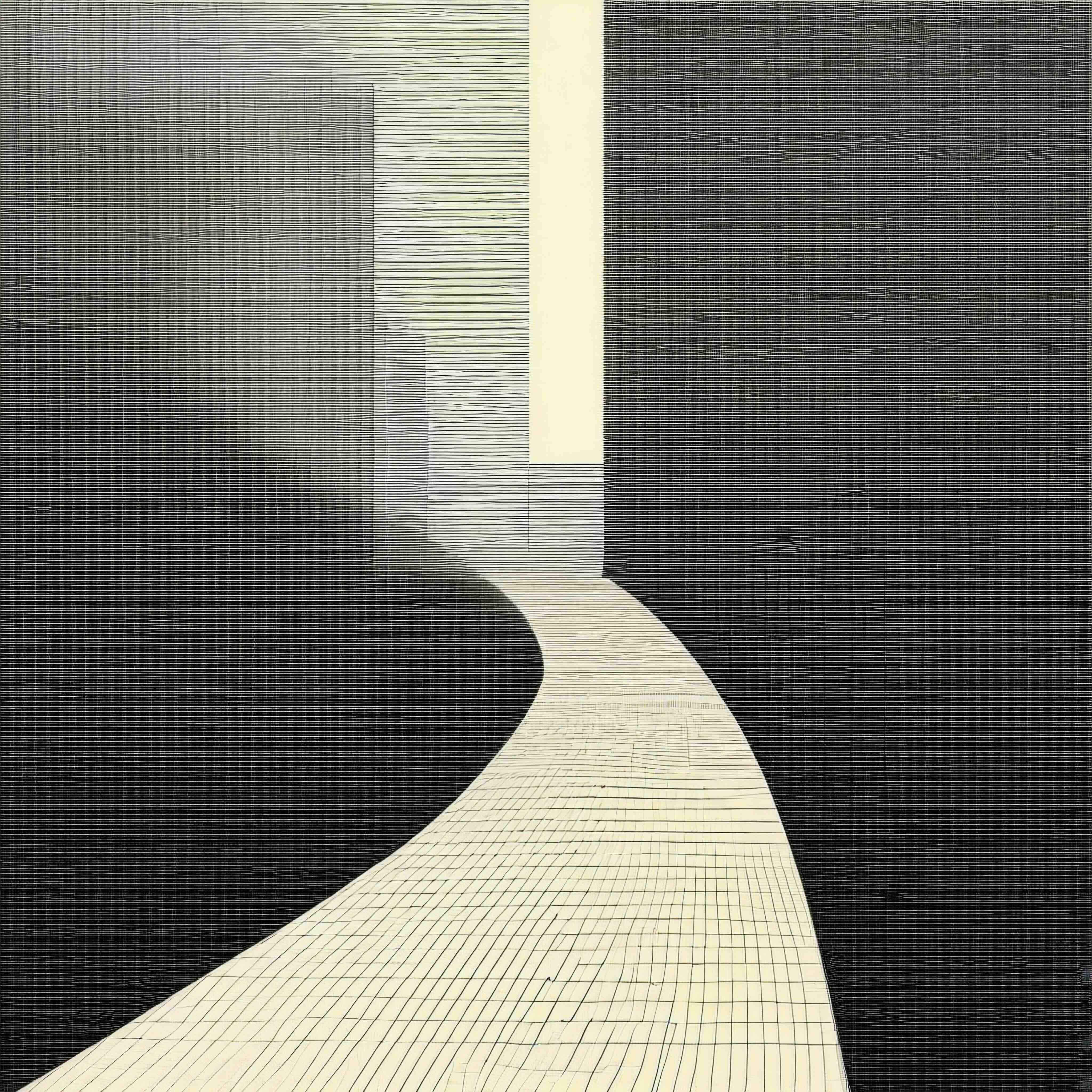「お客さんからこういうことされるけど、笑顔でうまくかわしてね」
中央線の駅からほど近いレンガ造りのスナックで、面接担当の男はわたしの手首を掴んで自分のペニスを触らせながらそう言った。
力いっぱい抵抗したが、男の力は驚くほど強く、開店前でうす暗いスナックの店内はよそよそしく、おまけにわたしは無知で非力だった。
それ以上のことが起きなかったのは、もはや奇跡でしかない。
逃げるように店から出て足早に駅に向かいながら、それでもわたしは、自分が性暴力の被害に遭ったのだとは考えられなかった。
当時のわたしにとって、その時のことは「ちょっと怖い目に遭っただけ」でしかなかった。
ボーっとしていてドブにはまりかけたとか、
料理中にうっかり指を切ってしまったとか、
夜道で向かいから歩いてきた男が、すれ違いざまにいきなり大声を上げたとか、
ナンパを無視して通り過ぎようとしたら、バッグを蹴られたとか、
小学生の頃、叔父から冗談まじりに殴るまねをされたとか、
そういうもの。
そういう類の、記録するまでもないちょっとしたトラブル。ハプニング。
だって、人生にはそういったことがまま起こるじゃないか。
そんなものは、ちょっとした怖い目でしかない。少なくとも、わたしのようなブスで貧乏で取り柄のない女にとって、それらは被害なんかではない。
よしんば被害だったとしても、その原因はきっとわたしにあったのだろう。
油断していたから、
従順でなかったから、
にっこり優しく微笑まなかったから、
誰かにとって魅力的な女でなかったから。
当時のわたしは、そう考えるようにしつけられていた。
そしてそのしつけは、おそらくいたって標準的なもので、程度は違えど当時の(そして今の)女性の多くが、身につけさせられているものだろう。
当時のわたしは、経済的にも心理的にも疲弊しきっていた。
その数年前に就職した会社を退職し、さらに諸事情あって消費者金融から数十万円を借りており、とにかくお金がなかったのだ。
お金の問題を解決するためには、働いて稼ぐ以外ないと思っていた。
そして、もっとも効率的に稼ぐことができるのは、アルバイトをかけもちしたり再就職をしたりすることではなく、男への性接待であるらしいと知ったところだった。
逼迫した状況で受けたスナックの面接がうまくいかず、わたしはとても落ち込んでいた。
どうしてもっと要領よく立ち回れなかったのだろうと、自分を責めた。
「ああいう怖い目をうまく回避していかないと、水商売では働けないんだな」
という、新たな知見を得たとさえ感じていた。
客の反感を買わずにあの状況を回避するなんて、わたしにできるだろうか?
そんな高等な接客、わたしにはとても無理だ。
だって、わたしはそんなに賢くないし、魅力的でもない。
ブスが調子に乗ってお高くとまっていると思われたら、恥ずかしいじゃないか。
でも、お金はすぐにでも必要だ。
どうしよう。
どうしたらいいんだろう?
そして、
「いいや。こうなったら、もうはじめからおとなしく触ってしまおう」
そう考えたのだ。
はじめから客の身体に触り、自分の身体も触らせてしまえば、きっと怖い目には遭わないだろう。それくらい腹を決めていれば、多少のことが起きても我慢できるだろう。
スナックでの怖い目から逃げのびてほどなく、わたしはデリバリーヘルスのアルバイトを始める。
2006年の暮れのことだった。
それ以来およそ14年間、わたしは性売買の現場で怖い目に遭い続けた。
わたしはうんと若い頃から、自分は社会的に無価値な女なのだと思っていた。
履歴書に書けるような学歴もスキルも何も持っていなかったし、顔も可愛くない。
女の社会的な価値とはすなわち、性的魅力があり、仕事ができて、多少のことには動じない、優しくて賢いということなのだと、わたしは思っていた。
でも、自分が持っているのは、若さと体力と、なんでもやってしまえという投げやりな前向きさだけだった。
だから、怖い目に遭うのも、痛い目を見るのも、ひとから面と向かって侮辱されるのも、きっと仕方がないのだ。
そういう価値観の中で育てられ、それらを強く内面化して生きてきた。
我慢しよう。
だってなにも持っていないのだから。
なにも持っていない女が我慢するのは当然なのだから。
いっとき息を止めて、汚物の漂う海に潜り、ギリギリまで我慢して浮上する。
そうすればお金が手に入る。
お金さえあれば、借金の返済について不安にならずにすむし、家賃も電気代も払える。
好きな本も、食べ物も、新しい服もなんだって手に入る。
好きなことに没頭することだってできる。
そのうえ綺麗に着飾って、他人に感謝され、客に可愛い可愛いと褒められながら稼げるなんて、こんな得な仕事はない。
そのためなら、裸で汚物を浴びるくらい我慢してもいいやと思ったのだ。
お金に困っていることを誰かに相談しようなどとは、考えたこともなかった。
お金がなくて困っているなんて、一体どうして誰に相談できようか。
そんな、みっともなくて恥ずかしいこと。
どうしてもお金が必要だった時、実家の親に、たった一言「助けてください」と言うことができていたら、その後のすべては違っていたかもしれない。
でも、わたしは親や学校や職場というこの社会から、教えられていたのだ。
「はじめからひとに頼らず、自分でなんとかしなさい」
だから自分でなんとかすることにしたのだ。
誰かに怒られるのは嫌だった。
助けを求めて迷惑がられるのは耐えられなかった。
助力を得られなかった徒労や虚しさなど感じたくなかった。
それらは、想像するだけで鳥肌が立つような、みじめで恐ろしいことだった。
そして何より、自分ひとりでもどうにかできると信じていた。
たとえ無学でも人付き合いが苦手でも、頑張れば(なにをどう頑張るにせよ)ひとりで生きていけるに違いない。そう信じていた。
そう信じなければ、学歴も金も知恵もない女がひとり、東京で生きていけやしなかった。
あの頃のわたしは知らなかったのだ。
ひとが簡単に社会から滑り落ちてしまえるということを。
そして一度滑り落ちてしまえば、目の前にそびえ立つ崖を登るのが容易ではないということを。
ともかく、わたしは肉体と時間という数少ない自らの資産で、考え得る最も効率的かつ実効的な方法を検討し、その手段を見つけ出し、実行した。
そしてそうしたことによって誰にも何も相談できなくなり、崖下から抜け出せなくなってしまったのだ。
性売買で怖い目に遭っても、それはすべてわたしの責任だ。
だってそうじゃないか。
わたしよりずっと大変な状況でも、性売買を選ばずにすんだひとはいるのだから。
その考えは常にわたしの活力の源となり、同時にわたしを蝕んだ。
誰かにたよって迷惑をかける必要もないし、生活も安定した。
そしてその生活を維持するために、わたしは自ら進んで金のために体を売り続けた。
自分の意志と責任において、わたしは自分を殺し、深い後悔のふちに佇み続けた。
一体、何から語るべきだろう?
より多くの男に買ってもらうために覚えた化粧のこと。
どんな手順で服を脱げば男から喜ばれるか研究したこと。
出勤している間は、まるで幼児のように自分のことを源氏名で呼ぶようにしていたこと。
くり返し触られることで乾燥し、擦り切れた外陰部の激痛のこと。
盗撮されたこと。
無理やり性器を挿入されたこと。
腐ったドブのようだった客の口臭と、それを我慢しながらしたキスのこと。
禁止行為はできないと断って「死ね」と言われたこと。
もっとたくさん稼げることを願って、店を転々としたこと。
出稼ぎをしたこと。
面と向かって値切られたこと。
何度も何度もクラミジアに罹ったこと。
「痛い」という訴えを嘘だと決めつけられたこと。
それでも性売買を辞めることができなかった、あの行き止まりの日々のこと。
「言いたくないことは、言わなくていいんだよ」
後年出会った友人は、わたしにそう言ってくれた。
誰にだって声を上げる権利があり、同時に沈黙する権利がある。語ることで苦しくなるようなことは、語らなくてもいいのだと、そのひとは言ってくれた。
わたしは、
わたしはでも、語ることにした。
わたしに起きたこと。
わたしが、自分で選択したのだ、自業自得の自己責任なのだと信じて黙ってきたことを。
社会という無数の個人が共有する幻想の中で、選ばされてきたことを。
わたしは黙らない。
自分の中の無念も怒りも憎悪も、隠さない。
わたしはわたしを買い、わたしを売り、わたしの粘膜に射精してきた多くの男達を憎む。
殺してやりたいとさえ思う。
みんな、苦しみぬいて死ねと思う。
「でも、そのお客さんが払ってくれたお金のおかげで生活できたんでしょ?」
そうだ。
わたしは、わたしの体と尊厳を踏みつけてきた男が払った金のおかげで生き永らえた。
わたしに梅毒やHPVや性病や虫歯や結膜炎や疥癬を感染させ、わたしの膣に爪を突き立て、わたしの本名をしつこく聞き出そうとし、わたしをレイプしながら「好きだと言え」とくり返す男がよこした金があったから、今日もまだわたしは生きている。
わたしが受けた苦痛は女が男から千円札数枚をもらうためには当然の代償である、そう信じて疑わない社会を告発するために、わたしは黙らないのだ。
一日も早く、男が女を金で買うのは当然だという社会が、滅びますように。