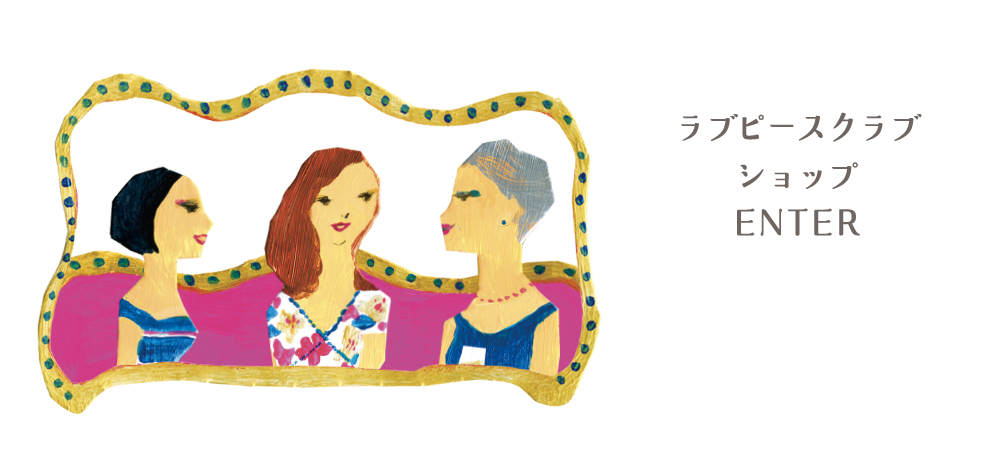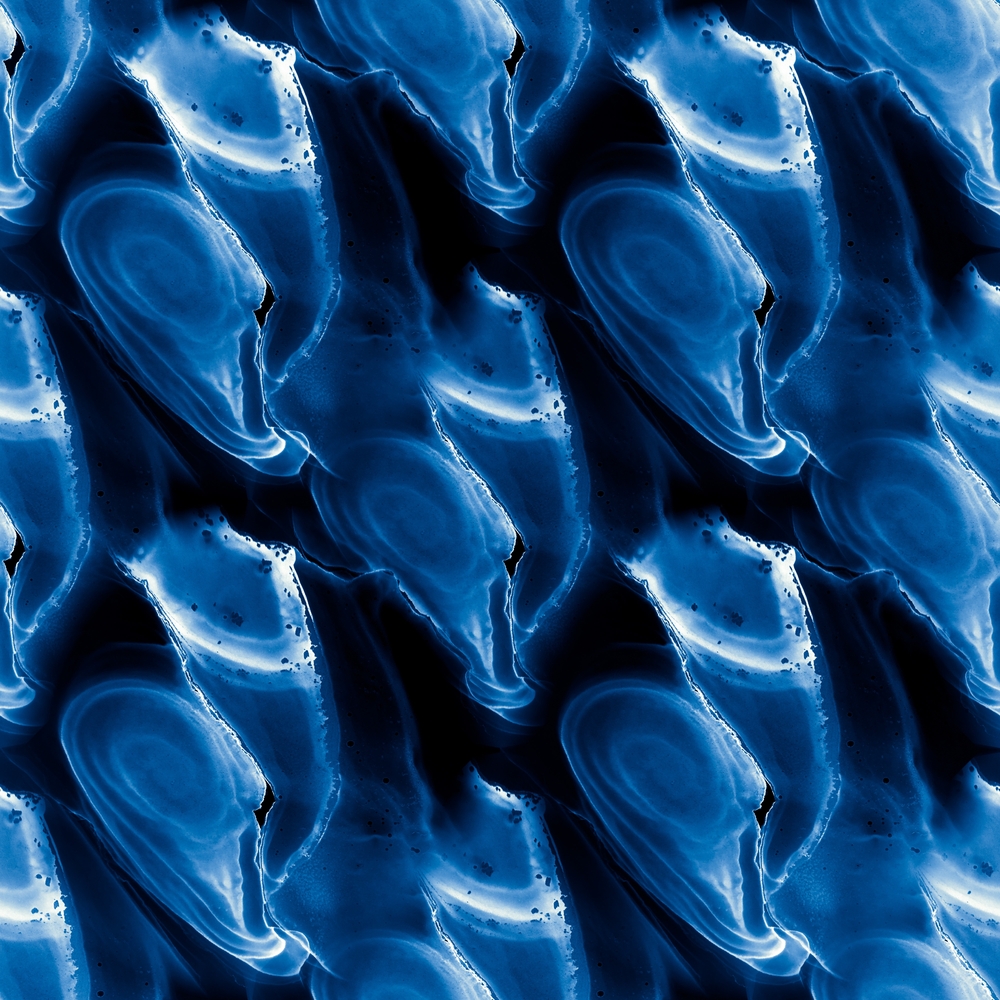日本には下着泥棒が昔から当たり前のように存在してきた。私自身もアパートの1階住まいだったときに、普段は室内に干している下着を、天気がいいからと一瞬だけ外に出したところ、見事に盗られた経験がある。なお、被害届は出していないので犯罪件数にはカウントされていない。同じ犯人に他の人も盗まれているだろうし、おそらく表沙汰になっていない下着泥棒被害の数は少なくないだろう。しかし、この日本ではありふれている下着泥棒というものは欧米にはいないらしいと聞く。
ヨーロッパをバックパックで1ヶ月ちょっと旅行した時に、2泊ほど学生寮住まいの友人に泊めてもらったことがある。その日、彼がちょうど洗濯をするからと、私の洗濯物も一緒に洗ってくれると言う。冬だったので、バックパッカー的には下着と靴下さえ替えていればOKの手洗い生活だったものの、洗濯機で洗えるのは素直に嬉しいのでお願いした。友人は私の洗濯物(主に下着)も一緒に全部洗濯機にかけ、寮の干し場で乾かしてから回収してきてくれた。その時に私の下着を完全に「ただの布」として扱ってくれていたので、頼んだこちらとしても変に照れたりする必要がなく非常に助かったのを覚えている。
その後、別の友人のところに一週間ほど厄介になった時には、一緒に洗濯室についていってマシンの使い方なども教えてもらった。かなり人数の多い大きな学生寮のわりには、洗濯機と乾燥機の数が充分ではないため、自分の洗濯物が仕上がる時間にその場にいないと、順番待ちしている学生に勝手に中身を取り出されて洗濯機の上に放置されることになる。みんな、それなりに時間をやりくりして洗濯に来ているので、終わった洗濯物の持ち主がやってくるのを待っている暇はないということらしい。しかも、かなり乱暴に取り出されて靴下が片方地面に落ちていたことも、取り出し忘れられたものがそのまま他人の洗濯物と一緒にもう一度グルグル回っていたこともある。
そこでも、下着は「ただの布」であって「性的」なものとしては扱われていないことが感じられた。各国の警察の資料などに当たったわけではないので断言はできないが、こうした経験から考えても、「欧米には下着泥棒はいない」にはそれなりの信憑性があるように思う。もし、下着泥棒がいるなら、女子学生はもう少し警戒して洗濯機を見張るだろうし、共同の洗濯物干し場に下着を干したままで自室に戻ったりはしないだろう。
00年代末頃、ヨーロッパ人と一緒に観た日本のインディーズ映画の中で、部活の合宿中に男子が好きな女子のブラジャーを盗んで匂いをかぐという、ある種のギャグシーンがあった。みんな大爆笑していたのだが、最近になって、その爆笑のニュアンスは日本人である我々と欧米の彼らでは別物だったのではないかと思うようになった。私は下着を盗んで匂いをかぐ必死さと通行人から話しかけられて慌てる様子を滑稽なものとして笑っていたのだが、ヨーロッパ人たちはあれを「意味不明なことをする描写」として面白がったのではないか、と。そして、日本社会で生きる女性は、下着を盗まれるということの気持ち悪さに対してある程度鈍感にならざるを得ないのかもしれないとも思う。
下着を盗まれた当時、私は「もう下着は外に出さないようにしよう」と心に誓った程度で、あまり深く考えないようにした。盗んだ奴が何を考えたか、その下着をどうしたのか。また、その下着を着けている女がここに住んでいるのだと知られてしまったことの気持ち悪さについても考えようとしなかった。世間知らずだったというか、呑気だったというか、防犯意識が低すぎて我ながら感心してしまうが、下着を盗まれることはそんなに珍しいことでもなかったし、気持ち悪いから考えたくなかったのだと思う。
まだネットが普及するずっと以前からブルセラ屋が存在し、使用済みの下着や体操着などが取引されていたし、コロナ禍を経た現在、女性の使用済みマスクもネットで売買されているらしい。下着にしてもマスクにしても体操着にしても、本来はただの布に過ぎないものではあるものの、わざわざそれを盗んだり、金を払ったりしてまで手に入れたいという男性がいること。それは、女性の側がどう認識していようと、使用済みの下着を「性的なアイテム」として消費する男性が存在しているということだ。
下着を盗まれたこと、それが財布や金目のものを盗られたのとは別の気持ち悪さを伴う理由もそこにある。実際に自分の手元から消えたものは下着一枚であっても、感覚的にはもう少し身体的な被害として経験される。自分が誰かの脳内で単なる「性的な物体」として想像され、弄ばれているような感覚とでも言えば伝わるだろうか。大げさに聞こえるかもしれないが、それは尊厳を傷つけられる感覚だ。
しかし、こうした被害者の感情さえ、男性たちによって「エロ」として消費される可能性もある。日本社会に流通する「エロ」表現の多くが女性を虐待したり辱めたりする加害性と強く結びつき、それが男性の性欲と不可分になっているからだ。そして、それが成立するのは、女性を全人的にではなく、単なる性的な身体パーツとして認識することが、男性たちの間で当たり前になっているからだろう。だからこそ、私たち女性は「人間」であると声を大にして訴え続ける必要があるのだ。


マーガレット・アトウッド『ペネロピアド 女たちのオデュッセイア』
鴻巣友季子訳
角川文庫
2025年
今世紀に入って、古典作品の「女性視点での語り直し」ものが注目されているらしい。今年になって邦訳が文庫化されて手に入りやすくなった『ペネロピアド』は、ホメロスの『オデュッセイア』をオデュッセウスの妻ペネロペイア(と十二人の侍女たち)の視点で語り直した小説だ。
『オデュッセイア』では、ペネロペイアは美しいだけでなく賢い女性であることが示されつつも、物語においては比較的受動的な存在になってしまっている。一方、『ペネロピアド』でペネロペイアによって語られるのは、それとは別の物語だ。ペネロペイアの生い立ちや現代社会に対するコメントなどの『オデュッセイア』には登場しないエピソードもあるが、オデュッセウスを待つ20年の間、彼女が自分で情報を集め、状況を把握し、それに対処すべく準備をしていたことも描かれる。
「異国の地で果てた夫オデュッセウスを思って涙にくれる貞節な妻」としてのペネロペイアではなく、女であることで軽んじられ、口を塞がれ、行動に制約を科されながらも闘うヒロインとしての能動的なペネロペイア像が立ち上がってくる。しかし、そのペネロペイアの語りも、合間に挟まる「十二人の侍女たちのコーラス」によって、オデュッセウスの語る作り話のように真偽の怪しいものに見えてくるところがまた面白い。