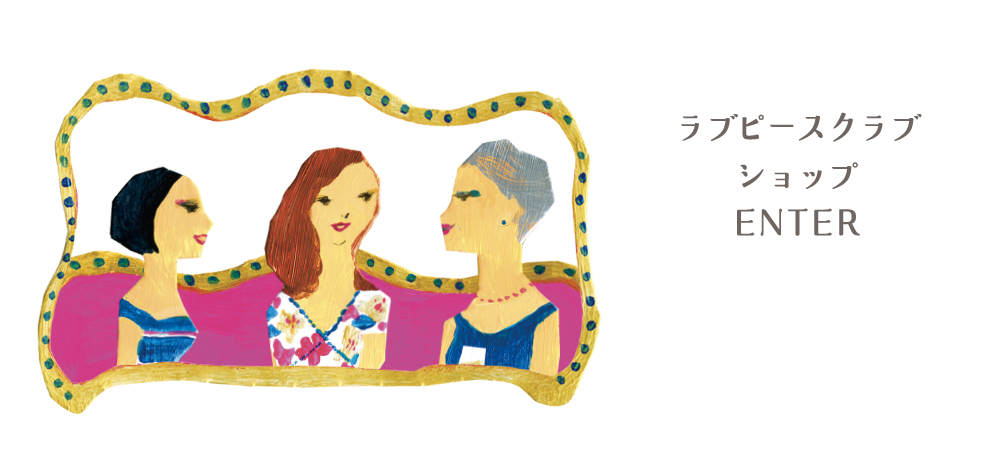前回も書いた通り、私は他大の授業に潜り込む形で大学におけるジェンダー・スタディーズの授業を受ける機会を得た。そこで、ジュディス・バトラーによる思考の転換の新しさに感動し、イブ・セジウィックのホモソーシャル分析の鮮やかさに感嘆した。新しい知識を得ることの楽しさもあって、私はどんどんジェンダー論にハマっていった。
しかし、当時の大学においては、まだ「現実に男女の身体差はない」とまでは言われていなかった。レズビアンやゲイという言葉は、「自分と同じ身体的性別に惹かれる人」を指す単語として共有されていたし、授業に何度かゲストスピーカーが来てくれることもあったが、どの人も生物学的性差そのものを「ないもの」として扱う話はしていなかった。おそらく、私だけでなく、授業に参加していた学生のほとんどは、バトラーの「セックスもまたジェンダーである」を、「身体的性差の完全否定」としてではなく、「社会的性差の強化の恣意性」を表現したものだと理解していたと思う。結果としては、この理解は間違いだったということになるらしい。
2018年の冬頃、SNSにおいては「生物学的女性」、「生得的女性」、「身体女性」、「女体持ち」など、以前であれば単純に「女性」と表現されたカテゴリの人々を指すために様々な表現がなされるようになっていた。中には、「女性」には「トランス女性」を含む場合もあるという前提を共有しているからこそ、「トランス男性」を含む身体の性別を表す表現として、こうした言葉を用いていたひとも少なくはなかった。私もそのひとりだ。それにもかかわらず、「身体的な性差に言及するのがすでに差別である」と言われ、「差別主義者」「トランスヘイター」というレッテルを貼られるようになっていった。
最近になって、しれっと「そんなことを差別扱いしてる人はいない」「生物学的性差があるのは自明のこと」と軌道修正している人たちも目に付くようになった。重度の物忘れなのか、単なる無責任なのか、判断に迷うところだ。SNSでの議論は、自分の作ったタイムラインを中心にしか観測できないので、すべての発言を拾うことは不可能だ。人によっては、「トランスヘイター」とされた女性たちが苛烈なバッシングを受けていた状況を知らなかった、という可能性もゼロとは言えない。
しかし、フェミニズムを中心にSNSでこまめに発信している著名人や学者のほとんどが、「生物学的性差に言及するのは差別」という言説に賛同していたし、(かのJ.K.ローリングを含め)「身体的性差はある」と述べた人たちが、SNS上のみならず、リベラルな媒体でも繰り返し「差別者」として名指しされてもいた。そういった経緯を全く知らないままで、「トランス差別が吹き荒れている」と長いあいだ認識していたなら、それはなぜなのか教えてほしい。
2025年夏の参院選の期間に、参政党による「発達障害なんてものはない」発言がおおいに批判されていたのを覚えているだろうか。その発言の何に問題があるのかというと、「現実にあるものをないと言ったこと」ではないのか? 言葉の上で「ない」ことにしてしまえば、議論を放棄することも考えることをやめてしまうこともできるだろう。しかし、現実に「ある」という事実は覆らないし、発達障害当事者の抱える困難はなくならない。
まだ、今ほどは発達障害というものが認知されていなかった頃、バイト仲間のひとりが「他人とうまくコミュニケーションできない」と悩んでいた。バイトのメンバーの間で「ちょっと変わった奴」と見なされていた彼は、自分の苦手を克服しようと接客系のバイトを選んだそうで、その後、色々と調べて「自分はおそらく発達障害を持っている」と気づいたそうだ。そのことを彼が私に話してくれたのは2005年くらいだったと思う。当時はまだ聞きなれない言葉だったが、その後、発達障害は世間一般に認知されるようになって、(まだ不十分とはいえ)早い段階から支援を受けることもできるようになった。それは、発達障害というものが「ある」ことが認知されたからこそだ。
身体的性差にも同じことが言えるのではないか。現実に存在している性差をないことにしても、女性身体で生きることの困難は消えてなくなりはしない。むしろ、身体的な性差によって引き起こされている問題に対処するためには、今以上にデータを集めて分析する必要があることが、性差医療の専門家によっても指摘されている。日常生活における問題にしても、身体の内部で起っている問題にしても、健常者の男性(西洋発の科学の場合は特に白人男性)を基準とする物差しでは測れないことがあるのだ。
女性差別を正当化する根拠に「身体的な性差」が挙げられることが多いからか、リベラルな人たちはその根拠の方に疑いを向ける傾向がある。実際、リベラル側の「身体的性差があるというなら、女性差別は仕方がないということになってしまう」といった内容の発言を目にしたことは何度もある。しかし、間違っているのは「身体に違いがあること」ではなく、「身体に違いがあることを根拠に女性を差別すること」であって、生物学的な性差を否定する必要はないし、むしろ身体に差がないというなら「男並み」になれる女性以外は「自己責任」ということにされてしまうのではないか。
生物学的性差を否定しても、性別二元論を否定しても、「女性身体」は消えてなくならないし、「女性」の定義を変えても現実に女性が受けている差別はなくならない。バトラーを読んだところで今月も生理は来るし、私はパートナー(男性)には力で勝てないし、「ぶつかり男」は隣の中年男性ではなく私に体当たりする。「バトラーを読め」は、女性身体という現実を生きる当事者たる女性を黙らせる呪文のように、繰り返し繰り返し唱えられていた。
しかし、呪文を唱えても、彼らの言うところの「トランス差別者」「ヘイター」「TERF」は消えなかった。ずっと発言し続けた人たちがいたからだ。おかしいことはおかしいと言い続けた女性たちがいたからだ。その人たちに心からの敬意を表したい。


小川洋子『密やかな結晶』(新装版)
講談社文庫
2020年
記憶(言葉、認識)が少しずつ「消滅」していく島を舞台としたディストピア小説。多くの人たちが「消滅」に適応し、つい昨日まで大事にしていたものでさえ忘れていく一方で、記憶を失わない人々は秘密警察の「記憶狩り」から隠れて暮らしている。
「消滅」が起きると、人々は消えたものへの感情や感覚、記憶までも徐々に失ってしまう、という設定は、荒唐無稽に見えなくもないが、本来はあり得ないことに「徐々に馴らされていってしまうこと」というのは現実に起き得るし、「言葉が意味をなさなくなること」は「女性」という言葉を巡るここ10年弱の議論で経験済みだ。
隠した記憶のカケラを手に取り、それにまつわる思い出を語る人の姿に、少数の友人たちと慎重に言葉を選びながら、ネット上における議論の推移への疑問を打ち明けあった日々のことを思い出さずにはいられなかった。そして、その日々は、まだ完全に過去のものになってはいない。